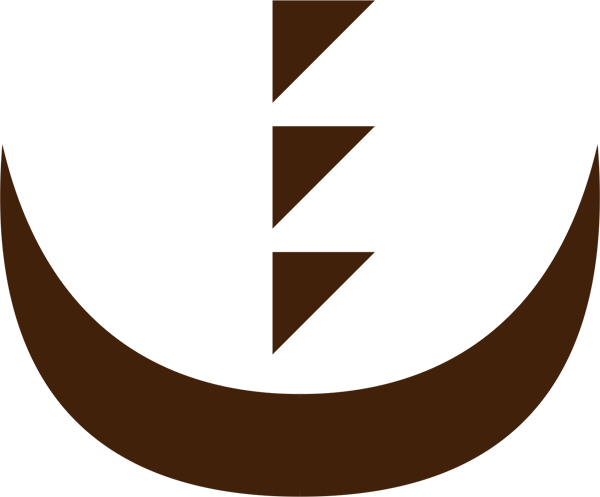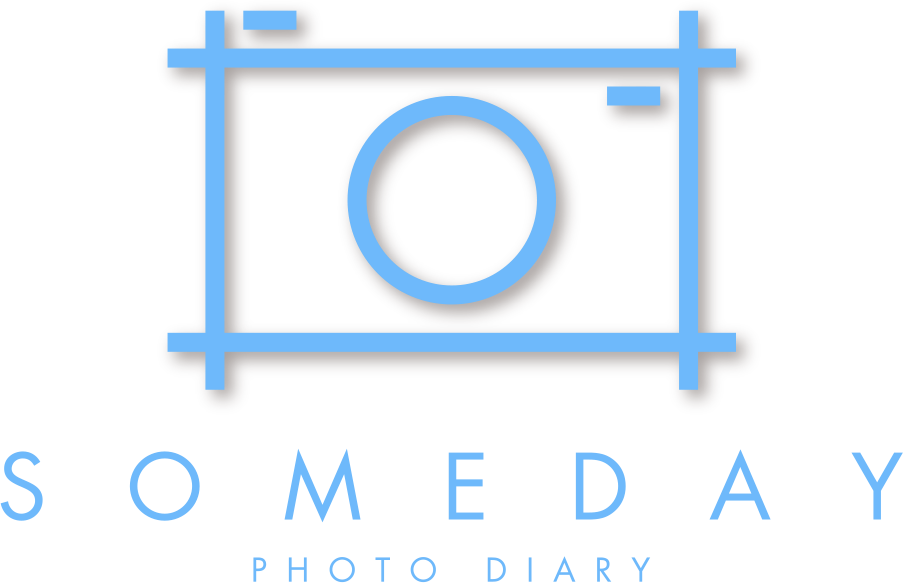home > 合唱団よびごえ

「合唱団よびごえ」は、2016年に東京学芸大学音楽科有志によって創設された合唱団です。声楽専攻の学生や、大学から合唱を始める学生など、様々なバックグラウンドをもつ団員が所属しています。現在は、学外での合唱祭やコンクール、学内での演奏会に出演する他、都内で活動する中高生と一緒に合唱をしたり、都外への勉強の旅も始めました。
「合唱×教育」をテーマに、ゆっくり時間をかけて、合唱の楽しさ、難しさを一緒に感じてもらえると嬉しいなと思います。新入団員、練習見学は随時ご相談ください!
問合せ:instaか、メールで!
本番の演奏について、みなさんの振り返りはどうでしたか?
技術的に・表現として・チームとして、後悔なく演奏できたでしょうか?小さくても大きくても、成長や新しい気付きがあったでしょうか?
本番から一日経ち、すでに新しい本番や目標に向かって、進み始めている方が多いと思います。僕は、今回の春こんを振り返ることで、春こんでのすべての学びに改めて感謝して、気持ちを一歩前に進めたいと思います。
今年度は、少数ながらもしっかりと頑張ってくれる女声に、男声が非常に厚い、そうしたチームだったように思います。例年と少し違う春こんのスタートとなったのは、男声合唱として参加するか・混声合唱にするか、新しいメンバーを募るか・現メンバーで出るか、そうした話し合いからスタートしたことでした。本番が終わって一日経ち、そういえば、この話し合いを受けて、一人ひとりの持っている強みやこれから伸ばしていってほしいなと勝手ながらも応援しているところなどを総合し、ほぼ1人1パートという、リスクある路線を決定したことを思い出しました。
伸ばしていってほしいなという点は、本当に人によってそれぞれでした。発声について何か僕が役に立てればいいなと思う方もいれば、耳の使い方を伸ばしていってほしいなという方もいました。チームを俯瞰しながらサポートしていく力を高めてくれるといいなと思った方もいれば、悩んだり困ったことがあれば自分だけで解決しようとせず、仲間に頼ることに価値を見出してくれるといいなという方もいました。
もちろんみなさんは、すでに持っているたくさんの素敵なところがあります。音楽に対していつでも真摯で誠実(全員ですね)、稽古場の雰囲気をぱっと明るくできる方、しっかりと譜読みをしてきてくれることで他の人の歌いやすさに貢献してくれた方、話し合いの時間になればファシリテーションしてくれる方、悩みが共有されれば自分はこう思うよと向き合ってくれる方、言葉には出さずとも水面下で誰かのためを思って行動してくれた方など。僕が言語化できていないだけで、もっともっと、あるんでしょう。
10月の稽古開始時と春こんが終わった今の自分を比較して、どんな新しい気づきがありましたか?なにが新しくできるようになりましたか?
これは、今でも、少し未来でも良いので、時間があるときに考えてみてもらえるといいなと思います。
僕がドラえもん好きというのは周知かもしれませんが、ドラえもんの素晴らしい設定の1つは、期限付きの友達、ということです。これは、児童・生徒からみたら、学校の先生も同じようなものですね。
僕とみなさんが密度高く関わりあえるのは、長い人で4年間です。その間に、どれだけの楽しい合唱体験を一緒にできるか、これは僕にとって、とても大きなミッションです。
「楽しい」というのは、僕は、「学びがある」状態だと思っているので、発声に自信がもてたりメカニズムに納得感が得られたり、作品を解釈したり表現したりすることに魅力を感じれたり、ハーモニーが決まったときの美しさに気づいたり、求められる知識・技能や協働学習という側面も含めて合唱ってこういう良さや難しさがあるんだと気づいたり、将来先生になったときに自分だったら子どもたちのためにこうしてみたいという希望が持てたり。
近い将来、みなさんは、子どもたちにとってのドラえもんになると思います。ドラえもんと一緒にいるとなんでもできるような気がして、声の出し方に自信がもてたり、作品のもつとっても美しい世界を見せてくれたり、一緒に合唱する仲間みんなを愛せるようになったり、そうして、音楽が大好きな子を育てていくんでしょう。
僕は万能ではありませんので、ドラえもん先生はすごいなと思いますが、今回の春こんを通して、声の出し方にちょっとでも理解が深まったり、新しくできるようになったことがあったならばよかったなと思いますし、デーモンやスリープの世界とその良さを味わってもらえていたら嬉しいなと思いますし、よびごえのメンバー一人ひとりのことを、今までよりもさらに愛してくれればうれしいなと思います。
本番後、結果発表後、はるとさんのシェアくださった音源を聴いて、僕の指導上の不足が多かったことには、素直に反省していますし、力不足を、本当に申し訳なく思っています。ピッチについてもっと丁寧に稽古すればよかったですし、言葉のさばきと輪郭について厳格にこだわればよかった、和声の確定のためにパート間のバランスをもう少し慎重に構築すればよかった、cresc. decresc.の計画をもっと厳密にルール化すべきだったなど、後悔は絶えません。これは、完全に僕の責任でした。
次回の春こんは、もしみなさんが望んでくれれば、今回のメンバーをベースに、新メンバーを加えて、もう一度合唱ができればいいなと思っています。
次なるは新歓。
新しい目標に向けて、またスタートしましょう。
みなさんと一緒に学ぶことのできた今年の春こんに、とても感謝しています。 小田直弥…
「合唱×教育」をテーマに、ゆっくり時間をかけて、合唱の楽しさ、難しさを一緒に感じてもらえると嬉しいなと思います。新入団員、練習見学は随時ご相談ください!
問合せ:instaか、メールで!
24
February
2026
2026
【2025】よびごえ日誌 vol.8 春こんを終えて
春こん、本当にお疲れさまでした。本番の演奏について、みなさんの振り返りはどうでしたか?
技術的に・表現として・チームとして、後悔なく演奏できたでしょうか?小さくても大きくても、成長や新しい気付きがあったでしょうか?
本番から一日経ち、すでに新しい本番や目標に向かって、進み始めている方が多いと思います。僕は、今回の春こんを振り返ることで、春こんでのすべての学びに改めて感謝して、気持ちを一歩前に進めたいと思います。
今年度は、少数ながらもしっかりと頑張ってくれる女声に、男声が非常に厚い、そうしたチームだったように思います。例年と少し違う春こんのスタートとなったのは、男声合唱として参加するか・混声合唱にするか、新しいメンバーを募るか・現メンバーで出るか、そうした話し合いからスタートしたことでした。本番が終わって一日経ち、そういえば、この話し合いを受けて、一人ひとりの持っている強みやこれから伸ばしていってほしいなと勝手ながらも応援しているところなどを総合し、ほぼ1人1パートという、リスクある路線を決定したことを思い出しました。
伸ばしていってほしいなという点は、本当に人によってそれぞれでした。発声について何か僕が役に立てればいいなと思う方もいれば、耳の使い方を伸ばしていってほしいなという方もいました。チームを俯瞰しながらサポートしていく力を高めてくれるといいなと思った方もいれば、悩んだり困ったことがあれば自分だけで解決しようとせず、仲間に頼ることに価値を見出してくれるといいなという方もいました。
もちろんみなさんは、すでに持っているたくさんの素敵なところがあります。音楽に対していつでも真摯で誠実(全員ですね)、稽古場の雰囲気をぱっと明るくできる方、しっかりと譜読みをしてきてくれることで他の人の歌いやすさに貢献してくれた方、話し合いの時間になればファシリテーションしてくれる方、悩みが共有されれば自分はこう思うよと向き合ってくれる方、言葉には出さずとも水面下で誰かのためを思って行動してくれた方など。僕が言語化できていないだけで、もっともっと、あるんでしょう。
10月の稽古開始時と春こんが終わった今の自分を比較して、どんな新しい気づきがありましたか?なにが新しくできるようになりましたか?
これは、今でも、少し未来でも良いので、時間があるときに考えてみてもらえるといいなと思います。
僕がドラえもん好きというのは周知かもしれませんが、ドラえもんの素晴らしい設定の1つは、期限付きの友達、ということです。これは、児童・生徒からみたら、学校の先生も同じようなものですね。
僕とみなさんが密度高く関わりあえるのは、長い人で4年間です。その間に、どれだけの楽しい合唱体験を一緒にできるか、これは僕にとって、とても大きなミッションです。
「楽しい」というのは、僕は、「学びがある」状態だと思っているので、発声に自信がもてたりメカニズムに納得感が得られたり、作品を解釈したり表現したりすることに魅力を感じれたり、ハーモニーが決まったときの美しさに気づいたり、求められる知識・技能や協働学習という側面も含めて合唱ってこういう良さや難しさがあるんだと気づいたり、将来先生になったときに自分だったら子どもたちのためにこうしてみたいという希望が持てたり。
近い将来、みなさんは、子どもたちにとってのドラえもんになると思います。ドラえもんと一緒にいるとなんでもできるような気がして、声の出し方に自信がもてたり、作品のもつとっても美しい世界を見せてくれたり、一緒に合唱する仲間みんなを愛せるようになったり、そうして、音楽が大好きな子を育てていくんでしょう。
僕は万能ではありませんので、ドラえもん先生はすごいなと思いますが、今回の春こんを通して、声の出し方にちょっとでも理解が深まったり、新しくできるようになったことがあったならばよかったなと思いますし、デーモンやスリープの世界とその良さを味わってもらえていたら嬉しいなと思いますし、よびごえのメンバー一人ひとりのことを、今までよりもさらに愛してくれればうれしいなと思います。
本番後、結果発表後、はるとさんのシェアくださった音源を聴いて、僕の指導上の不足が多かったことには、素直に反省していますし、力不足を、本当に申し訳なく思っています。ピッチについてもっと丁寧に稽古すればよかったですし、言葉のさばきと輪郭について厳格にこだわればよかった、和声の確定のためにパート間のバランスをもう少し慎重に構築すればよかった、cresc. decresc.の計画をもっと厳密にルール化すべきだったなど、後悔は絶えません。これは、完全に僕の責任でした。
次回の春こんは、もしみなさんが望んでくれれば、今回のメンバーをベースに、新メンバーを加えて、もう一度合唱ができればいいなと思っています。
次なるは新歓。
新しい目標に向けて、またスタートしましょう。
みなさんと一緒に学ぶことのできた今年の春こんに、とても感謝しています。 小田直弥…
現役チーム

石川花世Hanayo Ishikawa

石丸徳Megumi Ishimaru
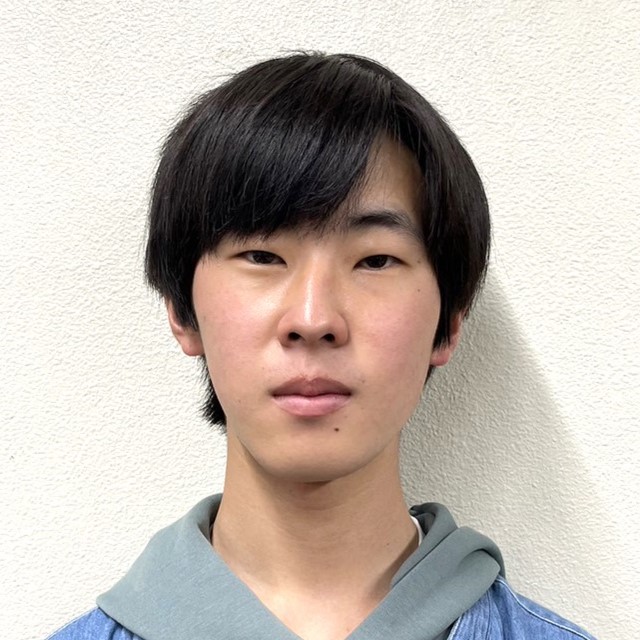
井藤一輝Kazuki Itou

伊藤陽杜Haruto Itou

加藤優奈Yuna Kato

小林翔人Shouto Kobayashi

佐藤光紀Kouki Sato

佐藤七海Nanami Sato
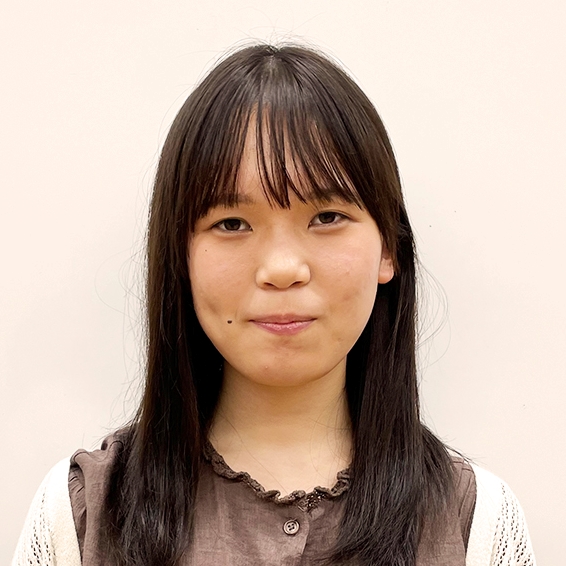
新喜真由音Mayune Shinki

辰川真奈美Manami Tatsukawa

真鍋翔吾Shogo Manabe

室伏萌衣Mei Murofushi
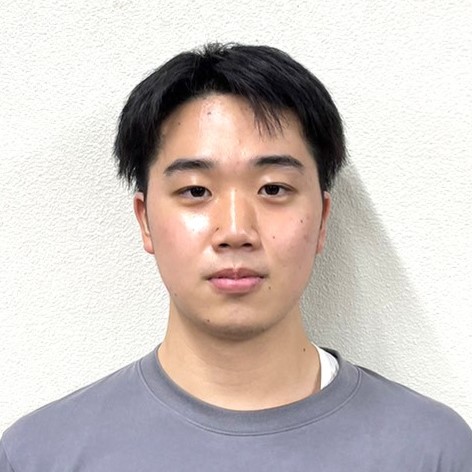
柳本泰佑Taisuke Yanagimoto
OB/OG

泉晴陽Haruhi Izumi
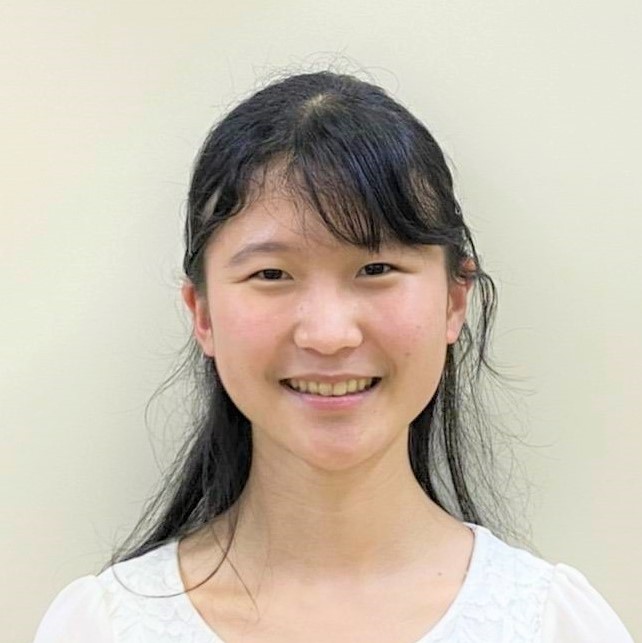
一柳優里愛Yuria Ichiyanagi

井出哲Satoru Ide
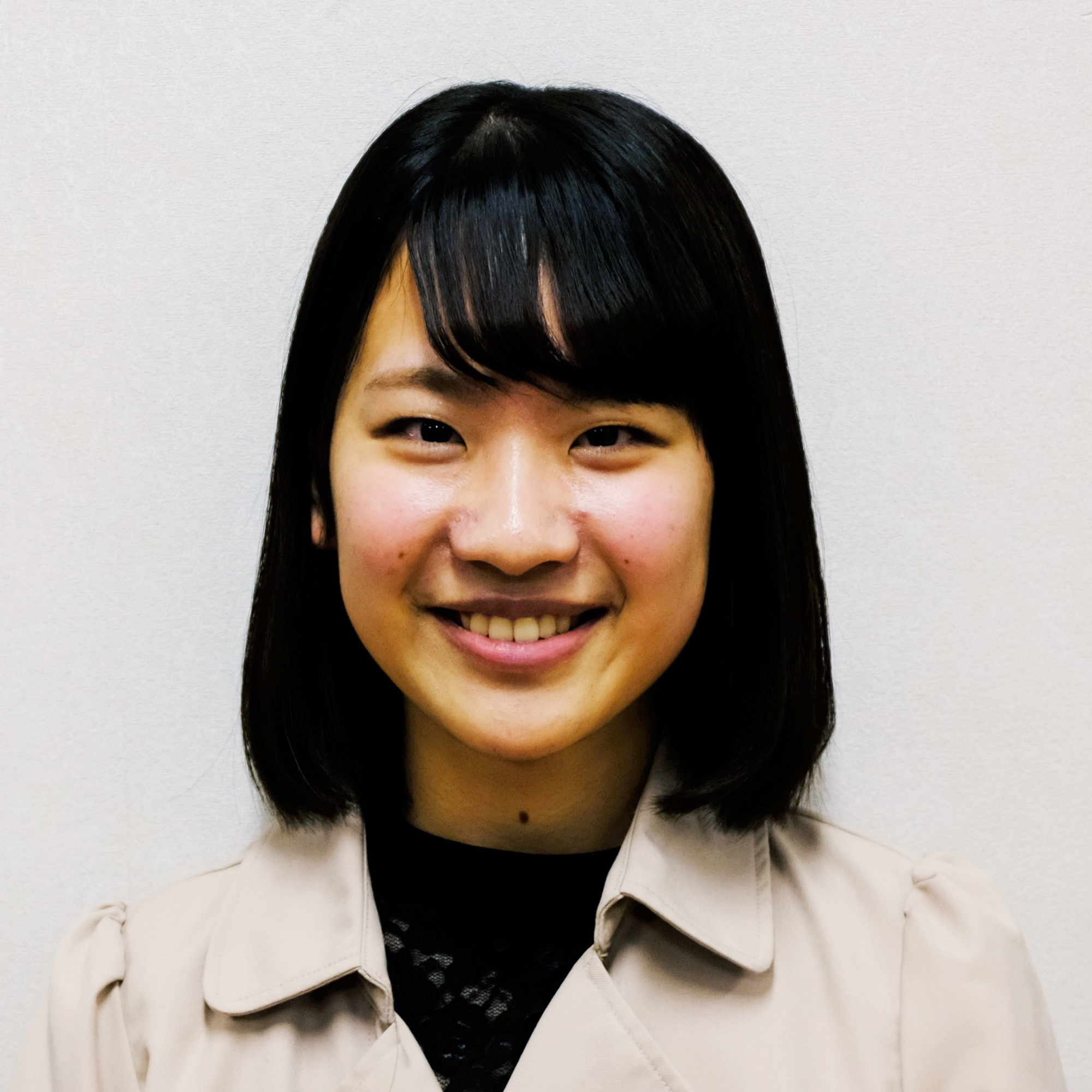
伊藤真緒Mao Itou
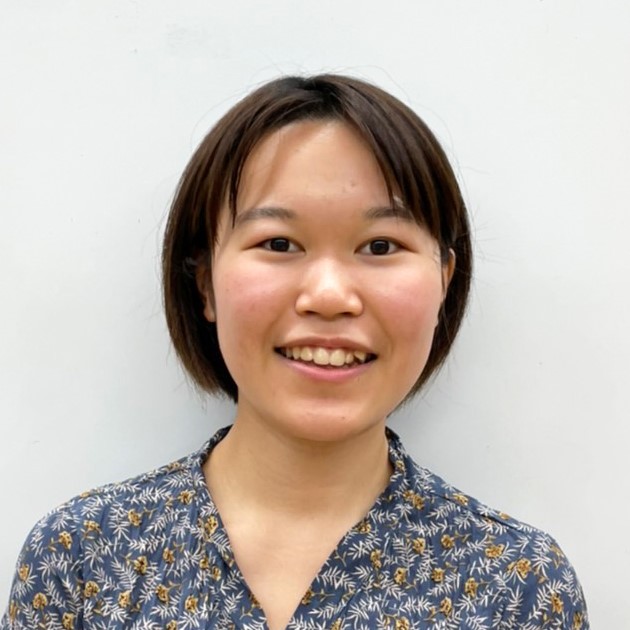
稲村歌乃Utano Inamura

伊野綾那Ayana Ino
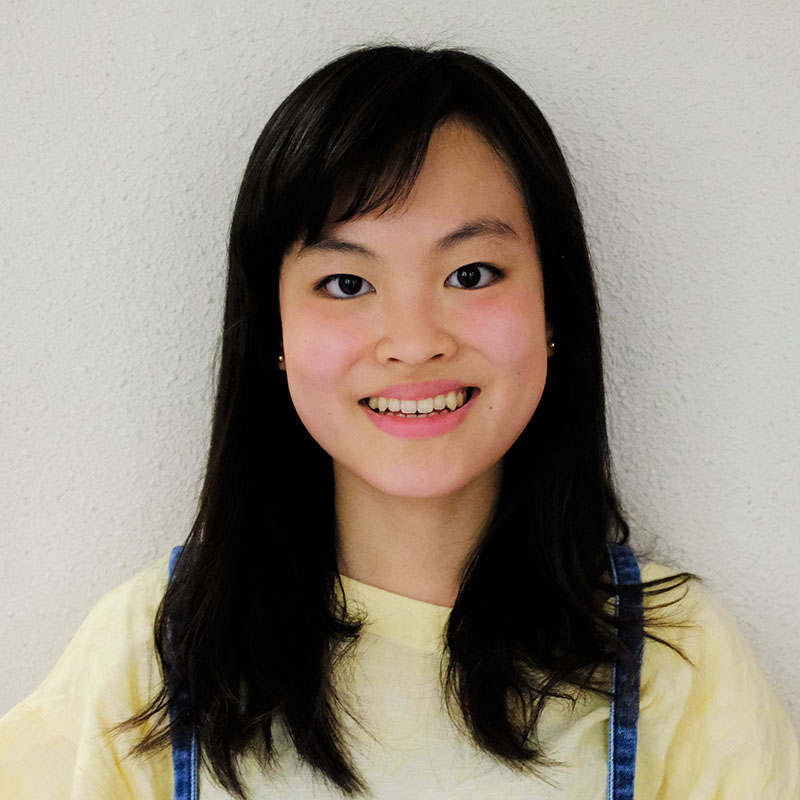
今城琴美Kotomi Imajo

大野菜々Nana Ohno
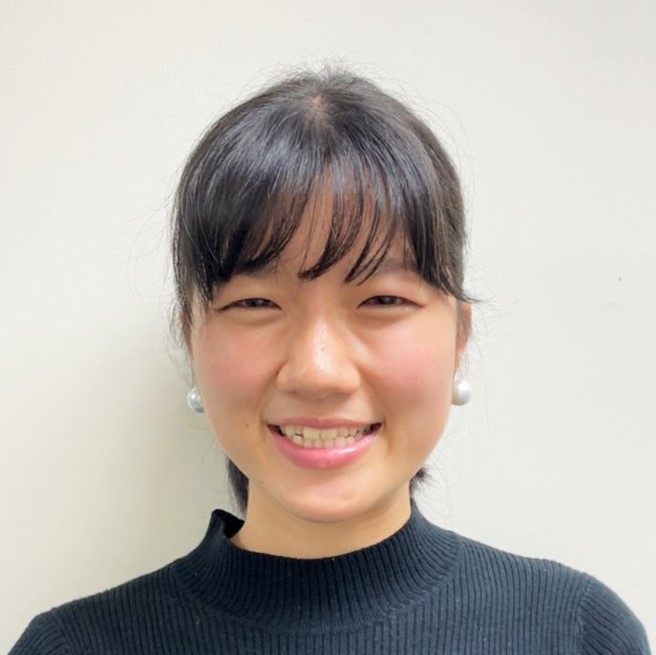
大瀧夏未Natsumi Ohtaki

神谷咲妃Saki Kamiya
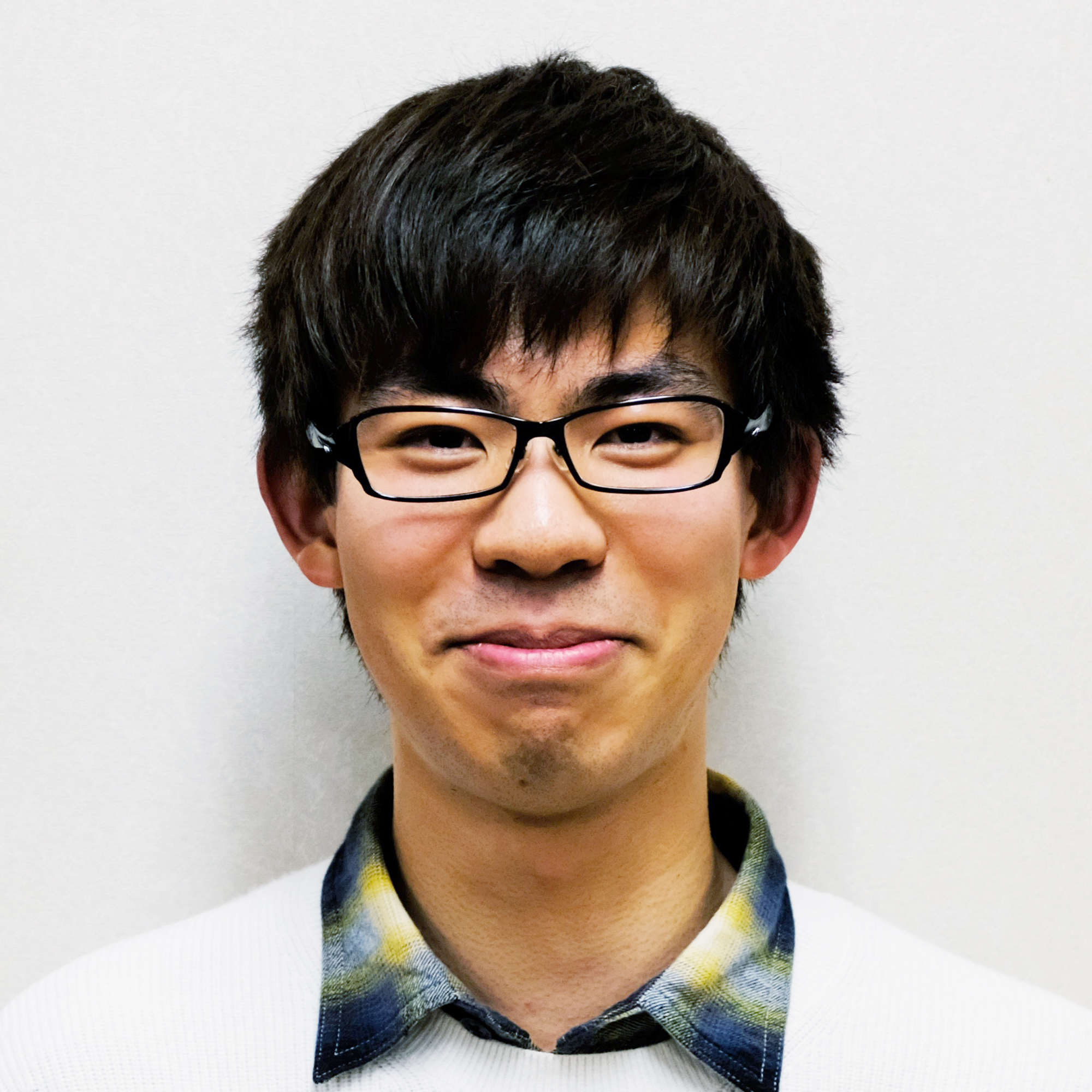
草野圭祐Keisuke Kusano
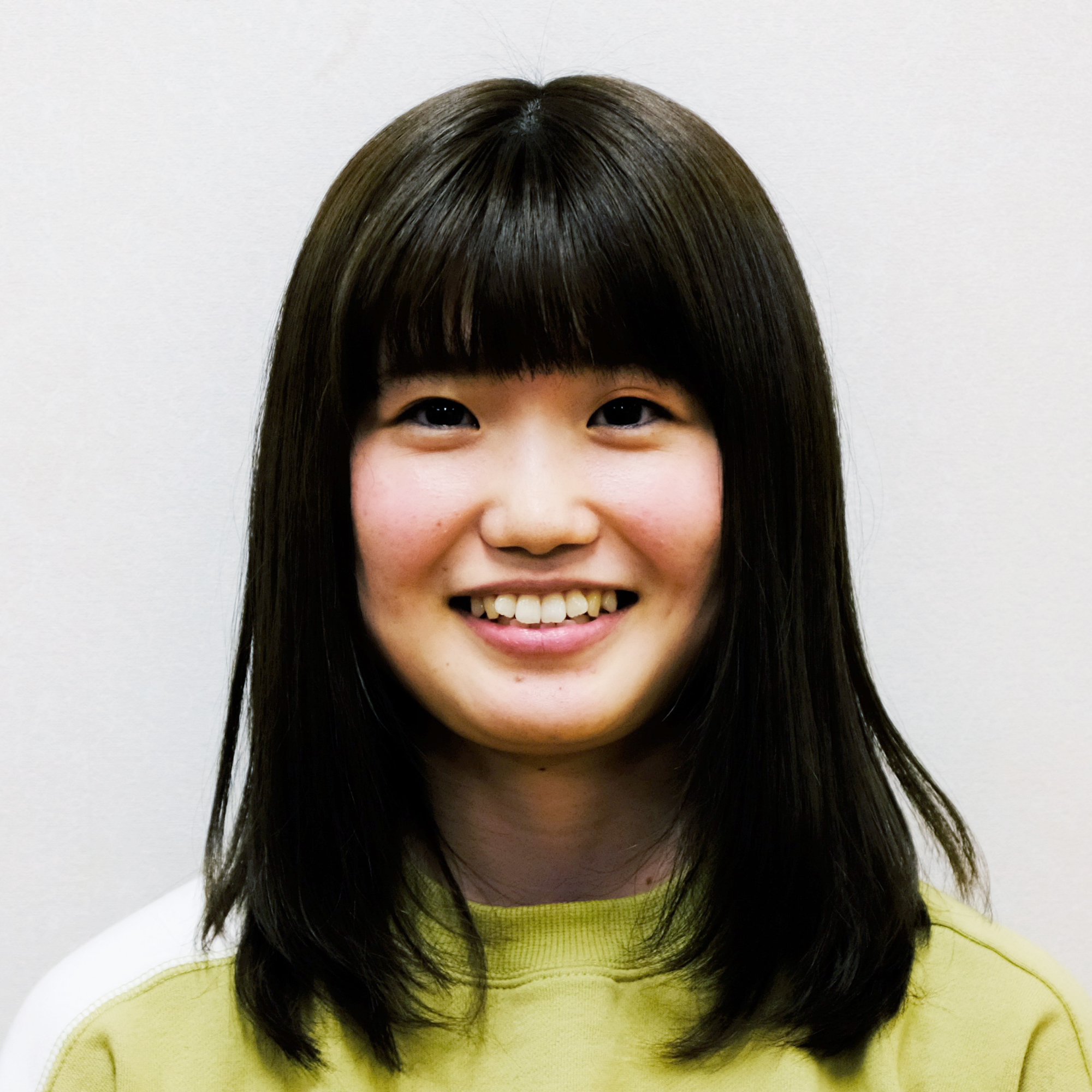
國元美乃里Minori Kunimoto

小金澤萌花Moeka Koganezawa

佐藤花音Kanon Satou

鈴木慧Kei Suzuki

滝澤奏有美Sayumi Takisawa
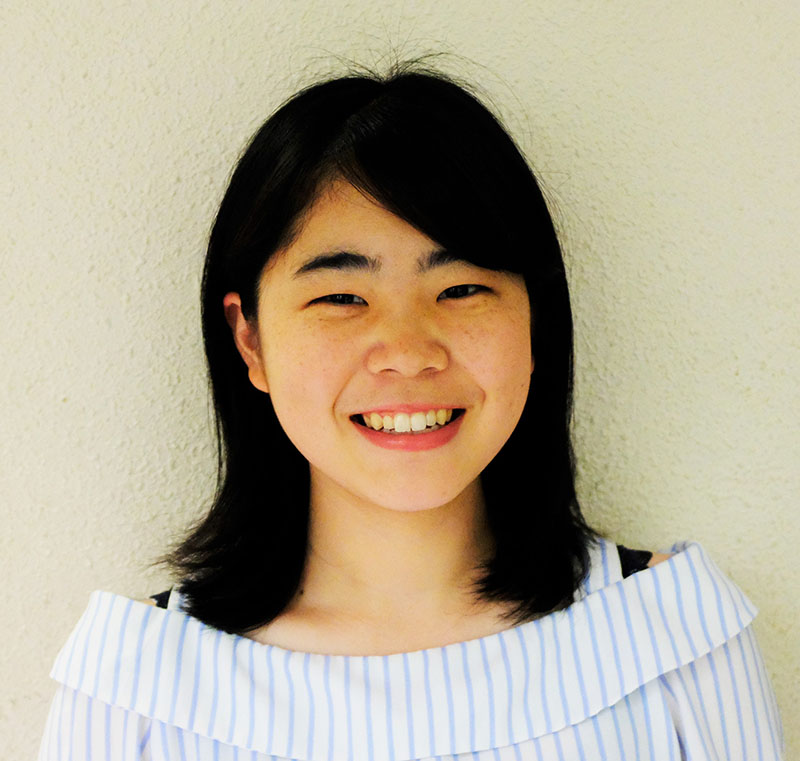
谷夏七星Nanase Tani
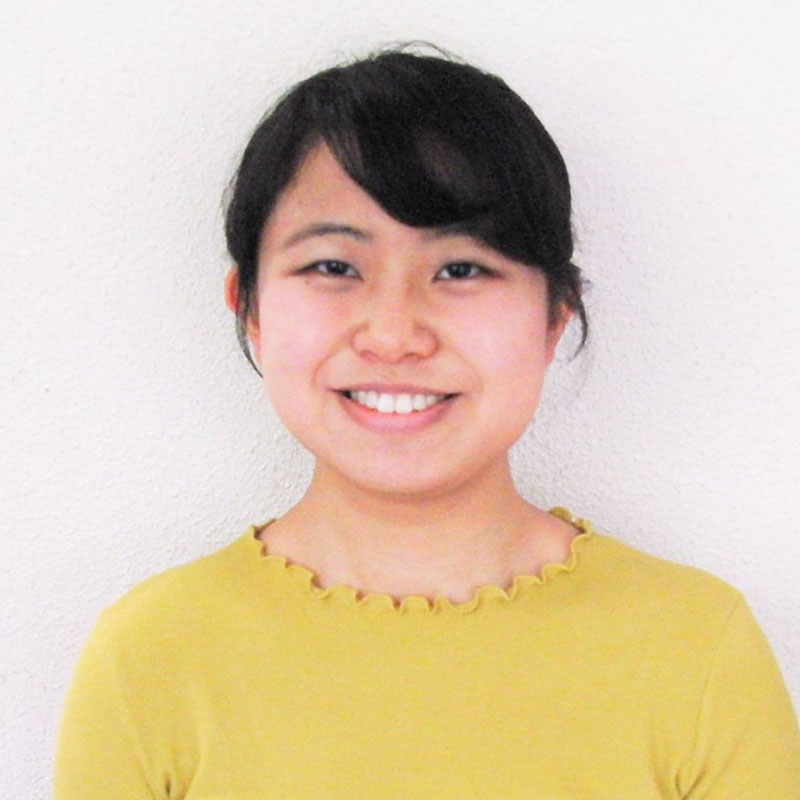
土屋七海Nanami Tsuchiya

中島菜々子Nanako Nakajima

名嘉眞静香Shizuka Nakama
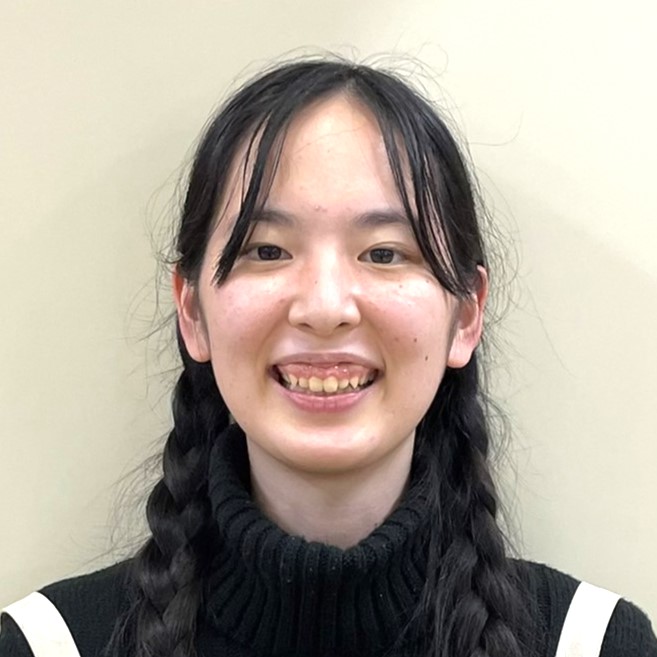
萩原春花Haruka Hagiwara

濱野瑞貴Mizuki Hamano
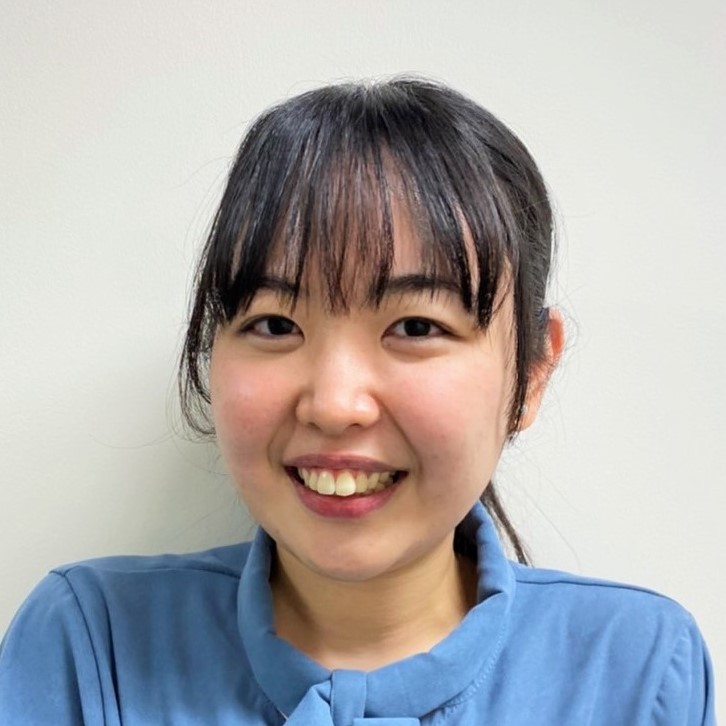
原田綾乃Ayano Harada
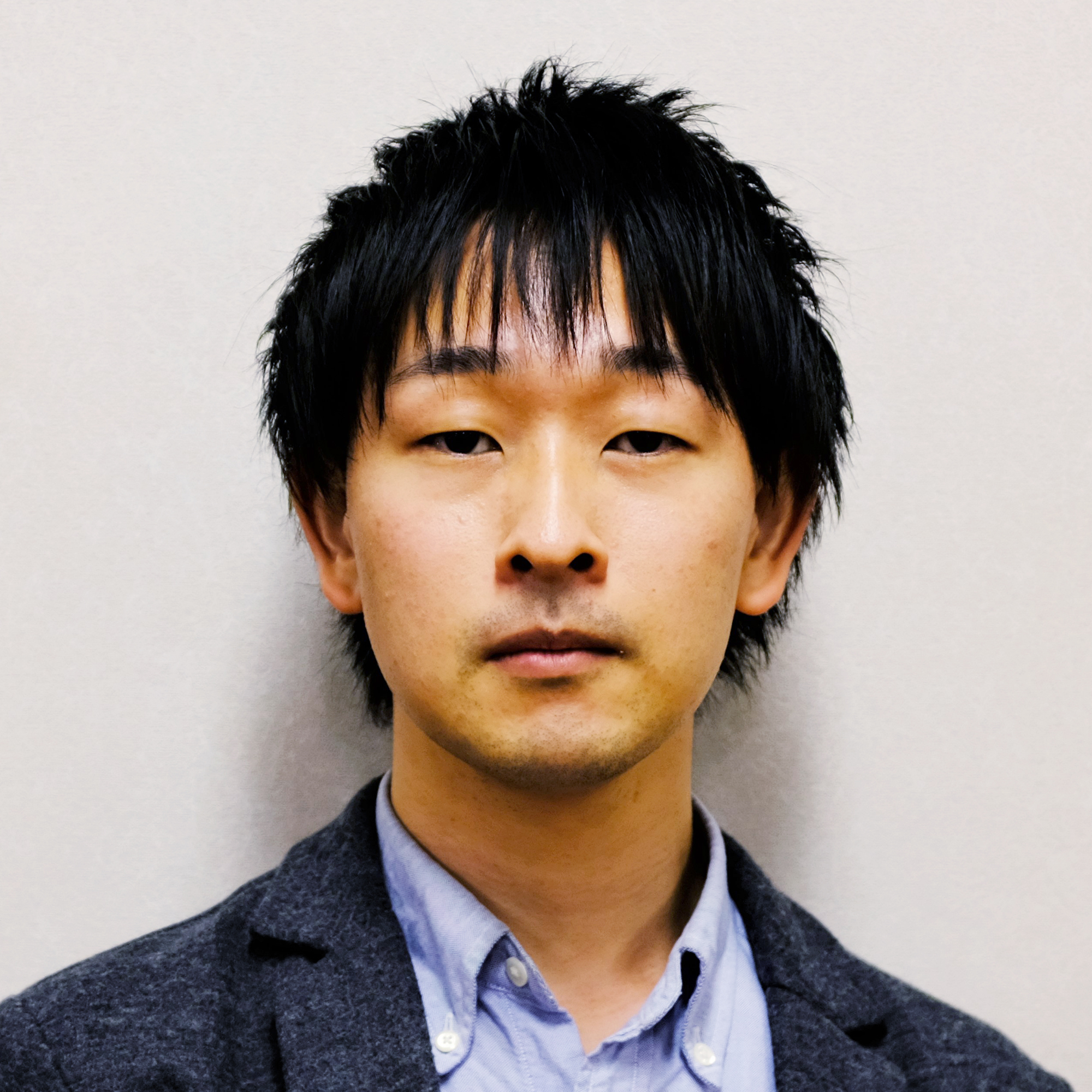
笛木和人Kazuto Fueki

藤原改Kai Fujiwara
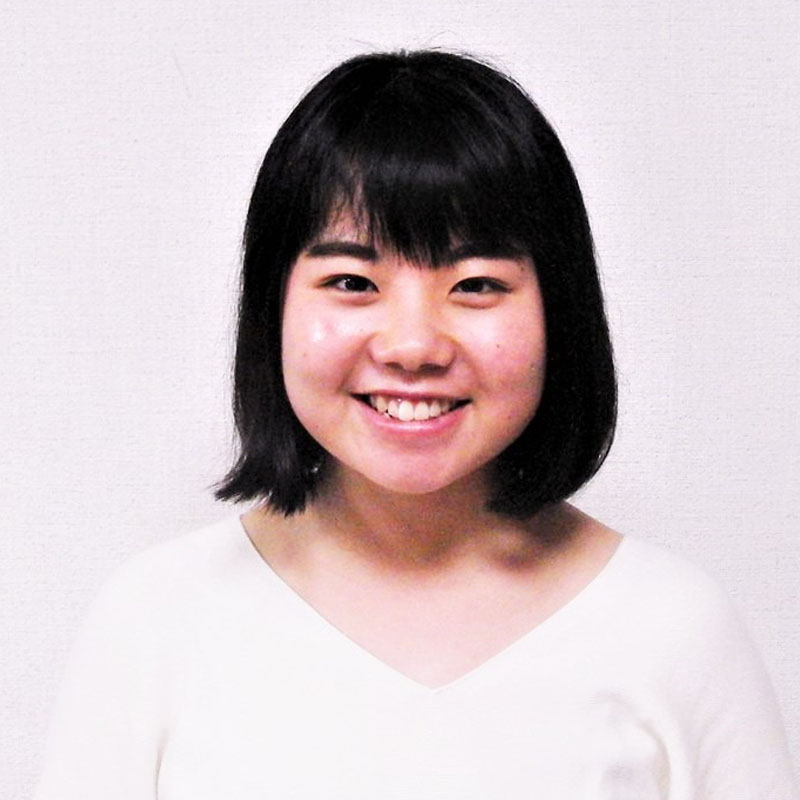
堀切彩愛Sae Horikiri

槇佳絵子Kaeko Maki
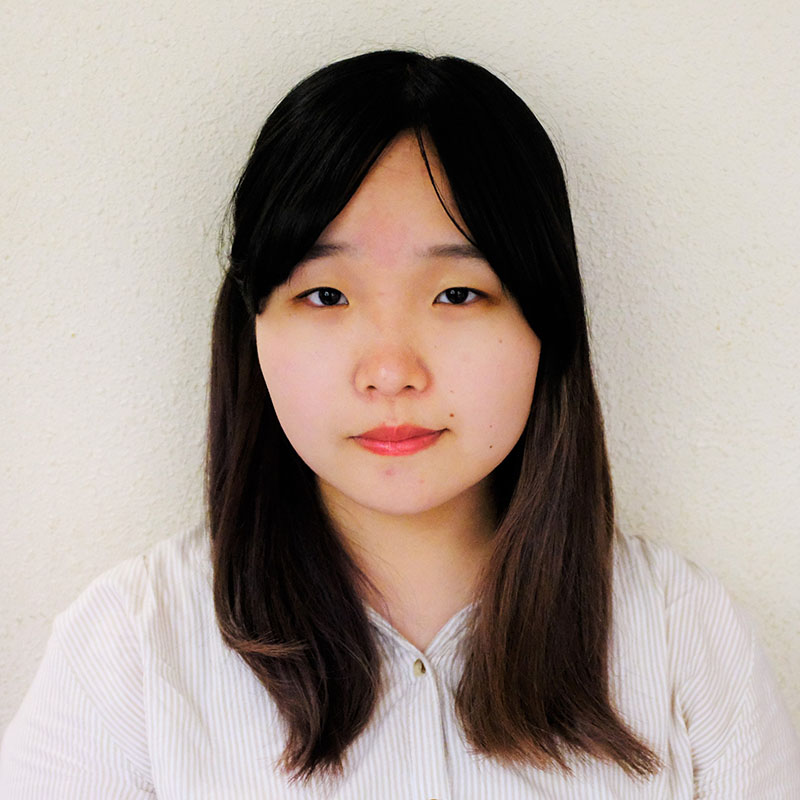
松本夏実Natsumi Matsumoto
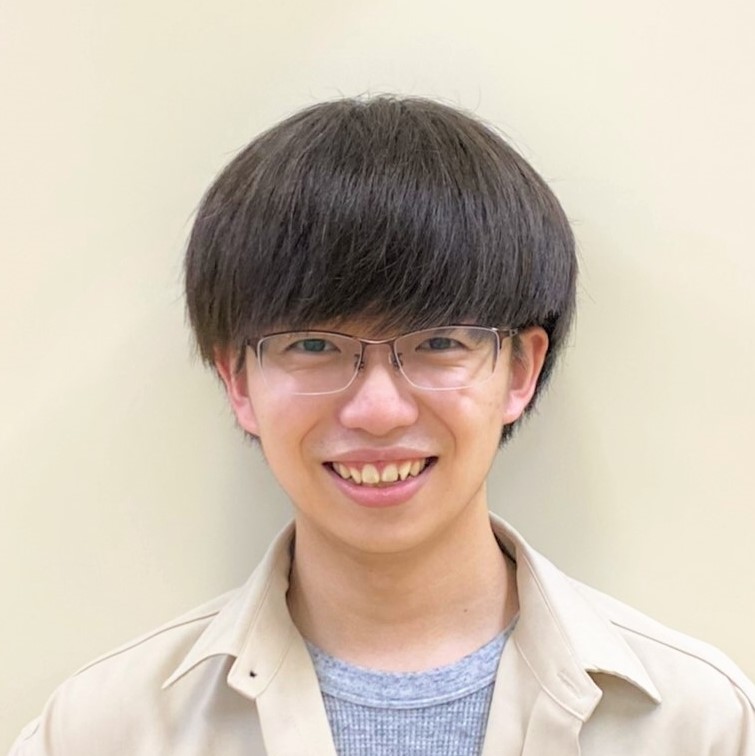
丸大喜Daiki Maru

森本侑花Yuka Morimoto
history
21
July
2025
2025
第80回東京都合唱祭
「こころよ うたえ」(一倉宏詩/信長貴富曲)
「Go the Distance」(David Zippel詩/Alan Menken曲/Ed Lojeski編)
ピアノ:鈴木楓雅さん(賛助)
02
March
2025
2025
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2025 銀賞
「クラシック・現代音楽部門(指揮あり)混声」
混声合唱のための『あい』より「あい」(谷川俊太郎詩/松下耕曲)
「Nyon Nyon」(Jake Runestad曲)
20
February
2024
2024
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2024 銀賞
「ユースの部 混声」
混声合唱のための『だるまさんがころんだ』より「Ⅰ」(矢川澄子詩/長谷部雅彦曲)
混声合唱のための『風の馬』より「第3ヴォカリーズ」(武満徹曲)
※演奏作品の説明は、Youtubeの概要欄に記載しました。