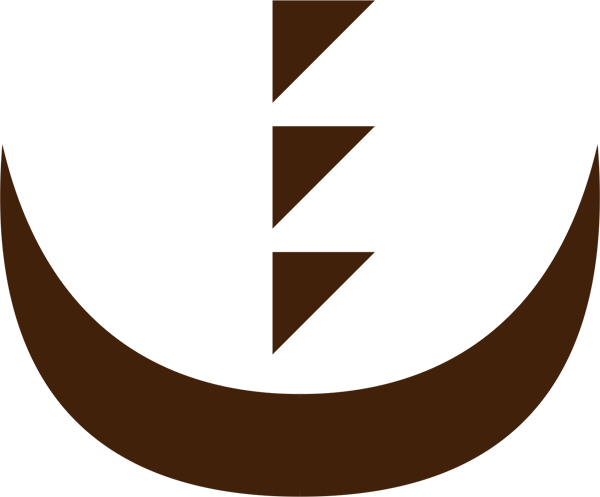home > メッセージ
タグ:メッセージ
30
May
2024
2024
【2024】よびごえ日誌 vol.1
春こん本番からもうすぐ4か月が経とうとしている今、前年度の活動を振り返ろうと思います。この日誌を書き始めてからは3か月が経ちました。自分の筆の遅さにびっくりです。合唱とは何か。ある日、小田さんから問いがありました。
【合唱】複数人で声を合わせて歌うこと…?とそのとき頭に浮かびましたが、そういうことじゃないんだよなと思い、それからずっと考えていました。3か月以上のんびり考えて、なんとなく答えの輪郭が浮かび上がってきたように思います。まだ答えが出ていないなんてのんびりし過ぎでしょうか…。ですが私にとって合唱とは何かということについて色々と考えているうちに、自分が教員になったときに、子どもたちに合唱ってどんなものだって思ってほしいんだろう、学校生活や私の授業を通してどんな世界に出会ってほしいんだろうという問いも生まれ、自分の教育観についても考えるきっかけにもなりました。
2023年の春こんに、よびごえのメンバーとして出場することを私は諦めました。(今でも後悔していることの一つです。)よびごえの活動を休んでいる間、もし復帰したとしたらまたみんなの足を引っ張ることになるのではないかという思いがずっとありました。1年生の時の感覚が戻ってきたようでした。1年生の時の私は合唱未経験で、毎回の稽古について行くことだけでいっぱいいっぱいでした。今思えば、ついて行くことすらできていなかったかもしれません。譜面から読み取ったこと、考えたことを具体的な技術に反映させて伝えることが重要なんだなぁ。でも、どうすればいいの?音を並べるだけで精一杯なんだよな。怒られたくないし、できないやつだと思われたくない。みたいな状態で、稽古後の振り返りではそれらしいことも言ったりして、背伸びしちゃったりもしていました。ただ足を引っ張っているということだけは毎回の稽古で感じていましたし、帰りの電車では泣いちゃいそうでした(笑)でも寝たらある程度忘れてしまって、それが良いんだか悪いんだかという感じですね。なんか、楽しいかも…?と感じた瞬間もたしかにありました。ですが、1年生のときに出た春こん後、正直合唱が好きなのかはまだわかりませんでした。当時を振り返って、そんな精神状態でよく辞めなかったなと思います(笑)こんな書き方をするとどんなスパルタ稽古なんだと思われるかもしれませんが、私が卑屈なだけで、毎回の稽古はメンバーに刺激を受け、新たな視点をもらえる充実したものでもありました。なので、これからよびごえに入ろうかな~と考えている方、ご心配なく。
よびごえに復帰した私は3年生になっていました。よびごえには1年生(私がのろのろ日誌を書いていたせいで年度が変わってしまいました。今ではもう2年生ですね、びっくり。)が4人も入ってきてくれました。うれしかった。音楽するぞ!という明るいエネルギー満ちていて、みんなの個性豊かなキャラクターや考えに触れ、なよなよしている場合じゃないぞと復帰後の私は踏ん張れました。また、尊敬する同期、後輩、先輩の存在にも心救われました。そして執行代にもなったということで、運営のための仕事も担うようになりました。大変さや責任の重さだけでなく、今までよびごえをつないできてくださった先輩方や小田さんの存在の大きさも改めて実感しました。よびごえの一員として稽古ができることや本番に臨めることが本当に有難く、幸せなことだなと思います。
春こんに向けた稽古を振り返って、今年度の活動に生かしたいことは、「反省会をするタイミングに気を付けること」「言語化することから逃げないこと」の2点です。
① 反省会をするタイミングについて
今回の春こんで歌った風の馬第3ヴォカリーズとだるまさんはずっと難解な曲でした。正直、本番当日を迎えても詰め切れていない部分というか、まだわからない部分がありました。だるまさんは物語の展開が早くパニック、風の馬もだるまさんよりかはテンポがゆっくりですがどこか掴めない感じがあって気が付いたら場面が変わります。そのために、演奏するときは次をどう歌うか、次、次、、という思考が重要だと感じました。私は稽古中に自分の中で反省会を開催してしまっています。ここが納得いかない、あちゃー、息がうまく吸えないのはどうして?この和音合ってる?など、歌いながら、もう過去となったことばかり考えてしまっています。改善点をあぶりだすことはもちろん重要ですが、本番や稽古の特定の場面においては時間を割くところはそこではなく、常に先のことを考える必要があると思いました。そうすることで、自分がどう歌いたいのかということを考えるのに集中することができます。また、もう変わらない過去のことより、自分次第で変えられる未来のことを考えたほうが精神衛生上良いなとも思いました。小田さんが以前どこかで、合唱は心のハーモニーだとおっしゃっていたと記憶にあるのですが、そのときはどういうこっちゃと思っていました。ですが、春こんの練習を通して、精神面が演奏に大きく影響することを身を持って学びました。気分の落ち込みを回避するため、これからは反省会をむやみやたらに開催しないことを誓います。
② 言語化すること
理論派か感覚派か。音楽科の仲間との間でもよく話題に上ります。私は、自称インプットは理論派、アウトプットは感覚派です。何かを教わるとき、順を追って一つ一つかみ砕きながらインプットしたほうが頭に入りやすいです。反対にアウトプットするときは、伝えたいことに適した言葉を見つけるということを簡単に放棄して、表情や身振り、擬音で押し出しか浴びせ倒し、が基本技という感じですね。昨年度の稽古で、自分の気持ちや考えを他者と交換することでだんだんとチームになれるのかなと思ったので、大事な場面で自分の考えや気持ちをきちんと言語化して伝えることから逃げないようにしたいなと思いました。
春こんを終えたみんなは一つ山を登ったからね、と小田さんが先日おっしゃっていました。春こんが山登りだとしたら、私たちはどんな山を登ったのかなぁ、私はみんなと一緒に登れたのかな、山だと思って実は丘を登っていたんじゃないだろうか、景色を楽しむ余裕はなかったなぁ(笑)、頂上はどこだったんだろう、と色んな考えや稽古での出来事が頭の中を巡って、夜しか眠れませんでした。今年もみんなで山登りができるといいです。
昨年度は、かわいい後輩と頼れる?同期、優しく聡明な先輩方、いつでも徳の高い小田さんと学ぶことができて、とても充実した一年でした。ようやく合唱が楽しいと思えた一年でした。
今は、今年度のよびごえがどのようなチームになってどんな音楽に出会うことができるのか楽しみです。また、よびごえラストイヤーなので、後悔が少なくなるよう、頭フル回転で毎回の稽古や本番に臨みたいです。 稲村歌乃…
04
March
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.13
こんにちは、1Bの柳本泰佑です。よびごえ日誌なるものを初めて書いてみようと思います。私は他のメンバーのように文才がないので、稚拙で短い物となりますが、見返すときの未来の自分は優しいですよね?許してください。よびごえに入って一年間、多くのことを学んだと思う。音程の取り方、和声の感じ方といった細かい技術から、音楽の形而上的な事柄まで。小田さんだけでなく、他のメンバーからも学ぶことがたくさんあった。よびごえの文化である、「振り返り」はよくできたものだと思う。その日に得た学びというものを、言語化というプロセスまでもっていき相手に伝える。一度言葉に変換できたものは忘れないし、その後の音楽活動の糧にできる。聞く人は、その人の人となりや価値観、音楽的な気づきを受け取ることができる。「振り返り」という時間が、歌い手の、そして合唱団の音楽を潤沢にしていることに気づいた。そしてよびごえ日誌もまさに振り返り。でもなかなか手を付けられず今日まで来てしまった。小田さんが下さったせっかくの機会を大切にしないとね。
春コン、お疲れさま。2曲とも、音程はすこぶる取れないし、味わい方を知らないと面白くもない、難曲でしたね。でも、これらの曲だからこそ、今まで以上に音楽に向き合えた。そしてまた、一つの言葉に出会った。それは「音楽が、技術に先行する」というもの。すべての音楽活動には、技術と音楽性の2つの要素が存在する。しかし、そこには順番があり、常に、こうしたいという音楽の理想の形が先にあって、それを実現するための手段として技術が待ち構えている。とかく、技巧的で、常人にはできない芸当をやってのける人が「うまい」や優秀と思われることが多い。でもそれは、技術が音楽性をおいて独り歩きしているように私は感じる。音楽を志す者は常に、どんな音色、風景、ニュアンスで、というものを頭の中で音響を正確に再現し、それと現実とのギャップを、技術を用いて埋めていく工程を繰り返す。そうしていく中で、自分自身がその音楽の良さを味わえるようになる。ここまでくれば、どんな音を聴いてほしいのか、何を表現したいかが明確になるし、そのころには身体もついてきてくれる。その結果、予定調和ではないその人の「心」から湧き出る音楽をステージの上で表現することができるのだと気づくことができた。一つ、その人の音楽性の高さや音楽の才能と呼ばれるものがあるならば、それは、その人が頭のなかで、ものすごく素敵で人の心を揺さぶるような音楽を創造できる力のことだと思う。
ほかにも学んだことは多くありますが、全部書くと全くまとまらなくなってしまうし、読み返す気がかなり失せる気がするのでこの辺で終わりにします。
小田先生、そしてよびごえの皆さん、この一年間ありがとうございました。これからもお世話になると思います。よろしくお願いいたします。 柳本泰佑…
01
March
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.12 選曲への考え方
こんにちは。小田です。よびごえ日誌について、僕も更新ができておらずに申し訳ありませんでした。
※ごめんなさい、超長文です。
今年度は2月12日に春こん。を終えることができ、誰一人欠けることなく演奏できたことをとても嬉しく思っています。また当日はOGの先輩が応援に駆けつけてくださり、とてもありがたかったです。
今回の自由曲は以下の2曲。
混声合唱のための『だるまさんがころんだ』より「Ⅰ」(矢川澄子詩/長谷部雅彦曲)
混声合唱のための『風の馬』より「第3ヴォカリーズ」(武満徹曲)
相変わらずよびごえでは、「今年はこの曲をやるのね!」ではない、「???なんだこの曲は?」という選曲になりました。悩みに悩んだことは、前回のよびごえ日誌で書いた通りですが、改めて、今回の選曲のポイントを、記録として書いておきたいと思います。
➀いまいるメンバーでなければできない作品であること
➁いまもっている能力ではできない作品であること
➂数か月をかけて取り組むに値する内容や背景をもった作品であること
➃聴衆とも合唱の良さを分かち合える作品であること
とても初歩的な話をするならば、「(小田が)やりたい作品だから」「流行っている作品だから」ということではなく、教育的に価値ある作品であるかどうか、つまりは取り組むことでよびごえメンバー1人1人に何かしらの変化が期待できるかどうかを検討するための観点とも言うことができるかもしれません。
➀いまいるメンバーでなければできない作品であること
音域や声質といった技術面や、メンバー同士でのコミュニケーションのスムーズさや困難な状況下における粘り強さといった人間性やメンタル、詩や音楽への柔軟な発想(解釈)ができるという想像力や創造力など、いくつかの側面から、まずは、メンバ―1人1人の強みやこれから伸ばしていきたいところ、団体としてのポテンシャルを総合的に考えることが重要です。
合唱はチームであることから、一人ひとりがすべての観点で高い能力をもっている、ということが求められるわけではありません。あるメンバーが技術面で高い能力を持っていれば、その人がある程度は技術面で団をリードしてくれるかもしれません。一方で技術面はもう少し伸ばしていきたいけれども、想像力や創造力はキラりと光るものをもっている方もいますね。場を和ませたり、笑いをおこすことのできる方もとても貴重です。
いまのチームを構成する一人一人はどういうことが強みで、グループとして見たときにはどういう強みや課題をもったチームなのか、ここまでを整理すれば、あとはメンバー一人ひとりの強みが十分に発揮できるように、そして課題はちょっとでも自信に変えていけるような、そうした選曲ができれば、今いるメンバーで演奏する価値が生まれてくるように思います。
逆に言えば、そうしたメンバーやチームの分析無くして選曲をする場合、本当にこのメンバーで演奏する価値とは何だったのかを見失うときが来るかもしれません。仮にものすごく明るいキャラクターの方が集まっている団に、「戦争の苦しみ」をテーマとする曲を選んだとして、技術的にはクリアできたとしても、それを私事として捉え、仲間とともに心から共感して歌うことはできないかもしれません。「団に合った選曲を!」と合唱祭や春こん。の講評で言われることがありましたが、それは決して技術面だけのことではないように思います。
➁いまもっている知識や能力ではできない作品であること
教育機会として考えたとき、僕は現メンバーが今はもっていない力(知識や能力)だけれども、約5か月かければきっとできるようになるような力を想定して、「できなかったことが、春こん。を通してできるようになる」ということを重視しました。例えば、今回は、いくつかのことを念頭に置きました。ぱっと思いつく例を挙げると、「変拍子は苦手だったけど、少しは慣れた」「無調は音がとれなかったけど、少し感覚が分かった」「自分のパートが1人だとしても自信をもって歌えるようになった」「発声のメカニズムを理解して歌ってみると、いつもとは違う声を出せるようになった」「楽譜を見たときにできなさそうな不安があったけど、いまは似たような楽譜を見てもそこまで不安を感じなくなった」「これだけ難しい曲をあきらめずに演奏できたんだから、もうほとんどの合唱作品は怖くなくなった!」…というような変化をしてほしいな、というものです。
すでにもっている能力で十分に取り組める作品の場合は、教育としての価値に限定して考えれば、そこまで選曲の優先度は高くないように思います。これは、「そもそも教育とは何か」というとても大きなテーマとも関わりますが、自然発達の過程でできるようになることは、特別な教育介入をせずとも自然に獲得されるため、あまり介入の必要性は無いように思います。しかし、自然には気づけなかったり、身につかないようなこと、もしくはいつかは気づくかもしれないけど時間がかかる可能性が高いもの(例えば慣性の法則や三角形の面積を求める公式など)は、自然に気づくのを待たずに先人の研究成果を先に教えることで効率的に他のことを学ぶことが可能になります。そうして、いろんなことを知り、できるようになるよう介入していくことが、教育を受ける側にとっては将来の選択の幅を広げたり、自分らしい生き方を支援していくことにつながるのではないかと思います。(逆に言えば、何か新しいことを知ったり、できるようになるわけではない介入は教育ではないとも言えます)。
約5か月間でどの程度の力がつくと予測ができるか(変化を期待できるか)、それはやはり、選曲前のメンバー一人ひとりへの十分な観察と、メンバー一人ひとりへの信頼があってこそのように思います。予測ができない場合、何が起こるかというと、メンバーの能力と作品に取り組む期間に対して、不釣り合いな高度な能力が求められる作品を選曲してしまうことや、反対に簡単すぎる作品を選曲してしまうことが考えられます。このどちらにもメンバーに対するデメリットがあります。もし作品が十分に飲み込めなかった場合は達成感が得られず、また人によってはそれを失敗体験と感じるかもしれません。反対に簡単すぎる場合は、飽きてしまう、というのがよく見られます。モチベーションを維持できないということです。このあたりは、教育実習に行かれた方は、指導案作成時や実際の授業でご経験をされているかもしれません。
➂数か月をかけて取り組むに値する内容や背景をもった作品であること
中学校における校内合唱コンクールでも、各校種におけるクラブ活動や部活動における合唱でも、この点は重要になってくると思います。音楽科の授業を考えると、年間で限られた時数の内、一定の時間を割くに値する内容や深みのある作品かどうか、クラブ活動や部活動においては、連日の練習を行ったことを生涯の中で位置づけたときに、価値のある作品であったのか(人生で出会って良かった作品なのかどうか)、ということはよく言われることに思います。
作品に取り組む中で、最初は音を取ることや、合わせをすることに必死な状態だったものが、どんどん作品に慣れていったときに、「響き」に特に美しさがある作品の場合は、丁寧に練習するほどに声を重ね合わせることの素晴らしさを感じられるかもしれません(例えばE. Whitacreの”Sleep”は響きが美しいです…!)。詩の意味が分かることで、「こう歌いたい!」が出てくる作品の場合は、詩の解釈やそれを表現につなげていくことで、解釈することや自分とは違う意見を取り入れながら演奏を一緒につくっていくことの楽しさを感じられるかもしれません。そうした、数か月をかけることでどんどん合唱することの良さが分かっていくような作品でなければ、どこかで合唱団はエネルギーを失っていくように思います。
一時期は、哲学的な詩や社会問題、日本古来の文化等をテーマとした詩をもつ合唱作品が国内で数多く生まれました。三善晃で言えば『オデコのこいつ』や「わりばしいっぽん」、南安雄の『日曜日~ひとりぼっちの祈り~』、間宮芳生の「合唱のためのコンポジション」シリーズ、鈴木憲夫の『永久ニ』といったものです。今は、詩の内容面は昔ほど多様さはなくなったように感じています。一方で、響きの美しさの面では、今の時代の方が個人的には色彩が華やかになったように思っています。三宅悠太や土田豊貴、横山潤子の作品のように、響きがかっこいい曲はどんどん生まれているように思います。(余談ながら、作品のもつ響きが変わってきた分、求められる声のポジションも変わってきましたし、作品で想定されている合唱団の規模も、楽譜をみると変わってきたなぁとも感じます。)
数か月をかけることでしか気づくことのできない合唱の良さをもっている作品かどうか、それは教育の観点からは見逃せないものでしょう。
➃聴衆とも合唱の良さを分かち合える作品であること
演奏者として忘れてはいけないのは、演奏するとき、そこには聴き手がいることです。僕が(比較的)マニアックな作品を選ぶ理由について、どこかでお話したかもしれませんが、よびごえのみなさんが歌ってくださることで、お客さんが「この曲素敵!」「こんな曲が合唱作品としてあったのか」と思ってくれたら、お客さんがもっと合唱を好きになってくれるかもしれませんし、作曲家やその作品の見直しにつながるかもしれません。
その先に楽譜が売れれば、経済活動が付いて回ることになります。副次的ではありますが、これはとても重要なことだと思っています。作曲家の方がまた新しい作品を生み出してくださるきっかけになるかもしれませんし、やはり歌ってもらえることで作品は初めて「生きる」ことになりますので、作曲家の方の活力に直接影響するでしょう。
お客さんが十分に知っている曲を聴くとき、僕の勝手な考えかもしれませんが、過去の名演と比較しながら聴いたりしていることってあるんじゃないかと思っています。それは「粗探しの聴き方」と僕は思っているのと、それは合唱の良さではなく、コンクールに偏った聴き方に思っています。「合唱本来の楽しさ」をコンクールから切り離して聴いてもらうためには、やっぱり、聴き馴染みのない、それでいて内容の深い曲がいいんじゃないかな、とは思っています。
というこの考えは、とある高校の有名合唱部の先生の話をお借りしました。「コンクールで勝てる曲」というのがある、と感じていた時代があるのですが、そのことを思っていた時、全くコンクールっぽくない曲で全国大会に進んだ学校の先生で、その時からずっと「なぜあの選曲にしたのか聞きたい!」と思っていたのが叶った時に伺った話です。
……、めちゃくちゃ長いやん!と思われるかもしれません。僕も思っています。
しかし、「選曲」(教材選択)という行為は、合唱活動の方向を直接的に決定するものであり、つまりは教育活動の方向を決定するとても重要なことだ、ということをみなさんとシェアしたいと思いました。
コロナ初年度、オンライン勉強会を開催して、「作品を通した体験探究」と題し、「教育的な視点で合唱作品を分析する」という活動を行っていました。その時の記事がよびごえ日誌に残っていますので、リンクを貼っておきます。児童合唱や混声合唱、女声合唱の、さらには社会問題を含むもの、ナンセンス詩、宗教作品、ポップスなどの様々な作品を毎回取り上げながら、グループに分かれて、ワークシートの問いをメンバーと一緒に考え、発表し、そこからさらにみんなで考えるような活動でした。ワークシートも当時のものを参考用に貼っておきます(音源と楽譜もワークシート中のリンクからアクセスできます)。
さて、ここまでで4500字という、、、やばい!!と思っています。
今回の春こん。にて実際に選んだ2曲に関する簡単な説明はYoutubeの概要欄に書きましたため、そちらをご覧ください。
いつぞやに、春こん。が終わったとき、「合唱とはなにか」ということを考えてみてください、ということをお伝えしたように思います。
定義としては、そんなに難しくないとは思います。複数名が、いくつかの声部に分かれて歌唱する音楽の表現形態の1つですが、もちろんそんなことを考えて欲しいわけではありません。…
28
February
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.11 春こん。を終えて
こんにちは、1Bの井藤です。合唱団よびごえに入団してもうすぐ一年経つことを考えると、大学生活1年目があっという間だったな、と感じます。大学に入って自分のコミュニティが以前と比べ物にならないほど広がったことで今までの自分とは違った視点で物事を考えることが多く、教育的な面・音楽的な面共にとても充実した日々を送ることができました。
さて、今日のよびごえ日誌は春こんや春こん本番までの稽古について、またこの1年間を振り返って考えたことなどを書いていこうと思います。
まずは、春こんお疲れさまでした&ありがとうございました!
今回のよびごえの活動でも、春学期の合唱祭以上にたくさんの経験を積むことができたと思っています。
実は、春こんに向けて動き出した時、私はかなり不安でした。小田さんのLINEの内容、「春こんの曲を覚悟することができた」という文面を見て、「いったいどんな難曲が選曲されたのだろう、僕は歌えるのかな…」と考えていました。
そうして小田さんセレクトを受けた『だるまさんがころんだ』と『「風の馬」より第三ヴォカリーズ』の2曲。どちらの曲も譜読みから難しく、音取り用の音源を小田さん・藤原さんに作っていただき、それを聴いて練習しても初めは全然うまくいきませんでした。さらに2曲とも歌うパートが自分1人になる箇所(『第三ヴォカリーズ』に限っては曲のほとんどの部分・・)があり、「頑張ろう!」という気持ちはあれど「あれ、これ皆と合わせできるのかな…」という不安が大きくなっていきました。1回目のよびごえ稽古では、他のパートの音は聴かずに、まずは自分の音が合わせでも正確に取れるように意識しましたが、やはりうまくいきません。しかし悩んでいるのは自分だけでなく、皆が必死になって練習している光景は自分にとって何より勇気をくれるものでした。
だんだんと練習を重ねる中で正確に音が取れるようになってくると自信が付き、他パートの音源を聴きながら歌えるようにも練習しました。しかし…いざ稽古で合わせてみると、練習の時とは雲泥の差。実際の生の音は歌いながらだととても聴きづらく合わせづらいもので、音源と人の生で聴く声がまったくの別物だということを痛感させられると同時に、毎週の稽古の重要さも身に染みました。
そして、待ちに待った(?) 初の小田さんとの対面稽古。改めて気づかされることの連続でした。特に発声では、「空気をどのように吸って・身体のどこに溜めて・どこを通って出ていくか」を意識しながら行うこと、「この高さの音は出ない、と自分自身で決めつけないこと」など、今まで自分が行ってきた発声が如何に無意識に声を出していただけだった、ということが露わとなるようなことばかりでした。いつかの稽古の振り返りで、自分は高校の先生が「本番前に10発10中ではなく100発100中になるように練習しなさい」と言われたことについて話しました。小田さんはよびごえの稽古で皆がわかりやすいように明確に言語化して、つまり理論的に、発声や歌のヒントを提示してくれました。小田さんの教え方から、「100発100中」も大きなイメージではなく、1つ1つの身体の動きやテクニックに理由と方法論を用いて技術を構築していくことで「まぐれ」を無くしていく工程、と捉えられるのではないか、と思います。
音がそろってくると、今度は歌詞や音程間の解釈に取り掛かりました。まだよびごえに入団して1年も経っていませんが、他のメンバーと意見交換をしながら時間をかけて曲の解釈を深めていく過程は、よびごえならではのとても良い活動だな、と思っています。1人ではきっと気づかなかったであろう新たな表現方法を発見したり、音楽に対する視野が広がったり、様々な視点からの歌詞解釈ができたりと、とても楽しい時間でした。この時間が無ければ、『だるまさんがころんだ』では怖く感じるイメージだった音形が温かく感じることはなかったし、『第三ヴォカリーズ』では曲の流れをはっきりと言語化することはできなかったと思います。
そして迎えた、春こん本番。今までの練習や稽古で取り組んできたことが多かったため、成果を出し切れるか、ホールでしっかり響く声で歌えるかと若干の緊張がありました。ですが、「音楽は、最後は心だから」という小田さんの言葉で、楽しく歌い切ることができました。曲の出だしの音量が違うといった点もあると思うのですが、夏に合唱祭で歌った時と同じホールだとは思えない程、第一声を出した瞬間にホールがよく響いていることがわかりました。練習でできたことが100%できた、とは言えないのが本番の怖いところですが、当日1人も欠けずに楽しんで演奏できたことは自身のとても素晴らしい思い出になりました。
4月からは大学2年生となりますが、この1年間で学んだことを活かして、自分に足りていない力を付けられる1年にしていきたいと思います。小田さんが春こんに向けたよびごえ日誌に「より良い合唱活動を実施できるようになるためには、たくさんの作品を知っておくことも大切」と書いていました。私が合唱団よびごえの一員として歌ってきた曲は今まで知らなかった曲の方が多く、知識・技術含めたくさんの経験を積むことができました。来年度からよびごえも新たなメンバーとなりますが、新1年生も一員に加わり、より多くの経験を一緒に積んでいけることを楽しみにしています。
長々と書いてしまいましたが、これで最後です。お付き合いください。
「教師はネガティブではいけない、ポジティブであれ。」少し言い切った形で書きましたが、稽古で小田さんがおっしゃった言葉です。東京学芸大学で1年学び、入学前より教壇に立つことが楽しみな反面、教師の裏側も思っていた以上に大変そうです。正直に言って、自分はポジティブではありません。理解していても、気が付くとネガティブ方向に偏っていきます。よびごえの活動含め、少なくとも大学4年になった時、このよびごえ日誌に自分がポジティブになれた、といった表現がより多く書かれていることを願っています。
ありがとうございました。
井藤一輝…
27
February
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.10
こんにちは、1Aの小林です。1年前の今頃はちょうど前期受験を終え、後期受験の不安と闘い、合否発表の日が来るのを震えながら待っていたことを想うと、改めて月日の流れの速さを感じます。あっという間ではあったけれど、この1年は自分にとって出会いと学びと音楽に恵まれた、すてきな1年でした。
さて今回は、春こんという1つの行事を終え、年度内の活動が終わった節目ということでよびごえ日誌を書いています。前回の日誌で小田さんからお譲りいただいた稽古の様子を含め、自分なりに考えたことや稽古を通して変わったことをお話しできたらと思っています。お付き合いください。
今年の春こんで僕たちが歌ったのは、『だるまさんがころんだ(詩:矢川澄子 曲:長谷部雅彦)』よりⅠと、『風の馬(曲:武満徹)』より「第三ヴォカリーズ」という2曲です。いま、本番前に見たのを最後に久しく開いていなかった楽譜を眺めながら書いています。書き込みがいっぱいです。大変に難解な2曲でした。
まずはだるまさんについて。初めて曲名を聞いたとき、知らない曲だ、YouTubeで聴いてみようと思い一番上に出てきた動画をタップしました。流れてきたのはなんと打ち込みの機械音声。衝撃を受けました。一つ下にあった動画からはひとの声が聴こえてきたので安心しましたが、流れていくだるまさんの応酬に?が止まりません。かと思えばそれは参考視聴用の音源だったので1分たらずで終わってしまいました。YouTubeの世界に存在するこの曲の音源は、僕が観測できた限りこの2つだけ。これはやばそうだぞ、と、だるまさんに対する第一印象は不安でいっぱいでした。
風の馬について、こちらは演奏の参考音源にこそ(だるまさんに比べれば)困りませんでしたが、曲の難解さはだるまさんと同等かそれ以上だったように思います。日本語として聴きとれる歌詞がないこと、不安を誘うような和音の連続、そして何より突然やってくる終結部、最初に聴き終えたときはこの曲を自分が歌うんだということを忘れてしまうような呆然とした感覚になりました。
2曲に共通して言えることは、全然好きになれそうになかったということです。
譜読みしてみても、合ってるんだか合ってないんだかさっぱりわからないまま稽古は始まりました。みんなといっしょに歌ったらわかるのかな?と思ったりしたこともありましたが、そんなことないどころかむしろ逆でした。こんな難しい曲に挑んでいるのに、先輩方は「よびごえっぽい」「こういうのにもきっとすぐ慣れちゃうよ」「私たちもそんな風にわけわかんない時期があったなァ」とニコニコしていて、マジかよと思いながらついていくので必死でした。
後期の活動に入って初めて体験する出来事がありました。対面稽古です。オフラインの小田さんは、勝手に持っていたイメージよりずっと背が高いひとでした。対面稽古を通じて何より強く感じられたことは、自分の声が持っている可能性です。うまく文章にはできないけれど、声域的な意味でも声質的な意味でも、自分はもっと幅を広げられる、それを表現に活かす余地が無限にあるのだという前向きな気持ちになりました。これはよびごえの活動についてだけでなく、ソロで歌うときにも活きています。技術と表現の「分けて考えるべき部分」と「双方向に繋げて考えるべき部分」という二面性、音楽をやっていくうえで不断に挑み続けなければならないこの課題に対するヒントやアイデアをたくさん吸収できた時間でした。
年が明けてから、一気に稽古の空気が変わったように自分は感じています。初めのころは「訳が分からない」「音が取れている気がしない」「あってるはずの和音が気持ち悪い」とプラスな考えが浮かぶ兆しがほとんどなかったのに、年明けの稽古からは歌っていて楽しいと思える音やフレーズが1つ、2つと増えていきました。終盤の稽古になって取り入れられた、パートバラバラで2グループに分かれて歌う練習は特に楽しかったです。普段近くで歌うことがないひとたちの声が近くに聴こえて、自分の声部の役回りを強く感じられました。最初は頭がいっぱいで苦しかった通し稽古も、回を重ねるごとに面白くなってきて、ここ決まった!うれしい!!と思えることがどんどん増えていきました。今考えてもとても不思議です。最初は全然好きじゃないとか思っていたのに。
きっとたくさん考えたことを共有して、たくさん気づいて、たくさん歌った稽古の蓄積と、それから小田さんの魔法と計算のおかげだったのだと思います。
本番は本当に楽しく歌えました。ホールが鳴っているのが聴こえて、拍手のあと観客の「すごい、、」というつぶやきも聞こえて、表現や技術的にもっとできたことはもちろんあったとは思いますが、充足感の得られる本番になりました。よびごえの一員として出場出来てよかったと、胸を張って言えます。
4月からはまた新たな体制で、新しいメンバーで、新しいよびごえが始まります。この1年で先輩方から得られたようなことを周りに与えられるように、そして自分だからこそ与えられることを周りに与えられるように、来年の春こんを終えてまたこの日誌を読み返している自分が今よりすてきな表現者になっているように、新しい1年も大切に豊かに過ごしていきたいです。
今頃ちょうど前期受験を終え、後期受験の不安と闘い、合否発表の日が来るのを震えながら待っているであろう次の1年生が、1人でも多く合唱団よびごえに興味を持ち、やがてチームになって、「私たちもそんな風にわけわかんない時期があったなァ」とニコニコ言う側になる日が来ることを願って、今回の日誌を終わります。
ありがとうございました。
小林翔人…
27
February
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.9 はるこんを終えて
今回のテーマは、はるこんを通して合唱について学んだことですので、そのテーマに沿って書いていこうと思います。さて、音楽には、二つの側面があると私は考えています。一つは純粋な遊びとしての側面。これはそのままの意味合いで、個人が自発的に、自身の心を満足させるために行う状態です。(遊びにも様々な定義がありますが、ここでは“子どもがするもの”や“片手間でするもの”という意味ではなく、行為自体が目的であるものをさします。大和言葉で管弦は“あそぶ”ものであって、英語では楽器がplayするものであることは、音楽のそういった側面を反映しているようにも思います。)もう一つは、人との結びつき、すなわちコミュニケーションや、社会を形成する側面です。こちらは、表現あるいは文化とされる音楽を主に指し、人と共有することをゴールとしています。聴き手、共演者、援助者や教育者、あるいは村や団体などの共同体、故人からのつながりなど、様々な結びつきを生んだり、強めたりするものです。合唱には一般的に、後者の側面を強く持っていると感じます。すなわち、“共有”を重視する側面です。共有物には幅広く様々なものがありますが、その中でも重要になってくるのは曲ではないかと思います。小田さんと、合唱の選曲についてお話ししたことを思い出し、選曲について自分なりに考察したことを述べさせていただきます。
教育者として選曲をするとき、そこにはどのような意味合いがあるのでしょうか。先日見学したある小学校の授業で、選曲について興味深い話がありました。曲を子ども自身に選ばせたとき、商業的に成功しているものが多い、というものです。商業的に成功しているから、自然に耳に入る。多数の人が良いと感じたのは事実かもしれませんが、その成功にかかわっているのは純粋に曲のよさや好感度だけではないでしょう。そうした曲を子ども自らが選んだ時、それは自発性といえるのか、という議論でした。このことは、人が社会すなわち他の人の影響から逃れることができないということを示していると思います。自発性すらも、何らかの人の影響があってこそ、出てくるものであるのかもしれません。そう考えた時、子ども自身に選択をゆだねることも一つの方法ですが、様々な選択肢があることを示し、新しい世界を見せることも教師の重要な役割の一つではないかと思いました。教師が提示した曲によって、子どもは自分の中に新たな文化を内在化させ、そしてそこから外界の新たな文化とつながっていくこともあるでしょう。
今回よびごえで歌った二曲にも、様々な要素が含まれています。二曲に共通する要素として小田さんが述べたのは、「願い」や「祈り」でした。願いや祈り、欲求というものは、生きる根本に深くかかわっているものである気がします。一人ひとり、そこから考えたことは異なったと思いますが、このテーマと選曲は私には、将来を考える時期も重なり、生きる意味を考える時間を与えてくれたと思います。皆さんにとっては、この選曲にはどのような意味合いがあったでしょうか。
さて、今回は合唱について学んだこととして選曲というテーマを取り上げ、長々書いてしまいましたが、頭を使った話はおしまいにして、最後に少しだけ気持ちを書かせて下さい。
一年前、一時期は本気でやめることを考えていたよびごえでしたが、一年終わってみるとここまで皆さんと時間を共にできて幸せだったな、と思います。執行代として大したことはできませんでしたが、よびごえを通じて、色々な新しい出会いもありました。卒団された先輩方から、今でも温かい言葉をいただくこともあります。前に、メンバーからなぜ専攻に声楽を選んだのかと聞かれたとき、理由がぱっと思いつかなかったのですが、私が歌が好きな理由は、音楽を通して人とかかわり、つながる時間が好きだったからだったなぁ、とふと思いました。よびごえもたった週に一回の稽古ですが、そうした色々な人との大切な場所の一つになっているし、これからも大切にしていきたいなと思います。そして、これからも合唱を通じて、大切な人や場所を増やしていきたいです。
大変長くなりました。半年分を一気に詰め込んだと思い、お許しください。ここまでお読みくださり、ありがとうございます。 一柳優里愛…
17
August
2023
2023
【2023】よびごえ日誌 vol.5 合唱祭を終えて
今年度から合唱団よひごえに入団しました、B類音楽1年の室伏萌衣です。 これからよろしくお願い致します。初めてのよびごえ日誌では入団してから合唱祭を通しての感想、それ以降で感じたことも含めて自分の考えを書かせていただきます。 (合唱祭以外のことも含めますが、未来の自分への日記、との事だったのでご容赦ください)少しわたし自身のことをお話ししますと、よびごえとの出会いは高2の冬、志望校を決めたあたりだったと思います。大学でも合唱を続けたかったので、大学の合唱団を調べていた時によびごえの存在を知り、演奏を聴いたり、日誌でみなさんの活動や考えを知ったりしました。高校から始めた合唱の恩師から、頭を使って音楽をすることを叩き込まれていたので、「ここだったら自分のやりたい合唱、考え方をより身につけることができる!」と確信しました。それから、よびごえをモチベーションにしつつ受験を乗り越え入団に至りました。
入団した今、上記のことをとても感じています。 小田さんの指導、そしてよびごえのみなさんとの活動は自分の中でとても大きな存在です。
合唱祭では、三善晃「かめ」と木下牧子「さびしいカシの木」を扱いました。特に三善晃の曲は今回が初めてで、苦手意識を持っていた反面、ようやく触れることができるワクワク感でいっぱいでした。個人的に和音をはめながら歌うという概念があまりなかったので、自分のパートと8・5・4度の音程の部分に印をつけたことや、3度の音の場合はそこまで音量出さなくてよいということが大変勉強になりました。(恥ずかしながら3度は長調短調決める音だから大きい方がよいと勝手に思っていました…)
よびごえで特に感じるのは、曲に対する想像力がみなさん流石…ということです。毎回みなさんの意見を聞き感動していました。 よりよい音楽をつくるには想像力がとても大切だなと最近感じます。(型にはまった音楽はぬるいというか、、小田さんが以前おっしゃっていた、いつでも新鮮な歌を歌わなければならない、ということにも通ずると思います)このようなことができる合唱団は限られていると思うので本当に楽しかったです。これからも色々な意見を聞くのが楽しみです!
本番はそこまで緊張することなく音楽を感じながら歌うことが出来ました。しかし、ホールが思ったよりも響き、どうしても男声側の声がより遅れて聴こえてしまったので戸惑いが生まれたのが心残りです。自分のテンポを保つ事の大切さを痛感しました。また、講評の先生の言葉の中にもあった、2つの曲の「さびしさ」という”共通点”がわたしの中で薄れていたのも反省です。それぞれの曲のメッセージ性の情報で自分の頭は溢れてしまっていました。この2曲を一緒に歌う意味までもっと考えるべきだったと感じます。これからに活かしていきます。
課題はありますが、合唱祭を通してそれぞれの合唱団の色を体感し「合唱っていいなぁ」と再認識する1日となりました。みなさんと同じ時間を共有することができてよかったです。
話が変わりますが、母校の部活指導に行ったとき、印象に残ったことがあったのでお話しします。
アドバイスの中で「息のスピードを速めてみよう」と伝えたときに一部の生徒に意味が伝わらず困らせてしまいました。どうしても、合唱に親しい人だとアドバイスを伝えたときに、体をどんな風に動かせばいいか感覚でわかってしまう、曲にどんな印象を与えるか伝わってしまうものです。合唱に触れたばかりの人にも分かりやすい言葉・指導ってなんだろう、と考えさせられる場面でした。 言葉の拙さの改善と、言葉以外でのアプローチ(指揮で導く等…現時点ではまだ夢のまた夢ですが)も行えるようにしていきたいと感じました。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。これからよびごえでたくさん学ばせていただきます!(そしてもっと上手く自分の考えをまとめられるように4年間言語化頑張ります!) 室伏萌衣…
03
August
2023
2023
【2023】よびごえ日誌 vol.4 合唱祭を終えて
はじめまして!今年度から合唱団よびごえに入団致しました、A類音楽1年の小林翔人と申します。合唱祭という初めての本番を終え、今回初めてよびごえ日誌を書かせていただくことになりました。拙い文章になってしまうと思いますが、長い文章にはならないようにしますので最後までお付き合い頂けると嬉しいです。筆者がよびごえの活動に初めて参加したのは1回目の新歓稽古の日でした。新一年生で参加していたのは僕一人でしたが、僕が今こうして団員になっているのはその日の活動でよびごえという合唱団に強く惹かれたからにほかなりません。よびごえの先輩方は皆さん本当に優しくて、真摯に合唱に向き合っていて、僕もこんな風になっていきたいと素直に思いました。そしていつもよびごえの合唱を一緒に創ってくださる小田さんとの出会いも、よびごえに入る大きなきっかけになりました(この文章の提出先が誰あろう小田さんなので、最初に読まれることになることを思うと少し恥ずかしいような気もしますが)。よびごえの稽古ならではの小田さんの指導は、僕の合唱観をより豊かにしてくださっています。今改めて、あの日新歓稽古に飛び入り参加した自分を褒めてあげたいです。
さて、冒頭でも少し触れましたが、合唱団よびごえは7月17日に 第78回 東京都合唱祭 に出演しました。僕にとってはよびごえとして参加する初めての本番でした。僕は中・高と吹奏楽部に所属していたので、誰かの前で合唱の発表をした経験といえば学校単位で行われる合唱コンクールくらいしかありません。緊張というよりは、楽しみな気持ちで臨みました。
テノールとして合唱を創る一員となる上で、本番までの稽古で様々なことを考え、試行錯誤を繰り返しました。そんな中で、僕が特に強く意識するようにしたことが2つあります。
1つ目は「念ずれば通ず、は合唱では通じない」ということです。これは新歓稽古の時に小田さんがおっしゃっていた言葉でした。つまり「感情任せで歌うのではなく、楽曲で表現したい情景や感情をどんな技術を使って観客に届けるかを考えて歌わないと、歌を通して伝えたいことも伝わらない」ということですが、これは本番までの稽古を通してよびごえが追求してきた課題の1つです。「かめ」であれば発音やパート間の音量バランス、小学生の男の子が詩に込めた想いをどう歌に乗せるかを考えました。「さびしいカシの木」であれば1番と2番の歌い方の変化、その変化を踏まえた3番の歌い方など、「時間経過」をキーポイントに合唱を創っていきました。
2つ目は「合唱の中での自分の歌のバランスを考える」ことです。非常に個人的な話にはなってしまうのですが、僕は今回テノールパートを1人で担当させていただきました。本当にありがたい機会です。他のパートが複数人いる中で自分の歌がどう聴こえているのか、大きく鳴りすぎていないか、聴こえてほしいところは聴こえているか、練習後に録音を聴いてバランスを確認しました。合唱学習のまさに真っ只中にいる僕にとって、本当に貴重な経験でした。
本番、よびごえの合唱がどんな風にお客様に聴こえていたか知ることは今の僕たちにはできません(それが音楽の面白いところであると同時に恐ろしいところでもあると思います)が、少しでも伝えたかったことが伝わる合唱になっていたらいいなと思います。
この合唱祭が終わった後感じたことは「やっぱり合唱って楽しい!!」でした。稽古を重ねてきたよびごえの合唱を多くのお客様に聴いていただけたことはもちろん、他団体の素晴らしい合唱をたくさん聴けたという点でも楽しい時間でした。よびごえの一団員として活動していくこれからの自分にとって、今回合唱祭に出演したことが大切な経験になったのは間違いありません。よびごえの皆さん、小田さん、合唱祭を運営してくださった皆様、そして聴いてくださったお客様に、改めて感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。
「長い文章にはならないようにしますので」などと筆者は書いていましたが、もうここまでで1600字を超える文章になってしまいました。初めてのよびごえ日誌なのでどうかご容赦ください。予告通り拙い文章だったと思いますが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。
これからもよびごえの一員として精一杯頑張ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 小林翔人…
03
August
2023
2023
【2023】よびごえ日誌 vol.3 合唱祭を終えて
はじめまして!1年B類音楽の井藤一輝です。今年度から合唱団よびごえに入団しました!精一杯活動に取り組んでいくので、どうぞよろしくお願いします!今回は初めての日誌となるので、よびごえの活動に対する自分の思いや、入団して初となる合唱祭の感想などを書いていこうと思います。
さっそくですが、私がよびごえに入団した経緯から話そうと思います。私が通っていた高校は合唱コンクールがなく、またコロナの影響もあったことから、私は高校で合唱を一度も経験しませんでした。だからこそ、大学では合唱もやりたい!と思っていたので、同じ音楽コースの子によびごえの新歓稽古に誘われた時はすぐに参加を決めました。
新歓稽古では相澤直人先生の「ぜんぶ」を歌い、特に「詩の繰り返しをどのように表現を変えて歌うか」について考えました。話し合いの際、私は主に曲の元となっている詩から意見を述べました。「ぜんぶここにある」の言葉だけが何度も歌詞に出てきていて、繰り返されるたびに強い思いが加わっているように感じました。他にも、一度目は他者に、繰り返しは自分自身に言っているという意見や広さ・深みが違っているという感じ方など、多くの異なるイメージを知ることができました。今まで詩から曲を考えることがなかったので、とても楽しい経験となり、歌えば歌うほど、考えれば考えるほどいろいろな思いが溢れてきました。
新歓稽古という短い時間の中でも学ぶことが多く、合唱そのものだけでなく自分が教える立場になった時に活かせる経験を多く積める、何よりよびごえの活動が楽しい!と思ったことから入団を即決させていただきました。(大野さんへの入団の連絡は少し遅くなりましたが…)
入団して間もなくよびごえ新体制の初舞台となる合唱祭に向けた稽古が始まり、「かめ」と「さびしいカシの木」を歌うことになりました。私はどちらも初めて聴く曲でした。2曲とも、『子ども観』をどう表現して歌うか、がとても大事になり、毎週の稽古でとても悩まされる議題となっていたと思っています。「かめ」はアカペラの曲なので各パート入りを合わせるタイミングがとても難しいなと感じていました。稽古が進んでいくに連れて詩の解釈も行い、どの部分をどう歌いたいかを話し合った後に初めて息がピッタリと合う合唱ができたと思います。自分はこう歌いたい、ということを言語化することで初めて、お互いにどの表現が歌詞に合っているかを考えられると改めて気付かされました。また、「かめ」の稽古で私がとても驚いたことが、初めて全パート一緒に歌う時、小田さんが「自分のパートを正確に、自己中心的に歌って」と言ったことです。聞いた時は、自分のパートだけ真剣に歌っていても他パートを聴けなければきれいな響きが作れないのでは、と混乱しました。けれど考えてみれば、いきなり他パートの音と一緒に歌うと自分の音やリズムがズレてしまう、といった問題は中学の合唱練習でも感じていたことで、「他パートが入っても、まずは自分のパートに集中して歌うことを意識する」という小田さんの言葉にとても納得がいきました。
「さびしいカシの木」は、1番2番3番(特に1・2番)をどのような変化をつけるかにたくさん話し合いの時間をとりました。また、日本語特有の鼻濁音や子音、特に重要な言葉の最初に多いkの子音を大事に発音することも注意ポイントとして学びました。自分がこの曲でこだわってみた場所は、3番のBassの入りと、その後の全パート共に入る「いまではとてもとしをとり」のところです。Bassの入りはとても暖かく声を出すことを意識しました。始めはうまく音が続きませんでしたが、小田さんや同じパートのアドバイス「胸を開放して、息を広げる感じ」を参考に暖かい声の出し方を考え、表現できたと思います。その後の各パートが同じ歌詞に合流するところは、1小節前のBassの音の流れをたっぷりと歌いたかったため、稽古で指摘をさせていただきました。少し自己満かなぁとも思いましたが、自分はとてもなめらかに歌いやすくなり、反対の声もなかったので同じような意図を持ってくれたのかな、と思ってます(笑)。
そして迎えた、よびごえとしての初の舞台であり、今までの稽古で学んだことに加えて、何を自分たちは届けたいかを一人ひとりが考えて臨んだ合唱祭!
私が合唱祭で感じたことはたくさんありましたが、大きくまとめれば、「やはり音楽って素晴らしい!!」ということです。多くの合唱団が各々の曲に向き合い、表現して合唱を作っている。各合唱団の歌からそれがひしひしと伝わってきて、とても幸せな時間が過ごせました♪
私自身も、ステージでの合唱はとても気持ちよく歌えて、歌い終えた時に充足感を感じました。よびごえが2曲に込めた思いが、聴いてくれた人々に伝えられたのではないかと思っています。しかしまだよびごえは新体制になったばかり、講評の内容や自分で練習通りに行かなかったことも含めて、さらに良い合唱が作れるようにこれからも精進していきたいと思います!
🎵最後に一言🎶
小田さんが最後の稽古でおっしゃった「合唱の意味」を、これからの稽古で考えていきたいと思います。私が小田さんの言葉を聞いた時にパッと出たのは、「それぞれの感じ方を共有し、1つの曲を表現していくことの大切さ、楽しさを伝える」といった意見ですが、おそらく小田さんの問いはもっと深いもの、またはもっと単純なものなんじゃないのかな〜と勝手ながら思ってます。自分が教える側に立ち、指導する際に大切なことも、これからの活動で吸収していけたらと思います!
気づいたらこんなにも長くなってしまっていたので、この辺で書き終えたいと思います。
改めてみなさん、合唱祭お疲れ様でした!また共に頑張って行きましょう! 井藤一輝…
10
March
2023
2023
【2022】よびごえ日誌 メッセージ(堀切)
こんにちは!4Aの堀切です。今回のよびごえ日誌は、書きたいことは沢山あるのになかなか書き進めることができませんでした。それは、書きたいことを文面にした時に、言葉が気持ちから離れていってしまうような感覚が強かったからです。書くために書いているような感覚、という感じでしょうか。普段の振り返りでは、直接話しているという即興性とライブ感で素直なことが話せますが、文章にするというのはそれ特有の難しさがあると感じました。ただ、今回の本番とこの4年間の振り返りを記録として残しておきたいので、できるだけ飾らず素直に書けたら良いなと思います。
まずは、今回歌った2曲について書きたいと思います。
今回歌った「Cikala le Pong Pong」と「Soleram」は共にインドネシアの曲ということで、そのアプローチがとても難しかったです。今、私自身やよびごえ全体としての曲に対するアプローチを振り返ると、共通性と固有性という視点が重要だったのではないかと感じます。私は、「Cikala le Pong Pong」を理解するにあたり、日本や自分との共通性に先に注目し、それを基盤として固有性に迫っていったと思っています。少し具体的に書くと、まず日本の結婚式のしきたりや様式と曲とを比べ、相手の家を立てたり形式を尊重したりして、思いとは裏腹なことを言うという共通性があると思いました。その後、では本当の思いとは何なのか、それはどうやって子どもや聴いている人に伝えているのかという共通性を基盤とした視点ができ、それがシンプルなリズムやフレーズを繰り返して没入感を生み出すというインドネシアの音楽の特徴や、踊りも含めたこの曲がもつ民族的なエネルギーの高さといった固有性の理解・体感につながりました。一方「Soleram」の場合は、インドネシアでポピュラーな子ども向けの歌であるということや、インドネシアの国民性と言われている奥ゆかしさが反映された歌詞であるという知識が先にありました。そしてその固有性から曲の背景を捉えた上で、子どもを想う親の気持ちという国を越えた共通性が、曲の世界観や歌っている時の自分の支えになっていたと感じます。私の中でも、曲によってアプローチが違いますし、同じ稽古をしている他のよびごえの方々も、人によって様々なアプローチをしていたのだと思います。どれが正しいということは無く、自分が一番腑に落ちる形で曲に対する理解を深められることが大切だったのだと思います。自分達とは異なる文化や音楽とどう接したら良いのか、その過程を実際に体験できたことはとても勉強になりました。
次に、よびごえの活動全体について書きたいと思います。
最初はよびごえの本番までの過程をできるだけ詳しく整理しておこうかとも思ったのですが、何だか違う気がしたので止めました。ここでは、よびごえの活動の自分なりの解釈について書こうと思います。
よびごえでやっていることを私なりに一言で表すと、「表現の主体者として、根拠をもって音楽をデザインすること」だと思っています。これが成り立つためには様々な要素が関係していると思いますが、団員個々の解釈や音楽表現が尊重されること、曲の世界観を理解する機会が保障されていること、この2つが特に重要な要素だと思っています。そして、この重要な要素は、解釈や音楽表現を無理に統一しないこと、曲の世界観について歌詞や背景、音楽から理解した上で、それを音楽表現に還元すること等の、よびごえで大切にしている考え方に支えられていて、そのような考え方がよびごえらしい学びを形づくっているのだと私は解釈しています。また、よびごえにおける合唱に対するアプローチが、そのまま団員同士の関係性の基盤になっていることが、よびごえという合唱集団の人間関係の特徴だと私は思っています。個人を尊重し主体的に行動するというのは集団の理念としてよくあるものだと思いますが、それが指導法と照らしても齟齬が無いというのは珍しいことなのではないかと思います。そして、このような活動をしているよびごえだからこそ、自分らしく学ぶことが誰かの学びや気付きになっているということに、卒業のタイミングで気付かされました。私にとってよびごえでの学びは、色々な要素や視点が混ざりあった多角的で開かれたものだったので、これからも自分の中で反芻しながら学びを深めていきたいと思っています。
さらに、私自身の大学4年間について書きたいと思います。
大学4年間を振り返ると、大切にしたものは大切になるということを改めて実感します。例えば、何かやってみたいことや興味があることに思い切って挑戦したことで、それが自分にとってすごく重要なものになったり、自分が変化するきっかけになったりしたことがありました。また、自分が大切にしたいと思っていたことが、色々な原因で大切にしきれなくなりそうだったとき、そのままそれを手放してしまったことも、ここだけは譲れないと大切にしきったことで、自分の揺らがない根幹になったと感じたこともありました。さらに、最初はあまり大切に思えなかったことでも取り組んでいくうちに、気付いたら実は大切なものになっていたということもありました。何かと接するときそこには必ず相手や対象が存在して、自分がした行動の影響を自分も相手も必ず受けるということを忘れないようにしたいと思いました。大学で学んだことを大切にしながら、何かを大切にできる勇気と柔軟性をもって過ごしていきたいと思います。
最後に、いつかこの日誌を読みにくるであろう自分に、せっかくのHPの位置づけを生かしてメッセージを残そうと思います。
この日誌を読みにきたということは、おおよそよびごえでの合唱体験をどうにか自分でも実践しようとして、行き詰まってしまったといったところでしょうか。もしよびごえの詳しい練習の様子が知りたいのであれば、他の日誌や当時の楽譜・録音を振り返れば良いと思いますが、そこまで不安になり過ぎる必要はないと思います。よびごえでせっかく学んだことを取りこぼしてしまったと思っているなら、たった4年で全てが理解できるほど合唱は単純ではないし、自分が本当に大切にしたいと思っている理念はちゃんと自分の中に残っていると思うので、安心してほしいです。むしろ、変わり続ける自分の教育観の中で、よびごえで学んだことを捉え直すことこそが、よびごえでの学びを生かすことにつながるのではないかと思います。教育観を確かに、柔軟にもちながら、目の前の子どもをよく見て、ともに学びを作っていってください。
本当に最後になりますが、よびごえで関わってくださった全ての皆さん、本当にありがとうございました。よびごえにいられて本当に良かったです!
堀切彩愛…
21
February
2023
2023
【2022】よびごえ日誌 メッセージ(原田)
こんにちは、3A原田です。春こん。ありがとうございました!
今年も本当にあっという間で、でも私なりにたくさん学んだ稽古期間でした。せっかくなので、去年の私と同じ3つのテーマで振り返ってみようと思います。この間書いたばかりなのに、また長くてすみません……
◎歌唱技術について
いつかの稽古の帰り、“発声はファンタジーじゃない”と小田さんに言われたのが印象に残っています。また、稽古では声量で感動させる、という話があって、アルト1全体で求められていたほど声量アップできたのかは分かりませんが、4ヶ月で少しは気持ちよくクレッシェンドできるようになった気がしています。指導者として「もっと元気に!ffで!」という指示をするのは簡単ですが、体をどう使えば大きい声が出せるのか、どんな練習や環境構成が効果的か、まで考えなければいけないな、と実感しましたし、そうして学んだ技術が増えれば増えるほど、曲での表現の幅が増えるのだと思いました。
余談ですが、私は発声中の小田さんの「筋肉と会話して」「ブレスから勝負は始まっている」といったパワーフレーズが好きで、この4ヶ月でも楽しい指導言がたくさんメモできて嬉しいです。「OK?」と優しく聞いてくださるのも好きなので、今度の実習で使ってみたいなと思います。
◎曲について
今年取り組んだ2曲は、インドネシア スマトラ島北部のパクパク族民謡と、リアウ諸島の民謡でした。稽古では、詩を一語ずつ訳して、インドネシアの文化にも触れながら、詩の解釈をしていきました。子どもは何歳でどこにいるのか、どんな抑揚をつけたら民謡らしくなるか、この部分にはどんな気持ちが隠れているのか、それはどんな技術で表現できるのか、など、没入感をもって歌うための解釈をたくさんできたように感じています。没入感といえば、先日声楽のレッスン中、突然ゾーンに入ったような、曲の世界観に閉じ込められたような気分になったことがあって、私、成長できているかもしれない……!と嬉しくなりました。表現するには、正解を察することではなくて、自分なりの解釈に入り込むことが必要なのだと最近ようやくわかってきた気がします。教育現場で扱う外国の音楽も、子どもなりの解釈ができるよう文化への理解を深めることで、よくわからないまま綺麗に演奏する、ということはなくなるのかもしれないと思いました。
また、今回は詩と音楽だけではなく、踊りの稽古もありました。視覚的な一体感は強烈でしたし、合わせて作った衣装もインパクトがあって、本番も変なことしてる感じが面白かったです。振りが付いているChikala le Pong Pongでは、詩から踊り方のイメージを膨らませたり、それぞれの動きに込められた意味を感じることで音楽の方向性が決まったりと、それぞれが影響し合ってを曲を作っていることが実感できました。
そして、この2曲は、民謡として誰かの人生の中で実際に歌われている曲という特徴もあります。合唱団ではなくても歌う人がいて、コンクールのステージでなくても歌われるタイミングと場所がある曲。それゆえの難しさがあったとは思うのですが、最後の稽古で“この曲は春こんが終わっても、明日も明後日も歌われる曲だよ”という話があったとき、なぜか少し嬉しくなりました。それは、ステージの本番のために準備する曲があるのと同じように、大切な人のために歌う曲、自分のために歌う曲があって、私の中でそれはどれも同じように大切だから、かもしれません。個人的な意見ですが、私は、“歌いたい”という衝動は本来、ステージ上よりも寧ろ日常の、どうしようもなく悲しいときや嬉しくてたまらないときの方が湧いてくるのではないか、と思っています。そうした衝動を、表現に繋げられたら、言われた通り歌うだけの合唱にはならないのかなあ、と考えたりもしました。音楽科にいるからこそ、日常の中の音楽、生活の中の歌の価値、意味にも気持ちが向けられたらいいな、と思います。
◎合唱について
大学に入ってから、たくさんの人のおかげで歌を歌うことが本当に楽しくて幸せだなあと思っています。ですが、それと同じくらい、合唱をすることにたくさん悩んできた気がします。私は歌うと元気になるはずなのに、合唱をするとなんで疲れるんだろう?とか、やっぱりコンクールは苦手だなあ……とか。「合唱が大好き!」と嬉しそうに振り返りをしているよびごえメンバーを見て羨ましく思ったり、声楽ではできることが合唱だとうまくいかなくて落ち込んだりもしました。それでも、合唱は私にとって楽しいものですし、そう思えているのはよびごえのおかげだなと思っています。素敵な環境にいられて嬉しいです。
去年の日誌で「関係性」の話をしたのですが、合唱団の中の関係性というのは、常に変化するものです。去年の私は先輩方に追いつこうと必死で歌っていましたが、今年は逆にパート練を進める立場になって、自分の歌唱技術を頼りにしなければならない場面がたくさんありました。そこには責任感のようなものが生まれていたのだと思います。このような変化が至る所で起こっているのが集団というもので、教育現場での合唱は、そういった関係性の変化が大きく演奏に影響するのではないかと思います。指導者との関係性、曲との関係性もありますね。合唱指導をするということは、広い視野とバランス感覚をもって、そういった変化にも敏感にならないといけません。声を合わせて、と簡単に言うけれど、楽器で音色を合わせるよりも声を合わせるのは感情を消費する作業だよなあと思ったり。これまで素直に歌えていたのに指導者の一言で歌いづらさを感じるということがあれば、逆に歌いやすくなることもあるなあと思ったり。賞がつくと頑張れる人がいる反面、音楽に…賞…?と心がざわつく人もいるかもしれません。歌うことを好きでいてほしい、と願うほど、合唱指導は難しいなあと感じます。
コンクールについては、夏の勉強会で“子どもの学びを支える合唱作品”の重要性を感じるとともに、歌い手が充実感をもてるコンクールへの向かい方について、春こん稽古からもヒントを得られた気がして嬉しいです。価値ある合唱指導、正解があるわけではないですが、歌い手側の思考を促す指導は大切にしたいと思います。絶対的な理想を押し付けられるのではなく、子どもたちが自由に考えてそれを主体的に歌にできる……コンクールに出たことで、その過程を経験できるような指導をしたいです。先生にお守りで貰った金のキーホルダーを見ながら、金賞じゃないとだめなのか…と不思議がっていた私のような小学生も満足する指導ができたら、当時の私も喜んでくれる気がします(笑)。
それにしても、周りのブレスを感じて、自分の声と同じパートの人の声を、自分とは違う音との重なりを感じながら、解釈の受け渡しをし、指揮者の要求にも応えつつ、最終的に伝えるものは空間全体にある音楽で……と考えると、様々な要因を含んだ、複雑で繊細なことをしているんですね。でも、いや、だからこそ、連帯感、親近感、一体感……でしょうか?一緒に歌うことでしか味わえない感動や魅力が合唱にはあって、私はそれが好きなのかな、と思います。
そして、よびごえでの時間はいつも、これまでの人生で一番真剣に、そしてマイペースに合唱と向き合える時間だと思います。こんな書き方をすると、いつものように各方面から考えすぎだの思いつめすぎだのと声をかけられそうですが、寧ろ逆で、こういう時間が欲しかったので嬉しいです。私は小学生にどんな気持ちで歌を歌ってほしいのか、合唱からどんなことを学んでほしいのか、それにはどんな手立てが必要なのか。先生になる前にもう少し深くまで考えてみたいです。
改めて、
4年生の先輩方、卒団おめでとうございます。関われた期間は1年ほどですが、先輩と一緒に歌えて嬉しかったです。ありがとうございました!
そんな偉大な4年生さんと、優しい同期、頼もしい2年生、かわいい1年生、こんな濃いメンバーで毎週一緒に歌える場所があるってすごいことですよね。いつもありがとうございます。幸せです。
小田さん、面白くて新鮮で楽しい稽古をありがとうございました。よびごえからもらったたくさんの学びを、自分なりに広げていけるように頑張ります。
春こん。本当にお疲れさまでした!
原田綾乃…
01
March
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(松本)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。25
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(一柳)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。15
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(堀切)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。15
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(原田)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(佐藤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(滝澤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(大瀧)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(小田)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(伊藤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(小金澤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 春こん編 12/23の日誌と、本番前日に思うこと
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。23
August
2021
2021
【2021】よびごえ日誌 合唱祭の振り返り
とっても時間が経ちましたが、よびごえメンバーより、合唱祭の演奏に関する感想と、前期の練習の運営について振り返りが欲しいとのことだったので、記録としてよびごえ日誌に綴ることとします。まず、何度も言いますが、こうした状況下において、新入生と共に、みなさん自身の力で舞台に立ち、拍手をもらえたことはとても素晴らしいことだと感じています。運営に注力してくれた2,3年生にはとても感謝しています。本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。
【演奏について】
合唱における演奏の良し悪しは、音程や和音、発音、複数の声部による有機的な音楽構成(解釈や空間づくり)といった「技術的な視点」だけでなく、パートや団としての声のまとまり、発声、選曲といった「個性が影響する視点」、さらに抽象化すると、気迫といった「雰囲気のようなもの」まで、いくつかの層が複雑に絡み合って決まってくるように思います。
それらを見渡したうえでも、総合的には、質の高い演奏だったと思います。それは、技術、個性、雰囲気を一定以上のクオリティで提供できていたこともありますし、それぞれの視点がよく練られている演奏だったとも言えます。
今後に向けた視点として、大きく2つの反省をしたいと思います。
1つ目は、マスクの壁を超えること。
講評でもいただいておりましたが、マスクをしていたとしても会場で言葉がはっきりと聞き取れるよう、もう少し調整をすべきだったように思います。特に、柔らかい音楽の場面(音量が小さく、レガート気味の場面)において、閉口母音(i, u, e)の子音は、開口母音(a, o)よりも注意をすべきでした。例:”く”じら。 一方で、例えば、くじらの優しい感じを出そうとするために子音をソフトにするという判断は間違っていなかったと思いますので、ホールの奥の客席に坐っていて、ちょうどよいくらいの量感の子音であるためには…、と考えたときには、個人的にはあと少し強く、もしくはあと少し意識をして発音すべきだったということです。
次に音量です。講評では、ホールの大きさと合唱団の人数に対して、立ち位置はベストの選択だったという声もいただきましたが、個人的には、みなさんの最大音量がしっかり出せていたのかが気になりました。合唱団よびごえの演奏としての魅力は、①作品解釈の深さと、②一人ひとりの思いの深さと、③少人数とは思えない音量の3点がすぐに思い浮かびます。マスクの影響は大きいと思いますが、マスクをつけていたとしても、音量の壁を超えれると思いました。ちなみに、合唱の場合、一人一人の声量が大きいだけでは、全体の音量は大きくなりづらいです。各パート内の音が良い感じで混ざり合い、さらに複数のパートが和音(倍音)の力を借りることで、初めて人数以上の迫力が成立します。今回は和音のはまり方は悪くなかったと思いますので、声量の意識がもう少し欲しかった、という反省と言えます。
2つ目は、力学を楽しむこと。
よびごえとしては指揮者がいない初めての本番だったと思いますが(実は過去にも1回あったのですが、ただその時はピアノ伴奏がありました)、その割にはよく縦があっていた、という一定数の評価もある一方で、僕からすると、アンサンブルとしてはもう少しやれたのでは?と思っています。それは縦が合っていなかったということではなく、「私はこのテンポで歌いたいけど、そっちがそのテンポでいくならしょうがないなぁ、折れてやろう」というのを、楽しむことができていたかどうか、という視点です。
少し脱線になるかもしれませんが、ソロでピアノを弾くのは完全に一人の世界なので他者から音楽を引っ張られるということは少ないと思いますが、例えば自分が歌い手だとして、伴奏がつくだけで一気に歌いにくくなったり、ここはこういう感じでブレスしたいのにな~、と思ったりすることはありませんか?たった一人共演者が増えるだけで、舞台上には力学(音楽の引っ張り合い)が発生します。自分はこうしたいけど、君がそうするならばこう歌ってあげてもいいよという具合です。自分一人で演奏する以外の時は、ほぼ確実にこうした状況が生まれると言ってよいと思います。つまりは、こうした力学は避けることはできないですし、自分の思い通りに歌えないということが悪いことではないということです。しかし、そういう力学を楽しめていたかどうか、という視点をみなさんにお示ししたいと思ったのは、こういう力学こそ、合唱なのではないか、と思うところがあるからです。(これは吹奏楽でも言えるのかもしれませんが。)
パートの中には小さな力学があり、全体練習の時には大きな力学があるようにも思います。そうした音楽の引っ張り合いが、結果的によびごえらしいサウンドを創り出すように思いますし、指揮者がいないからこそ、この力学と今まで以上に向き合わざるを得ないとも思います。10人未満で、かつ指揮者無しで全国大会で堂々と歌う中学生、高校生の姿を見ると、こうした力学を楽しんでいるように僕には見えます。よびごえのみなさんにも、きっと、できるはず。そこには、新しい感覚が待っているのではないでしょうか。
【前期の練習の運営について】
コロナの変異株のことを思うと、少なくともよびごえの稽古に参加したことによって陽性者が出なかったことは本当に良かったと思いました。Zoomでも、思いのほか、音楽の内容については指導ができたことも良かったと思いますし、これまでのよびごえの稽古のように、みなさん1人1人に考えてもらい、それを積み上げて演奏を作っていくというプロセスもほぼほぼ再現できたと思います。
もし後期に向けてお願いしたいことがあるとすれば、指揮者がいないとき、テンポがどんどん遅くなることは本当によくあることです。そうしたときに、曲の途中であっても軽く振って(指揮をして)、音楽を前にもっていってくれるような人がいると大変助かると思いました。前期は最初と最後だけ、振ってくれたと思いますが、「春こん。」が無事に開催されることとなり、みなさんも参加したいと思ってくださるのであれば、作品の難易度はこれまでよりも高くせざるを得ないと思います。そうしたとき、前期のような、最初と最後だけを振るシステムでは完成まで持っていけない可能性を危惧しています。
感染症対策やオンラインを活用した稽古については、前期でほぼ確立できたと思いますので、あとは上述の、より難易度の高い作品にも対応できるようなシステムの構築ができれば来年以降にも役立つものになると思います。変拍子やテンポがころころ変わる曲、それぞれのパートがまったく合わないような曲など、高度な合唱作品が演奏できる能力を1人1人はもっていると思うのですが、それを指揮者無しでみんなであわせて、本番も指揮者無しで演奏できるようになるための方法を考えていきたいですね。これは後期に向けた僕の大きな宿題とも言えますし、みなさんと協力しながら解決したい課題です。
以上、改めて、先日の合唱祭はお疲れ様でした。
夏休み真っ最中で、エンジョイされている方も多いと思います。コロナには本当にお気を付けいただきつつも、楽しいことをたくさん経験してください。YouTubeで合唱を聴きまくったり、合唱指導の本を図書館から借りてきて、なるほど!とか、いや~ここは違うやろ~!とツッコミを入れてみたり。そして、勉強会の時は、メンバーみんなで一緒に合唱と向き合いましょう。
小田
おまけ:ねぷた金魚
青森の夏はそろそろ終わります。
…
11
June
2021
2021
【2021】よびごえ日誌 小田より
みなさん、こんにちは。小田です。2021年度、初めての投稿が6月になってしまったこと、
例年のよびごえ日誌を思うと、とても遅いようですが、
一方で、この記事の裏側で、よびごえメンバーがどれほどの思いで
学びを継続しようと努力していることか、想像いただけることと思います。
さて、新年度を迎えたこともあり、いくつか
合唱団よびごえで合唱を学ぶということについて、
参考になりそうなことをメモをしておきたいと思います。
1.大学に入るまでに経験してきた様々な合唱
大人数で声を合わせて歌うということを合唱という場合、
学校は合唱をする機会が比較的多いように思います。
それは、例えば英語の時間以外で英語を使うことと
音楽の時間以外で音楽をすることを比較しても分かりやすいかもしれません。
行事のたびに校歌を歌うかもしれませんし、
「朝の歌」というものを設定している学校では
月によって歌をかえながらも、みんなで歌うと思います。
音楽集会や校内合唱コンクールに視点をよせると、
それは合唱することに重きを置いたイベントのようにも思います。
さらには、クラブ活動や部活動として、合唱に没頭することもできます。
授業としての合唱のみでなく、行事としての合唱、特別活動としての合唱、
こうした様々な合唱体験を経て、いま、私たちは大学で音楽を専攻しているのだということを
今一度認識しておくのは有益だと思います。
2.合唱の教育的成果を左右する要因を探すために
教員を目指す・目指さないを別として、
今日的に、合唱をテーマとした研究で何が言われているのか
その一端を知っておくことに損はないと思います。
研究論文や研究報告をいくつか眺めてみると、
合唱団という組織そのものの効用として、
合唱団の存在によって、所属団員と地域の人が繋がることができる
というものがあげられていたり(「地域における児童合唱団の機能と役割」, 2020年)、
合唱活動についての効用としては、
合唱活動を通して得られたあらゆる人とのつながりが醸成され、
それによって参加者自身がコミュニティへの帰属意識を高め、
さらには精神的健康への影響が考えられること、
また、そうした土台の上で情操の豊かさや身体的健康、well-beingへと
繋がっていく可能性が言われています
(Benefits of choral…
04
March
2021
2021
【2020】よびごえ日誌 メッセージ(國元)
長らくうちに置いてあった合唱団よびごえの看板を、本日返納してきました。よびごえのメンバーとして合唱することももうないのかと、何とも言えぬ喪失感のようなものを感じています。だけど、人とかモノって終わりがあるからこそありがたみや大切さが身に染みてわかるものですよね。4年前何となく入ったよびごえをこんな思いで卒業するとは、当時の私には想像もつかないだろうと思います。よびごえは、ただの歌がうまい人たちの集まりではありません。ここでの合唱は、ただ単に歌うことを楽しむとかいう次元ではなく、音楽は思考や感情を伴う学問であり、音楽を前に圧倒的敗北を味わい、盛大に悩みながら少しずつ答えらしきものが出てくる、という何ともヘビーでハードなものでした。合唱ってこんなにも頭を回転させなければならないのかと、しかしそれがめちゃくちゃ楽しかったりもするんですね。ゴールが遠くに見えていたり、なんか頑張ればできそうなことって、私は少しつまらないと感じます。だけどよびごえは、私では到底太刀打ちできない世界が広がっていて、自分の非力さを感じるけれど同時にとてもワクワクするような、そんな不思議な場所でした。無知すぎる自分に幻滅したり、こんなの考えても分かるはずがないと放り投げたくなったり、自分が小さすぎることがわかった時、あぁ自分では敵わないなと敗北を確信した時、そこで初めて答えが見えてきたり本当の楽しさとか面白さがわかってくるのだと思います。そんな場を提供してもらった私は、同じような場を今度は子どもたちに提供しなければなりません。よびごえで合唱をやってきた者として、これから教育現場に出る私には日本の合唱教育を支えていく使命があります。技術とか選曲とか練習方法諸々、学校の音楽の授業だからと妥協するのではなく、わからない苦しさもできない無力さもすべて面白いと思わせられるような、合唱の本当の価値を提供できるような、そんな音楽教師になりたいです、なります。よびごえで学んだこと、めちゃ歌がうまくて頭の良い尊敬する先輩同期後輩と一緒に歌ったこと、小田さんの想い、全部、宝物です。本当に、素敵な場所でした。この大学に入って、皆に出会えて、小田さんに出会えて、幸せです。ありがとうございました。 國元…
27
February
2021
2021
【2020】よびごえ日誌 本番後の振り返り編(森本)
会場での練習なしで客席から舞台に出るというのが新鮮で、客席に出た瞬間に緊張が押し寄せてきて少し大変でした。段々とこの舞台の空気感に慣れ、歌うことの楽しみを感じながら歌えました。気持ちが最初から作れなかったのが悔しいですが、このような状況下のなかでも本番を迎えられて本当に良かったです。そして卒団の時を迎えました。本番終了後のミーティングでも話しましたが、短い間の所属だったもののよびごえで本当に濃い経験ができました。私は作曲専攻ですが、よびごえで、実際に音楽を演奏する活動でなければ経験できない、音楽を形作ること、音楽を伝えること、音楽を共有することについて、よびごえならではの濃さをもって、沢山経験できました。そしてそれらは私の創作活動に良い影響をもたらしています。おそらく、それが、惜しくも演奏されることはなかった、よびごえの新歓コンサートのために作曲した女声合唱にも現れていたかと思います。よびごえの活動なしではこの曲は生まれていませんでした。
私は今後大学院で作曲を続けますが、このように、これからも、音楽に向き合ったり音楽と仲良くしようとしたり、または時には違う視点をも持ったりして様々な経験をし、そんな自分だから作れる新しい音楽を生み出していきたいと強く思います。また、教育(人に音楽を言葉などで伝えたり教えたり、その音楽の良さを発信することも含み)にも興味があるので、その点もよびごえでの経験をいかして引き続き探究していきたいと思います。
今までありがとうございました。 森本…
05
April
2020
2020
【2020】よびごえ日誌 号外
みなさん、2020年度がやってきました。100年に一度の非常事態の真っ只中、いま日本中に蔓延している不安は、少しでも傍で咳をする人がいれば距離を取り、いつも十分にあるはずの商品があと少ししかないと「とりあえず買っておこう」という発想を生むなど、普段の私ではない”特殊な私”を増殖させているように思います。”特殊な私”は冷静な判断を鈍らせたり、視野を狭くし、利己主義の発想を誘導したりと、どんどん自分自身を社会と切り離し、孤立へと向かっていく性質があるのかもしれません。僕が怖いと思っているのは、今の自分が自分でも気づかないうちに”特殊な私”になってしまっていて、無意識にそのような行動をとってしまうことです。クレヨンしんちゃんに出てくる上尾先生のように、眼鏡の着脱のような明確なスイッチがあるわけではないのです。自分のことは自分でしっかりと見つめること。そして、こういうときこそ身の周りの人に優しくあってほしいと思います。さて、よびごえの活動がいつ再開できるのか、先行きは見えないのですが、せっかくなので僕の中学・高校時代を振り返りながら、よびごえのみなさんには合唱について考えを深めて頂けるような「探究テーマ」(宿題)を提供できればと思います。
▽▽▽
僕が最初に合唱に出会ったのは全くの偶然でした。小学校の時から音楽集会や卒業式、授業中も音楽の先生に代わって伴奏を弾いていた記憶すらありますが、あらゆる場面でピアノを弾いていたことが中学校の先生にも引き継がれ、中学1年の終わりの頃、音楽の先生から「Nコンの伴奏をしてみない?」と言われました。もちろん引き受けました。当時の楽譜がこれです。(平成17年度中学校の部課題曲「花と一緒」)
今見ると、間違った解釈の箇所もありますが、ただこれを見る限り、少年なりにのびのびと楽譜を勉強し、また既に細かい少年だったのだと思います。この曲の伴奏について明確に覚えているのは、歌の最後の切りとピアノの切りを同時にするのではなく、ピアノのペダルをほんの少しだけ残すことで、空間をふわっと仕上げようということにこだわっていたことです。また、歌の旋律とピアノの旋律が会話するようにしたいというメモもあり、ここでも歌とピアノが互いの役割を果たしあうことで得られる効果を期待していたとも思われます。この翌年は「虹」が課題曲で、その時には歌とピアノが会場でどのように混ざるかという意味でのバランスにもこだわっていたので、この頃から、なにか伴奏へのこだわりが芽生え始めたとも言えると思います。
(探究テーマ「1.合唱の伴奏のあり方」)
実際に歌い手として合唱を始めたのも、初めてNコンの伴奏をした年でした。きっかけは、Nコンの自由曲がアカペラだったことです。もちろん先生にはこう言われます。「課題曲を弾いた後、自由曲は歌わない?」この時、実はものすごく悩みました。なぜならば、歌が苦手だと自負していたからです。ただ、中学1年の校内合唱コンクールにて、合唱部が当時のNコン課題曲だった「信じる」と、自由曲「合唱のためのコンポジションⅠ」(間宮芳生作曲)を歌っていたのを思い出して、それがやたらとかっこよかったのです。当時の自由曲は「五木の子守唄」「おてもやん」(若松正司編曲)で、この作品はどちらかと言えば「合唱のためのコンポジションⅠ」のような現代的な作曲手法が一部採用されており、掛け声の多用や、各パートがハンドベルのように重なっていくなど、作品自体の面白さがありました。その翌年は課題曲が「虹」に対して、自由曲は「44わのべにすずめ」(木下牧子作曲)でした。この頃にはハーモニーが決まったことによる快感はすでに覚えていて、さらに心に刺さった合唱作品の楽譜を収集し始めていました。
(探究テーマ「2.歌うことが好きになるヒントはどこにあるのか?」)
こうして、みるみるうちに合唱の楽しさに気づいていった僕でしたが、ある時こんなことを思いました。それは、「この曲すごい!」と直感的な感動を覚えるけれども、なぜ「すごい!」と思ったのか分からない、ということに気づいたのです。中学3年生の僕は、「なにか僕がこの曲を好きな理由があるはずだ!」と思い至り、当時もっともはまっていた曲の楽譜を買ってもらい、分析してみることにしました。それが、鈴木輝昭作曲の『ひみつ』から「うそ」でした。(特にこの最後の小節が、不思議で不思議でしょうがなかったのです。)
当時はもちろん楽典も知らないわけなので、そもそもどうすれば分析できるのか(一定のルールに従ってすべての音を調査できるのか)、その方法を開発するところから始めました。その時の僕の方法は、ピアノパートと合唱パートを頭から弾いていき、特に心に刺さった箇所をメモして、それらに法則性がないかと整理をしていきました。
僕はこの分析作業から多くのことを学びました。例えば、「半音でぶつかっている音も、1オクターブ、2オクターブと離れていくことで直接的な不快感を避けることができ、むしろ独特の美しさを持つこと」「歌のパートではフレーズの終わりで和声が解決していなくともそれにつながるピアノが和声を回収すること」「輝昭の用いる変拍子は日本語のリズムからすると全く当然の割り振りであって楽譜の見方を変えるととても読みやすい楽譜であること」「曲全体に不協和音がちりばめられているにもかかわらず最後の最後で最もシンプルな和声を長時間鳴らすことで異様な印象を覚えること」等。
(探究テーマ「3.私にとって魅力的だと思う作品の秘密はどこにあるのか?」)
こうして、我流の分析方法を手にした私は、中学校で配られる「コーラスフェスティバル」に載っている作品のうち、やはり好きな作品を分析したり、当時はやり始めた信長貴富の作品を分析したりしていました。分析をすればするほど、たまっていくのは「僕がその作品を好きだと思う理由」だけでなく、「こういうタイミングでこういう音を書けば感動するかもしれない」という作曲意欲でした。そうです、作曲を始めたのです。
「そうだ、作曲をしよう!」と思いたった僕は、当たり前のように合唱曲を書こうと思っていました。そのため、詩を探さなければいけなかったのですが、どういう経緯かは忘れてしまったのですが、選んだ詩は立原道造の「虹とひとと」でした。
詩を選んだから、「早速曲を書いてみよう!」と思い、ピアノに向かい、言葉のリズムを無視しないよう、混声四部でいきなり楽譜を書き始めたのですが、詩の一行分に音をつけるとアイデアがとまり、また一行分に音をつけると、次はその前のセクションと音楽的に繋がらないことに気づきました。ここで、とても大事なことに気づいたのです。それは、「詩の全体像を理解していないと作曲ができない!」ということでした。実は、これに気づくまで数週間はかかったと思います。どうして書き進められないのか、一行分につけた音は自分では満足していたのに、次の一行分の音と合わせると、一気に構成が崩れる気がしたのです。その曲は中学3年生を卒業するころに無理やり完成させて、いまではお蔵入りしていますが、それでもこの作業は僕にとても大きな学びを提供してくれました。
(探究テーマ「4.なぜ詩の全体像が分からないと作曲できないのか?」)
さて、ここまではまだ僕の中学時代しかお話していません。この時点で、相当、合唱や音楽そのもの、また詩にも踏み込んでいる僕ですが、これらの経験を持って、次は高校で合唱を続けることになります。
高校は、俗にいう合唱が強い学校でした。稽古方法も極めて効率的で、それでいて人懐っこい雰囲気のある、オン・オフのはっきりした部活でした。
僕の高校は、日本の現代作品を取り扱うことが多く、特殊な演奏法が出てくる作品は部員全員が「普通のこと」だと思っていました。「変拍子だから難しい」「演奏方法が分からないから難しい」といった声は一度も聞いたことがありませんでした。むしろ、特殊な演奏法を楽しんでいる雰囲気すらありました。例えば、『海の詩』(岩間芳樹作詩/廣瀬量平作曲)の「内なる怪魚 シーラカンス」では、水を入れたコップにストローを差し、息を吹き込んでぶくぶくさせる、ということが楽譜に指示されており、では誰がそのぶくぶく係をやるのか、ということでとても盛り上がりましたし、『氷河の馬』(大手拓次作詩/西村朗作曲)の「氷河の馬」では、男声が4部に分かれて裏声でクラスターをする箇所があるのですが、裏声ができないメンバーにとっては鍛錬でしかありませんでしたが、みんなで休憩時間に遊んだりすることで少しずつ楽しさへと変わっていきました。
(探究テーマ「5.一風変わった作品の要素をいかに合唱の喜びに繋げていけるのか?」)
合唱部の年間スケジュールはタイトで、1時間程度の新歓コンサートが新年度一発目で、そこから地域の合唱祭、全国総合文化祭全国大会、全日本とNHKコンクールの県大会、ブロック大会、あがよくば全国大会、そして合唱部の定期演奏会、アンサンブルコンテストが毎年のほぼマストで、それに慰問演奏や市のイベントでの出張演奏などが入ります。使いまわす曲もありますが、今思うととてつもない量の暗譜をして、1曲にかけられる稽古時間も2回の部活で本番というのもありました。新曲を読むときは、だいたい最初のパート練ですべて音を取り、2回目以降のパート練は解釈・表現にすべての時間を使っていました。
僕がパートリーダーになったとき、そんな強行スケジュールで鍛えられた「効率」は、今僕が持っている時間感覚にも大きく影響しています。1回のパート練習は50分程度。その間で複数の曲を練習しなければいけない。しかし新曲も音を取らなければいけない。となると、新曲の音取りをいかに効率的に終わらせ、各自がいったん認知した音を繰り返し反復させて自信を持たせてあげることができるか、全体の合わせになってもパニックにならずに同じことができるのか、そのためのパート練習をすることに特化しました。その結果、「あの空へ~青のジャンプ~」(石田衣良作詩/大島ミチル作曲)のような曲であれば、15分~20分で音取りが終了できていました。
では「どうやってパート練習の効率化を行ったのか」ということですが、大きくは2つのことを意識していました。
1つ目はパート練習がスムーズにいくような人間関係を築くことです。パートリーダーの言うことを素直に聞いてくれる環境はとても重要ですが、それは単純に厳しくすればいいわけではないのは皆さんご承知の通りですね。そして、高校といえば、ただでさえもいろんなイベントがあるわけです。体育祭や文化祭、定期考査、それに加えて家庭の事情もあります。この人の言うことだったら信じてみてもいいか、という関係を作るのは容易ではありませんし、キレやすい部員もいたり、人間関係のいざこざで部活に来れなくなりそうなのも僕にできる限り支えて、守ってあげなければいけません。みんなのことを第一に思っていることを感じてもらい、とにかく仲間を大事に、それでいて僕は本気でみんなと良い音楽をしたいことを伝え続けました。
2つ目は、稽古の緩急です。楽典が分かるわけでもない当時の僕たちは、いかに印象的に耳で覚えるかが重要でした。そのため、複雑な和声の箇所でも、シンプルな和声に置き換えて音を取ってみたり、「この音ってこの曲のここに似てない?もはやパクりじゃね?」などとたわごとを言うことで、過去の記憶を活用しながら新しい旋律にも親近感を覚えやすくなるような工夫をしていました。また、「早く音取りが終われば、今日のパートは全部休憩にしよう!」などと、エサで釣ることもありました。
僕のパートリーダー生活は、1時間目~6時間目までの通常授業の時に、いつもパートの仲間のことと、「今日はどうやってパート練習をしよう?」ということだけを考えていたと言っても過言ではありません。…
08
April
2019
2019
【2019】よびごえ日誌 vol.001
2019年度の新歓1日目は、ミニコンサートで「にじ色の魚」「夢みたものは…」「今日の日」「狩俣ぬくいちゃ」を歌い、その後は見学に来てくれたみなさんと一緒にワークをしました。最初のワークは、まず「夢みたものは…」の前半を音取りしたあと、「楽譜通りに歌う」ということを意識して歌唱しました。その後、では「楽譜通り」と言われてなにを意識したのか、1人1つずつ発言しました。例えば、以下のような意見がでました。
・強弱
・音の長さ
・拍子感
・音程
・フレーズ感
・言葉の節目
・言葉のニュアンス
・歌詞をまちがえない
これは、楽譜にはどのような情報が書かれてあるのか、私は楽譜に何が書いてあると認識しているのか、これらを改めて考えるためのワークです。「楽譜ってそもそも何…?」という意見も出ましたが、これはとても良い問いだと感じましたし、いろいろな情報が含まれている楽譜をもう1度捉え直すきっかけになったのではないかと思います。
例えば、誰が読んでも同様に読み取れる情報として、調性や和声、形態(アカペラ、混声3部合唱等)などが楽譜に書かれている一方で、可変的な情報も含まれています。例えば、詩や強弱記号等、「私」と「あなた」ではその意味や程度が異なる可能性があるものです。楽譜とはそのような情報の総体であり、「楽譜通りに歌う」という試みは、自分と音楽の関係を問い直すためのキーワードなのかもしれません。
2つ目のワークでは、上記の中に出てこなかった、無意識の中で感じている音楽へのバイアス、というものを取り扱いました。今回、「夢みたものは…」を歌う時、だれ一人として荒っぽい歌い方をせず、自然に柔らかく歌唱しようとしていましたが、楽譜のどのような条件が私たちをそのような歌唱へと導くのか、考える事にしました。
全体を5つのチームに分け、チーム名を考え、各チーム最低5つは要素を出すこととしました。チーム名は、「タピオカ元年」「八宝菜」「チーム女子力」「1/2長野県民」「いちごGUMI」など、個性が結集しました。
「mpから始まる指示があるから強くは歌えないのではないか」「タイトルに『夢』がつくからそのイメージにひっぱられるのではないか」「和声構造がシンプルなことに原因があるのではないか」など、全員の意見を共有することで、「柔らかい」と感じてしまう音楽の条件が自然と整理されていきました。
なぜ私たちはある音楽を柔らかいと感じ、ある音楽は固いと感じるのか。今回は「夢みたものは…」の持つ質感を「柔らかい」というキーワードを頼りに考えてみましたが、この先、日常生活のなかにありふれているモノの「柔らかい」と音楽における「柔らかい」の間に共通点を探そうとするとき、そこにはきっと、学びが拡がっていく喜びがあるのだと思います。
今回のワークは計1時間のため、各自が疑問やもやもやを持ち帰ってくれるといいな、と思い課題を設定しましたが、それらを抱えながら、これから始まる大学4年間の学びのスタートしてくれるといいな、と感じています。
みんな、入学おめでとう!楽しい学びの世界が拓かれますように!
小田…