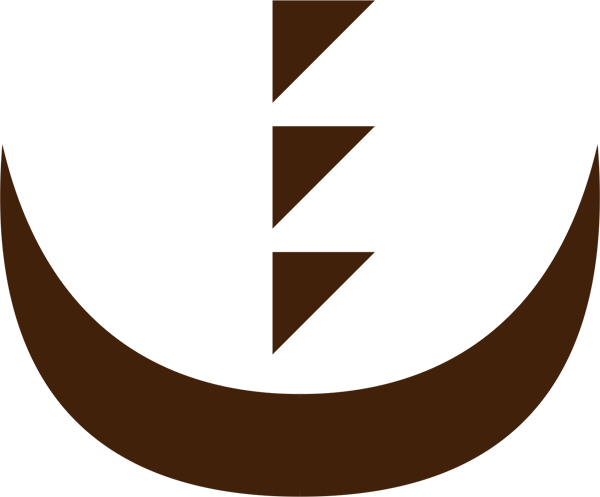home > 春こん
タグ:春こん
30
May
2024
2024
【2024】よびごえ日誌 vol.1
春こん本番からもうすぐ4か月が経とうとしている今、前年度の活動を振り返ろうと思います。この日誌を書き始めてからは3か月が経ちました。自分の筆の遅さにびっくりです。合唱とは何か。ある日、小田さんから問いがありました。
【合唱】複数人で声を合わせて歌うこと…?とそのとき頭に浮かびましたが、そういうことじゃないんだよなと思い、それからずっと考えていました。3か月以上のんびり考えて、なんとなく答えの輪郭が浮かび上がってきたように思います。まだ答えが出ていないなんてのんびりし過ぎでしょうか…。ですが私にとって合唱とは何かということについて色々と考えているうちに、自分が教員になったときに、子どもたちに合唱ってどんなものだって思ってほしいんだろう、学校生活や私の授業を通してどんな世界に出会ってほしいんだろうという問いも生まれ、自分の教育観についても考えるきっかけにもなりました。
2023年の春こんに、よびごえのメンバーとして出場することを私は諦めました。(今でも後悔していることの一つです。)よびごえの活動を休んでいる間、もし復帰したとしたらまたみんなの足を引っ張ることになるのではないかという思いがずっとありました。1年生の時の感覚が戻ってきたようでした。1年生の時の私は合唱未経験で、毎回の稽古について行くことだけでいっぱいいっぱいでした。今思えば、ついて行くことすらできていなかったかもしれません。譜面から読み取ったこと、考えたことを具体的な技術に反映させて伝えることが重要なんだなぁ。でも、どうすればいいの?音を並べるだけで精一杯なんだよな。怒られたくないし、できないやつだと思われたくない。みたいな状態で、稽古後の振り返りではそれらしいことも言ったりして、背伸びしちゃったりもしていました。ただ足を引っ張っているということだけは毎回の稽古で感じていましたし、帰りの電車では泣いちゃいそうでした(笑)でも寝たらある程度忘れてしまって、それが良いんだか悪いんだかという感じですね。なんか、楽しいかも…?と感じた瞬間もたしかにありました。ですが、1年生のときに出た春こん後、正直合唱が好きなのかはまだわかりませんでした。当時を振り返って、そんな精神状態でよく辞めなかったなと思います(笑)こんな書き方をするとどんなスパルタ稽古なんだと思われるかもしれませんが、私が卑屈なだけで、毎回の稽古はメンバーに刺激を受け、新たな視点をもらえる充実したものでもありました。なので、これからよびごえに入ろうかな~と考えている方、ご心配なく。
よびごえに復帰した私は3年生になっていました。よびごえには1年生(私がのろのろ日誌を書いていたせいで年度が変わってしまいました。今ではもう2年生ですね、びっくり。)が4人も入ってきてくれました。うれしかった。音楽するぞ!という明るいエネルギー満ちていて、みんなの個性豊かなキャラクターや考えに触れ、なよなよしている場合じゃないぞと復帰後の私は踏ん張れました。また、尊敬する同期、後輩、先輩の存在にも心救われました。そして執行代にもなったということで、運営のための仕事も担うようになりました。大変さや責任の重さだけでなく、今までよびごえをつないできてくださった先輩方や小田さんの存在の大きさも改めて実感しました。よびごえの一員として稽古ができることや本番に臨めることが本当に有難く、幸せなことだなと思います。
春こんに向けた稽古を振り返って、今年度の活動に生かしたいことは、「反省会をするタイミングに気を付けること」「言語化することから逃げないこと」の2点です。
① 反省会をするタイミングについて
今回の春こんで歌った風の馬第3ヴォカリーズとだるまさんはずっと難解な曲でした。正直、本番当日を迎えても詰め切れていない部分というか、まだわからない部分がありました。だるまさんは物語の展開が早くパニック、風の馬もだるまさんよりかはテンポがゆっくりですがどこか掴めない感じがあって気が付いたら場面が変わります。そのために、演奏するときは次をどう歌うか、次、次、、という思考が重要だと感じました。私は稽古中に自分の中で反省会を開催してしまっています。ここが納得いかない、あちゃー、息がうまく吸えないのはどうして?この和音合ってる?など、歌いながら、もう過去となったことばかり考えてしまっています。改善点をあぶりだすことはもちろん重要ですが、本番や稽古の特定の場面においては時間を割くところはそこではなく、常に先のことを考える必要があると思いました。そうすることで、自分がどう歌いたいのかということを考えるのに集中することができます。また、もう変わらない過去のことより、自分次第で変えられる未来のことを考えたほうが精神衛生上良いなとも思いました。小田さんが以前どこかで、合唱は心のハーモニーだとおっしゃっていたと記憶にあるのですが、そのときはどういうこっちゃと思っていました。ですが、春こんの練習を通して、精神面が演奏に大きく影響することを身を持って学びました。気分の落ち込みを回避するため、これからは反省会をむやみやたらに開催しないことを誓います。
② 言語化すること
理論派か感覚派か。音楽科の仲間との間でもよく話題に上ります。私は、自称インプットは理論派、アウトプットは感覚派です。何かを教わるとき、順を追って一つ一つかみ砕きながらインプットしたほうが頭に入りやすいです。反対にアウトプットするときは、伝えたいことに適した言葉を見つけるということを簡単に放棄して、表情や身振り、擬音で押し出しか浴びせ倒し、が基本技という感じですね。昨年度の稽古で、自分の気持ちや考えを他者と交換することでだんだんとチームになれるのかなと思ったので、大事な場面で自分の考えや気持ちをきちんと言語化して伝えることから逃げないようにしたいなと思いました。
春こんを終えたみんなは一つ山を登ったからね、と小田さんが先日おっしゃっていました。春こんが山登りだとしたら、私たちはどんな山を登ったのかなぁ、私はみんなと一緒に登れたのかな、山だと思って実は丘を登っていたんじゃないだろうか、景色を楽しむ余裕はなかったなぁ(笑)、頂上はどこだったんだろう、と色んな考えや稽古での出来事が頭の中を巡って、夜しか眠れませんでした。今年もみんなで山登りができるといいです。
昨年度は、かわいい後輩と頼れる?同期、優しく聡明な先輩方、いつでも徳の高い小田さんと学ぶことができて、とても充実した一年でした。ようやく合唱が楽しいと思えた一年でした。
今は、今年度のよびごえがどのようなチームになってどんな音楽に出会うことができるのか楽しみです。また、よびごえラストイヤーなので、後悔が少なくなるよう、頭フル回転で毎回の稽古や本番に臨みたいです。 稲村歌乃…
04
March
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.13
こんにちは、1Bの柳本泰佑です。よびごえ日誌なるものを初めて書いてみようと思います。私は他のメンバーのように文才がないので、稚拙で短い物となりますが、見返すときの未来の自分は優しいですよね?許してください。よびごえに入って一年間、多くのことを学んだと思う。音程の取り方、和声の感じ方といった細かい技術から、音楽の形而上的な事柄まで。小田さんだけでなく、他のメンバーからも学ぶことがたくさんあった。よびごえの文化である、「振り返り」はよくできたものだと思う。その日に得た学びというものを、言語化というプロセスまでもっていき相手に伝える。一度言葉に変換できたものは忘れないし、その後の音楽活動の糧にできる。聞く人は、その人の人となりや価値観、音楽的な気づきを受け取ることができる。「振り返り」という時間が、歌い手の、そして合唱団の音楽を潤沢にしていることに気づいた。そしてよびごえ日誌もまさに振り返り。でもなかなか手を付けられず今日まで来てしまった。小田さんが下さったせっかくの機会を大切にしないとね。
春コン、お疲れさま。2曲とも、音程はすこぶる取れないし、味わい方を知らないと面白くもない、難曲でしたね。でも、これらの曲だからこそ、今まで以上に音楽に向き合えた。そしてまた、一つの言葉に出会った。それは「音楽が、技術に先行する」というもの。すべての音楽活動には、技術と音楽性の2つの要素が存在する。しかし、そこには順番があり、常に、こうしたいという音楽の理想の形が先にあって、それを実現するための手段として技術が待ち構えている。とかく、技巧的で、常人にはできない芸当をやってのける人が「うまい」や優秀と思われることが多い。でもそれは、技術が音楽性をおいて独り歩きしているように私は感じる。音楽を志す者は常に、どんな音色、風景、ニュアンスで、というものを頭の中で音響を正確に再現し、それと現実とのギャップを、技術を用いて埋めていく工程を繰り返す。そうしていく中で、自分自身がその音楽の良さを味わえるようになる。ここまでくれば、どんな音を聴いてほしいのか、何を表現したいかが明確になるし、そのころには身体もついてきてくれる。その結果、予定調和ではないその人の「心」から湧き出る音楽をステージの上で表現することができるのだと気づくことができた。一つ、その人の音楽性の高さや音楽の才能と呼ばれるものがあるならば、それは、その人が頭のなかで、ものすごく素敵で人の心を揺さぶるような音楽を創造できる力のことだと思う。
ほかにも学んだことは多くありますが、全部書くと全くまとまらなくなってしまうし、読み返す気がかなり失せる気がするのでこの辺で終わりにします。
小田先生、そしてよびごえの皆さん、この一年間ありがとうございました。これからもお世話になると思います。よろしくお願いいたします。 柳本泰佑…
01
March
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.12 選曲への考え方
こんにちは。小田です。よびごえ日誌について、僕も更新ができておらずに申し訳ありませんでした。
※ごめんなさい、超長文です。
今年度は2月12日に春こん。を終えることができ、誰一人欠けることなく演奏できたことをとても嬉しく思っています。また当日はOGの先輩が応援に駆けつけてくださり、とてもありがたかったです。
今回の自由曲は以下の2曲。
混声合唱のための『だるまさんがころんだ』より「Ⅰ」(矢川澄子詩/長谷部雅彦曲)
混声合唱のための『風の馬』より「第3ヴォカリーズ」(武満徹曲)
相変わらずよびごえでは、「今年はこの曲をやるのね!」ではない、「???なんだこの曲は?」という選曲になりました。悩みに悩んだことは、前回のよびごえ日誌で書いた通りですが、改めて、今回の選曲のポイントを、記録として書いておきたいと思います。
➀いまいるメンバーでなければできない作品であること
➁いまもっている能力ではできない作品であること
➂数か月をかけて取り組むに値する内容や背景をもった作品であること
➃聴衆とも合唱の良さを分かち合える作品であること
とても初歩的な話をするならば、「(小田が)やりたい作品だから」「流行っている作品だから」ということではなく、教育的に価値ある作品であるかどうか、つまりは取り組むことでよびごえメンバー1人1人に何かしらの変化が期待できるかどうかを検討するための観点とも言うことができるかもしれません。
➀いまいるメンバーでなければできない作品であること
音域や声質といった技術面や、メンバー同士でのコミュニケーションのスムーズさや困難な状況下における粘り強さといった人間性やメンタル、詩や音楽への柔軟な発想(解釈)ができるという想像力や創造力など、いくつかの側面から、まずは、メンバ―1人1人の強みやこれから伸ばしていきたいところ、団体としてのポテンシャルを総合的に考えることが重要です。
合唱はチームであることから、一人ひとりがすべての観点で高い能力をもっている、ということが求められるわけではありません。あるメンバーが技術面で高い能力を持っていれば、その人がある程度は技術面で団をリードしてくれるかもしれません。一方で技術面はもう少し伸ばしていきたいけれども、想像力や創造力はキラりと光るものをもっている方もいますね。場を和ませたり、笑いをおこすことのできる方もとても貴重です。
いまのチームを構成する一人一人はどういうことが強みで、グループとして見たときにはどういう強みや課題をもったチームなのか、ここまでを整理すれば、あとはメンバー一人ひとりの強みが十分に発揮できるように、そして課題はちょっとでも自信に変えていけるような、そうした選曲ができれば、今いるメンバーで演奏する価値が生まれてくるように思います。
逆に言えば、そうしたメンバーやチームの分析無くして選曲をする場合、本当にこのメンバーで演奏する価値とは何だったのかを見失うときが来るかもしれません。仮にものすごく明るいキャラクターの方が集まっている団に、「戦争の苦しみ」をテーマとする曲を選んだとして、技術的にはクリアできたとしても、それを私事として捉え、仲間とともに心から共感して歌うことはできないかもしれません。「団に合った選曲を!」と合唱祭や春こん。の講評で言われることがありましたが、それは決して技術面だけのことではないように思います。
➁いまもっている知識や能力ではできない作品であること
教育機会として考えたとき、僕は現メンバーが今はもっていない力(知識や能力)だけれども、約5か月かければきっとできるようになるような力を想定して、「できなかったことが、春こん。を通してできるようになる」ということを重視しました。例えば、今回は、いくつかのことを念頭に置きました。ぱっと思いつく例を挙げると、「変拍子は苦手だったけど、少しは慣れた」「無調は音がとれなかったけど、少し感覚が分かった」「自分のパートが1人だとしても自信をもって歌えるようになった」「発声のメカニズムを理解して歌ってみると、いつもとは違う声を出せるようになった」「楽譜を見たときにできなさそうな不安があったけど、いまは似たような楽譜を見てもそこまで不安を感じなくなった」「これだけ難しい曲をあきらめずに演奏できたんだから、もうほとんどの合唱作品は怖くなくなった!」…というような変化をしてほしいな、というものです。
すでにもっている能力で十分に取り組める作品の場合は、教育としての価値に限定して考えれば、そこまで選曲の優先度は高くないように思います。これは、「そもそも教育とは何か」というとても大きなテーマとも関わりますが、自然発達の過程でできるようになることは、特別な教育介入をせずとも自然に獲得されるため、あまり介入の必要性は無いように思います。しかし、自然には気づけなかったり、身につかないようなこと、もしくはいつかは気づくかもしれないけど時間がかかる可能性が高いもの(例えば慣性の法則や三角形の面積を求める公式など)は、自然に気づくのを待たずに先人の研究成果を先に教えることで効率的に他のことを学ぶことが可能になります。そうして、いろんなことを知り、できるようになるよう介入していくことが、教育を受ける側にとっては将来の選択の幅を広げたり、自分らしい生き方を支援していくことにつながるのではないかと思います。(逆に言えば、何か新しいことを知ったり、できるようになるわけではない介入は教育ではないとも言えます)。
約5か月間でどの程度の力がつくと予測ができるか(変化を期待できるか)、それはやはり、選曲前のメンバー一人ひとりへの十分な観察と、メンバー一人ひとりへの信頼があってこそのように思います。予測ができない場合、何が起こるかというと、メンバーの能力と作品に取り組む期間に対して、不釣り合いな高度な能力が求められる作品を選曲してしまうことや、反対に簡単すぎる作品を選曲してしまうことが考えられます。このどちらにもメンバーに対するデメリットがあります。もし作品が十分に飲み込めなかった場合は達成感が得られず、また人によってはそれを失敗体験と感じるかもしれません。反対に簡単すぎる場合は、飽きてしまう、というのがよく見られます。モチベーションを維持できないということです。このあたりは、教育実習に行かれた方は、指導案作成時や実際の授業でご経験をされているかもしれません。
➂数か月をかけて取り組むに値する内容や背景をもった作品であること
中学校における校内合唱コンクールでも、各校種におけるクラブ活動や部活動における合唱でも、この点は重要になってくると思います。音楽科の授業を考えると、年間で限られた時数の内、一定の時間を割くに値する内容や深みのある作品かどうか、クラブ活動や部活動においては、連日の練習を行ったことを生涯の中で位置づけたときに、価値のある作品であったのか(人生で出会って良かった作品なのかどうか)、ということはよく言われることに思います。
作品に取り組む中で、最初は音を取ることや、合わせをすることに必死な状態だったものが、どんどん作品に慣れていったときに、「響き」に特に美しさがある作品の場合は、丁寧に練習するほどに声を重ね合わせることの素晴らしさを感じられるかもしれません(例えばE. Whitacreの”Sleep”は響きが美しいです…!)。詩の意味が分かることで、「こう歌いたい!」が出てくる作品の場合は、詩の解釈やそれを表現につなげていくことで、解釈することや自分とは違う意見を取り入れながら演奏を一緒につくっていくことの楽しさを感じられるかもしれません。そうした、数か月をかけることでどんどん合唱することの良さが分かっていくような作品でなければ、どこかで合唱団はエネルギーを失っていくように思います。
一時期は、哲学的な詩や社会問題、日本古来の文化等をテーマとした詩をもつ合唱作品が国内で数多く生まれました。三善晃で言えば『オデコのこいつ』や「わりばしいっぽん」、南安雄の『日曜日~ひとりぼっちの祈り~』、間宮芳生の「合唱のためのコンポジション」シリーズ、鈴木憲夫の『永久ニ』といったものです。今は、詩の内容面は昔ほど多様さはなくなったように感じています。一方で、響きの美しさの面では、今の時代の方が個人的には色彩が華やかになったように思っています。三宅悠太や土田豊貴、横山潤子の作品のように、響きがかっこいい曲はどんどん生まれているように思います。(余談ながら、作品のもつ響きが変わってきた分、求められる声のポジションも変わってきましたし、作品で想定されている合唱団の規模も、楽譜をみると変わってきたなぁとも感じます。)
数か月をかけることでしか気づくことのできない合唱の良さをもっている作品かどうか、それは教育の観点からは見逃せないものでしょう。
➃聴衆とも合唱の良さを分かち合える作品であること
演奏者として忘れてはいけないのは、演奏するとき、そこには聴き手がいることです。僕が(比較的)マニアックな作品を選ぶ理由について、どこかでお話したかもしれませんが、よびごえのみなさんが歌ってくださることで、お客さんが「この曲素敵!」「こんな曲が合唱作品としてあったのか」と思ってくれたら、お客さんがもっと合唱を好きになってくれるかもしれませんし、作曲家やその作品の見直しにつながるかもしれません。
その先に楽譜が売れれば、経済活動が付いて回ることになります。副次的ではありますが、これはとても重要なことだと思っています。作曲家の方がまた新しい作品を生み出してくださるきっかけになるかもしれませんし、やはり歌ってもらえることで作品は初めて「生きる」ことになりますので、作曲家の方の活力に直接影響するでしょう。
お客さんが十分に知っている曲を聴くとき、僕の勝手な考えかもしれませんが、過去の名演と比較しながら聴いたりしていることってあるんじゃないかと思っています。それは「粗探しの聴き方」と僕は思っているのと、それは合唱の良さではなく、コンクールに偏った聴き方に思っています。「合唱本来の楽しさ」をコンクールから切り離して聴いてもらうためには、やっぱり、聴き馴染みのない、それでいて内容の深い曲がいいんじゃないかな、とは思っています。
というこの考えは、とある高校の有名合唱部の先生の話をお借りしました。「コンクールで勝てる曲」というのがある、と感じていた時代があるのですが、そのことを思っていた時、全くコンクールっぽくない曲で全国大会に進んだ学校の先生で、その時からずっと「なぜあの選曲にしたのか聞きたい!」と思っていたのが叶った時に伺った話です。
……、めちゃくちゃ長いやん!と思われるかもしれません。僕も思っています。
しかし、「選曲」(教材選択)という行為は、合唱活動の方向を直接的に決定するものであり、つまりは教育活動の方向を決定するとても重要なことだ、ということをみなさんとシェアしたいと思いました。
コロナ初年度、オンライン勉強会を開催して、「作品を通した体験探究」と題し、「教育的な視点で合唱作品を分析する」という活動を行っていました。その時の記事がよびごえ日誌に残っていますので、リンクを貼っておきます。児童合唱や混声合唱、女声合唱の、さらには社会問題を含むもの、ナンセンス詩、宗教作品、ポップスなどの様々な作品を毎回取り上げながら、グループに分かれて、ワークシートの問いをメンバーと一緒に考え、発表し、そこからさらにみんなで考えるような活動でした。ワークシートも当時のものを参考用に貼っておきます(音源と楽譜もワークシート中のリンクからアクセスできます)。
さて、ここまでで4500字という、、、やばい!!と思っています。
今回の春こん。にて実際に選んだ2曲に関する簡単な説明はYoutubeの概要欄に書きましたため、そちらをご覧ください。
いつぞやに、春こん。が終わったとき、「合唱とはなにか」ということを考えてみてください、ということをお伝えしたように思います。
定義としては、そんなに難しくないとは思います。複数名が、いくつかの声部に分かれて歌唱する音楽の表現形態の1つですが、もちろんそんなことを考えて欲しいわけではありません。…
28
February
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.11 春こん。を終えて
こんにちは、1Bの井藤です。合唱団よびごえに入団してもうすぐ一年経つことを考えると、大学生活1年目があっという間だったな、と感じます。大学に入って自分のコミュニティが以前と比べ物にならないほど広がったことで今までの自分とは違った視点で物事を考えることが多く、教育的な面・音楽的な面共にとても充実した日々を送ることができました。
さて、今日のよびごえ日誌は春こんや春こん本番までの稽古について、またこの1年間を振り返って考えたことなどを書いていこうと思います。
まずは、春こんお疲れさまでした&ありがとうございました!
今回のよびごえの活動でも、春学期の合唱祭以上にたくさんの経験を積むことができたと思っています。
実は、春こんに向けて動き出した時、私はかなり不安でした。小田さんのLINEの内容、「春こんの曲を覚悟することができた」という文面を見て、「いったいどんな難曲が選曲されたのだろう、僕は歌えるのかな…」と考えていました。
そうして小田さんセレクトを受けた『だるまさんがころんだ』と『「風の馬」より第三ヴォカリーズ』の2曲。どちらの曲も譜読みから難しく、音取り用の音源を小田さん・藤原さんに作っていただき、それを聴いて練習しても初めは全然うまくいきませんでした。さらに2曲とも歌うパートが自分1人になる箇所(『第三ヴォカリーズ』に限っては曲のほとんどの部分・・)があり、「頑張ろう!」という気持ちはあれど「あれ、これ皆と合わせできるのかな…」という不安が大きくなっていきました。1回目のよびごえ稽古では、他のパートの音は聴かずに、まずは自分の音が合わせでも正確に取れるように意識しましたが、やはりうまくいきません。しかし悩んでいるのは自分だけでなく、皆が必死になって練習している光景は自分にとって何より勇気をくれるものでした。
だんだんと練習を重ねる中で正確に音が取れるようになってくると自信が付き、他パートの音源を聴きながら歌えるようにも練習しました。しかし…いざ稽古で合わせてみると、練習の時とは雲泥の差。実際の生の音は歌いながらだととても聴きづらく合わせづらいもので、音源と人の生で聴く声がまったくの別物だということを痛感させられると同時に、毎週の稽古の重要さも身に染みました。
そして、待ちに待った(?) 初の小田さんとの対面稽古。改めて気づかされることの連続でした。特に発声では、「空気をどのように吸って・身体のどこに溜めて・どこを通って出ていくか」を意識しながら行うこと、「この高さの音は出ない、と自分自身で決めつけないこと」など、今まで自分が行ってきた発声が如何に無意識に声を出していただけだった、ということが露わとなるようなことばかりでした。いつかの稽古の振り返りで、自分は高校の先生が「本番前に10発10中ではなく100発100中になるように練習しなさい」と言われたことについて話しました。小田さんはよびごえの稽古で皆がわかりやすいように明確に言語化して、つまり理論的に、発声や歌のヒントを提示してくれました。小田さんの教え方から、「100発100中」も大きなイメージではなく、1つ1つの身体の動きやテクニックに理由と方法論を用いて技術を構築していくことで「まぐれ」を無くしていく工程、と捉えられるのではないか、と思います。
音がそろってくると、今度は歌詞や音程間の解釈に取り掛かりました。まだよびごえに入団して1年も経っていませんが、他のメンバーと意見交換をしながら時間をかけて曲の解釈を深めていく過程は、よびごえならではのとても良い活動だな、と思っています。1人ではきっと気づかなかったであろう新たな表現方法を発見したり、音楽に対する視野が広がったり、様々な視点からの歌詞解釈ができたりと、とても楽しい時間でした。この時間が無ければ、『だるまさんがころんだ』では怖く感じるイメージだった音形が温かく感じることはなかったし、『第三ヴォカリーズ』では曲の流れをはっきりと言語化することはできなかったと思います。
そして迎えた、春こん本番。今までの練習や稽古で取り組んできたことが多かったため、成果を出し切れるか、ホールでしっかり響く声で歌えるかと若干の緊張がありました。ですが、「音楽は、最後は心だから」という小田さんの言葉で、楽しく歌い切ることができました。曲の出だしの音量が違うといった点もあると思うのですが、夏に合唱祭で歌った時と同じホールだとは思えない程、第一声を出した瞬間にホールがよく響いていることがわかりました。練習でできたことが100%できた、とは言えないのが本番の怖いところですが、当日1人も欠けずに楽しんで演奏できたことは自身のとても素晴らしい思い出になりました。
4月からは大学2年生となりますが、この1年間で学んだことを活かして、自分に足りていない力を付けられる1年にしていきたいと思います。小田さんが春こんに向けたよびごえ日誌に「より良い合唱活動を実施できるようになるためには、たくさんの作品を知っておくことも大切」と書いていました。私が合唱団よびごえの一員として歌ってきた曲は今まで知らなかった曲の方が多く、知識・技術含めたくさんの経験を積むことができました。来年度からよびごえも新たなメンバーとなりますが、新1年生も一員に加わり、より多くの経験を一緒に積んでいけることを楽しみにしています。
長々と書いてしまいましたが、これで最後です。お付き合いください。
「教師はネガティブではいけない、ポジティブであれ。」少し言い切った形で書きましたが、稽古で小田さんがおっしゃった言葉です。東京学芸大学で1年学び、入学前より教壇に立つことが楽しみな反面、教師の裏側も思っていた以上に大変そうです。正直に言って、自分はポジティブではありません。理解していても、気が付くとネガティブ方向に偏っていきます。よびごえの活動含め、少なくとも大学4年になった時、このよびごえ日誌に自分がポジティブになれた、といった表現がより多く書かれていることを願っています。
ありがとうございました。
井藤一輝…
27
February
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.10
こんにちは、1Aの小林です。1年前の今頃はちょうど前期受験を終え、後期受験の不安と闘い、合否発表の日が来るのを震えながら待っていたことを想うと、改めて月日の流れの速さを感じます。あっという間ではあったけれど、この1年は自分にとって出会いと学びと音楽に恵まれた、すてきな1年でした。
さて今回は、春こんという1つの行事を終え、年度内の活動が終わった節目ということでよびごえ日誌を書いています。前回の日誌で小田さんからお譲りいただいた稽古の様子を含め、自分なりに考えたことや稽古を通して変わったことをお話しできたらと思っています。お付き合いください。
今年の春こんで僕たちが歌ったのは、『だるまさんがころんだ(詩:矢川澄子 曲:長谷部雅彦)』よりⅠと、『風の馬(曲:武満徹)』より「第三ヴォカリーズ」という2曲です。いま、本番前に見たのを最後に久しく開いていなかった楽譜を眺めながら書いています。書き込みがいっぱいです。大変に難解な2曲でした。
まずはだるまさんについて。初めて曲名を聞いたとき、知らない曲だ、YouTubeで聴いてみようと思い一番上に出てきた動画をタップしました。流れてきたのはなんと打ち込みの機械音声。衝撃を受けました。一つ下にあった動画からはひとの声が聴こえてきたので安心しましたが、流れていくだるまさんの応酬に?が止まりません。かと思えばそれは参考視聴用の音源だったので1分たらずで終わってしまいました。YouTubeの世界に存在するこの曲の音源は、僕が観測できた限りこの2つだけ。これはやばそうだぞ、と、だるまさんに対する第一印象は不安でいっぱいでした。
風の馬について、こちらは演奏の参考音源にこそ(だるまさんに比べれば)困りませんでしたが、曲の難解さはだるまさんと同等かそれ以上だったように思います。日本語として聴きとれる歌詞がないこと、不安を誘うような和音の連続、そして何より突然やってくる終結部、最初に聴き終えたときはこの曲を自分が歌うんだということを忘れてしまうような呆然とした感覚になりました。
2曲に共通して言えることは、全然好きになれそうになかったということです。
譜読みしてみても、合ってるんだか合ってないんだかさっぱりわからないまま稽古は始まりました。みんなといっしょに歌ったらわかるのかな?と思ったりしたこともありましたが、そんなことないどころかむしろ逆でした。こんな難しい曲に挑んでいるのに、先輩方は「よびごえっぽい」「こういうのにもきっとすぐ慣れちゃうよ」「私たちもそんな風にわけわかんない時期があったなァ」とニコニコしていて、マジかよと思いながらついていくので必死でした。
後期の活動に入って初めて体験する出来事がありました。対面稽古です。オフラインの小田さんは、勝手に持っていたイメージよりずっと背が高いひとでした。対面稽古を通じて何より強く感じられたことは、自分の声が持っている可能性です。うまく文章にはできないけれど、声域的な意味でも声質的な意味でも、自分はもっと幅を広げられる、それを表現に活かす余地が無限にあるのだという前向きな気持ちになりました。これはよびごえの活動についてだけでなく、ソロで歌うときにも活きています。技術と表現の「分けて考えるべき部分」と「双方向に繋げて考えるべき部分」という二面性、音楽をやっていくうえで不断に挑み続けなければならないこの課題に対するヒントやアイデアをたくさん吸収できた時間でした。
年が明けてから、一気に稽古の空気が変わったように自分は感じています。初めのころは「訳が分からない」「音が取れている気がしない」「あってるはずの和音が気持ち悪い」とプラスな考えが浮かぶ兆しがほとんどなかったのに、年明けの稽古からは歌っていて楽しいと思える音やフレーズが1つ、2つと増えていきました。終盤の稽古になって取り入れられた、パートバラバラで2グループに分かれて歌う練習は特に楽しかったです。普段近くで歌うことがないひとたちの声が近くに聴こえて、自分の声部の役回りを強く感じられました。最初は頭がいっぱいで苦しかった通し稽古も、回を重ねるごとに面白くなってきて、ここ決まった!うれしい!!と思えることがどんどん増えていきました。今考えてもとても不思議です。最初は全然好きじゃないとか思っていたのに。
きっとたくさん考えたことを共有して、たくさん気づいて、たくさん歌った稽古の蓄積と、それから小田さんの魔法と計算のおかげだったのだと思います。
本番は本当に楽しく歌えました。ホールが鳴っているのが聴こえて、拍手のあと観客の「すごい、、」というつぶやきも聞こえて、表現や技術的にもっとできたことはもちろんあったとは思いますが、充足感の得られる本番になりました。よびごえの一員として出場出来てよかったと、胸を張って言えます。
4月からはまた新たな体制で、新しいメンバーで、新しいよびごえが始まります。この1年で先輩方から得られたようなことを周りに与えられるように、そして自分だからこそ与えられることを周りに与えられるように、来年の春こんを終えてまたこの日誌を読み返している自分が今よりすてきな表現者になっているように、新しい1年も大切に豊かに過ごしていきたいです。
今頃ちょうど前期受験を終え、後期受験の不安と闘い、合否発表の日が来るのを震えながら待っているであろう次の1年生が、1人でも多く合唱団よびごえに興味を持ち、やがてチームになって、「私たちもそんな風にわけわかんない時期があったなァ」とニコニコ言う側になる日が来ることを願って、今回の日誌を終わります。
ありがとうございました。
小林翔人…
27
February
2024
2024
【2023】よびごえ日誌 vol.9 はるこんを終えて
今回のテーマは、はるこんを通して合唱について学んだことですので、そのテーマに沿って書いていこうと思います。さて、音楽には、二つの側面があると私は考えています。一つは純粋な遊びとしての側面。これはそのままの意味合いで、個人が自発的に、自身の心を満足させるために行う状態です。(遊びにも様々な定義がありますが、ここでは“子どもがするもの”や“片手間でするもの”という意味ではなく、行為自体が目的であるものをさします。大和言葉で管弦は“あそぶ”ものであって、英語では楽器がplayするものであることは、音楽のそういった側面を反映しているようにも思います。)もう一つは、人との結びつき、すなわちコミュニケーションや、社会を形成する側面です。こちらは、表現あるいは文化とされる音楽を主に指し、人と共有することをゴールとしています。聴き手、共演者、援助者や教育者、あるいは村や団体などの共同体、故人からのつながりなど、様々な結びつきを生んだり、強めたりするものです。合唱には一般的に、後者の側面を強く持っていると感じます。すなわち、“共有”を重視する側面です。共有物には幅広く様々なものがありますが、その中でも重要になってくるのは曲ではないかと思います。小田さんと、合唱の選曲についてお話ししたことを思い出し、選曲について自分なりに考察したことを述べさせていただきます。
教育者として選曲をするとき、そこにはどのような意味合いがあるのでしょうか。先日見学したある小学校の授業で、選曲について興味深い話がありました。曲を子ども自身に選ばせたとき、商業的に成功しているものが多い、というものです。商業的に成功しているから、自然に耳に入る。多数の人が良いと感じたのは事実かもしれませんが、その成功にかかわっているのは純粋に曲のよさや好感度だけではないでしょう。そうした曲を子ども自らが選んだ時、それは自発性といえるのか、という議論でした。このことは、人が社会すなわち他の人の影響から逃れることができないということを示していると思います。自発性すらも、何らかの人の影響があってこそ、出てくるものであるのかもしれません。そう考えた時、子ども自身に選択をゆだねることも一つの方法ですが、様々な選択肢があることを示し、新しい世界を見せることも教師の重要な役割の一つではないかと思いました。教師が提示した曲によって、子どもは自分の中に新たな文化を内在化させ、そしてそこから外界の新たな文化とつながっていくこともあるでしょう。
今回よびごえで歌った二曲にも、様々な要素が含まれています。二曲に共通する要素として小田さんが述べたのは、「願い」や「祈り」でした。願いや祈り、欲求というものは、生きる根本に深くかかわっているものである気がします。一人ひとり、そこから考えたことは異なったと思いますが、このテーマと選曲は私には、将来を考える時期も重なり、生きる意味を考える時間を与えてくれたと思います。皆さんにとっては、この選曲にはどのような意味合いがあったでしょうか。
さて、今回は合唱について学んだこととして選曲というテーマを取り上げ、長々書いてしまいましたが、頭を使った話はおしまいにして、最後に少しだけ気持ちを書かせて下さい。
一年前、一時期は本気でやめることを考えていたよびごえでしたが、一年終わってみるとここまで皆さんと時間を共にできて幸せだったな、と思います。執行代として大したことはできませんでしたが、よびごえを通じて、色々な新しい出会いもありました。卒団された先輩方から、今でも温かい言葉をいただくこともあります。前に、メンバーからなぜ専攻に声楽を選んだのかと聞かれたとき、理由がぱっと思いつかなかったのですが、私が歌が好きな理由は、音楽を通して人とかかわり、つながる時間が好きだったからだったなぁ、とふと思いました。よびごえもたった週に一回の稽古ですが、そうした色々な人との大切な場所の一つになっているし、これからも大切にしていきたいなと思います。そして、これからも合唱を通じて、大切な人や場所を増やしていきたいです。
大変長くなりました。半年分を一気に詰め込んだと思い、お許しください。ここまでお読みくださり、ありがとうございます。 一柳優里愛…
02
November
2023
2023
【2023】よびごえ日誌 vol.9 今年も春こんが始まります
みなさん、こんにちは。小田です。この前始まったかと思う夏休みも、あっという間に終わり、後期が始まりました。
後期の活動としては、春こんでの発表に向けて、2つの合唱作品をみんなで時間をかけて学んでいきたいと思っています。
稽古の様子は次回以降のよびごえ日誌に譲ることとして、今回は、自由曲候補には挙がったけれども、取り上げなかった作品を紹介したいと思います。
みなさんが将来、より良い合唱活動を実施できるようになるためには、たくさんの作品を知っておくことも大切に思います。以下、ご存知の作品もあるかもしれませんが、どれも素敵な作品ですため、これを機に聴いてみてもらえると嬉しいです。
そして、この曲だったら一緒に合唱をする仲間と①どんなことに新しく気づくことができそうか、②なにができるようになるか、③これから先の音楽学習を考えたときにどのような役割を果たすか、ということについても考えてみてもらえると、さらに、実用的な学びになろうと思います(作品の教材可能性)。例えば外国の宗教作品であれば、①その宗教ならではの考え方や言葉、ユニークな音響の美しさに気づきがあったり、②純正律の響きを求めて、4度や5度、8度の響きをきれいに響かせることができるようになるかもしれませんし、③そうした学びは、日本の作品を取り扱うときにも4度や5度、8度の響きを意識するきっかけになるかもしれませんね。日本の民謡をモティーフとする作品だったらばどうでしょうか、歴史的な問題を扱った作品だったらばどうでしょうか…、さまざまに考えてみてください😊
◆『合唱のためのコンポジションⅠ』(曲:間宮芳生)
日本の合唱界では、新しい作品が演奏される傾向があります。新しいというのは、例えば委嘱作品もそうですが、ご健在の作曲家の作品を指しています。例えば今年のNコンでは高田三郎(1913-2000)の作品を取り扱った学校もありましたが、比較的珍しいように思います。
よびごえのみなさんとの「学び」という観点で考えると、合唱界に携わっていると自然に接することの多い作曲家よりも、間宮芳生を含む、すでにレジェンドになっている中田喜直、武満徹、三善晃といった、過去の一時代をリードした作曲家の作品についてともに学び、今日のコンテキストで捉え直すことは重要な学びなのではないかと考えて、この作品を思いつきました。
『合唱のためのコンポジション』は間宮 芳生(まみや みちお)のライフワークと言って良いと思いますが、その最初の作品はみなさんにはどう聴こえるのでしょうか。僕はこの作品を中学1年生の時に初めて聴いて、中学3年間、ずーっと頭から離れずにおりました。中学生当時の僕には、よく分からないけれども、なんだかすごくかっこいい曲だと感じたのを覚えています。
◆”Cries of London”(曲:Luciano Berio)
1974年に書かれたこの作品は、まもなく50年を経とうとしている今日においても古さを全く感じさせない、緊張感のあるサウンドが特徴です。よびごえメンバーであれば、こうした作品にも取り組めると思いましたが、現代音楽の特徴である著作権の関係で楽譜代が高く、今回はそれを1つの理由として、候補に留まることとなりました……。
◆Mama Afrika(曲:Sydney Guillaume)
ハイチ出身の作曲家による、ハイチそしてアフリカに焦点を当てた作品です。小田はまたこういう曲にすぐ飛びつく…と思われそうですが、たしかに自分でも、こうした、日本以外の、世界や人々の歴史に目を向けられるような作品が好きなのはあるのかもしれません。
コロンブスの航海についてはみなさんご存知に思いますが、さて、コロンブスによって新大陸が発見されたことは、その後の現地人の未来にどのような影響を与えたのでしょう。ハイチは、コロンブスによって発見されたことで、先住民(タイノ人)は絶滅させられ、西アフリカの黒人は、奴隷としてハイチに強制的に連れてこられ、労働を強いられました。
ハイチの歴史はアフリカの黒人たちの歴史でもあり、そしてアフリカは人間の誕生の場所ともいわれる(と作曲家は捉えている)、こうしたテーマを持つこの曲は、よびごえのみなさんとともに学ぶ価値のある、大変に魅力的な作品に思えました。しかし、打楽器が必要なため、春こんでは演奏不可でした…。
◆『唱歌』より第3楽章(曲:千原英喜)
間宮の『合唱のためのコンポジション』と似た発想の作品ですが、千原の特徴ともいえる、甘美な旋律が含まれている点で、間宮に比べて多分に今日的です。僕もこの曲を歌ったことがありますが、なんとも不思議な作品で、各パートのかけあいにかっこよさを感じたことを覚えています。テキストは トテシャン チリリン など、口三味線の言葉で構成されています。
◆I Will Lift Mine Eyes(曲:Jake Runestad)
Eric Whitacreというアメリカの作曲家がいるのですが、彼の作品を初めて聴いたとき、とてもびっくりしたのを覚えています。日本では”Sleep”(https://youtu.be/aynHSTsYcUo?si=U8Vg6NEbDnTZe8bP)や”Leonardo Dreams of His Flying…
10
March
2023
2023
【2022】よびごえ日誌 メッセージ(堀切)
こんにちは!4Aの堀切です。今回のよびごえ日誌は、書きたいことは沢山あるのになかなか書き進めることができませんでした。それは、書きたいことを文面にした時に、言葉が気持ちから離れていってしまうような感覚が強かったからです。書くために書いているような感覚、という感じでしょうか。普段の振り返りでは、直接話しているという即興性とライブ感で素直なことが話せますが、文章にするというのはそれ特有の難しさがあると感じました。ただ、今回の本番とこの4年間の振り返りを記録として残しておきたいので、できるだけ飾らず素直に書けたら良いなと思います。
まずは、今回歌った2曲について書きたいと思います。
今回歌った「Cikala le Pong Pong」と「Soleram」は共にインドネシアの曲ということで、そのアプローチがとても難しかったです。今、私自身やよびごえ全体としての曲に対するアプローチを振り返ると、共通性と固有性という視点が重要だったのではないかと感じます。私は、「Cikala le Pong Pong」を理解するにあたり、日本や自分との共通性に先に注目し、それを基盤として固有性に迫っていったと思っています。少し具体的に書くと、まず日本の結婚式のしきたりや様式と曲とを比べ、相手の家を立てたり形式を尊重したりして、思いとは裏腹なことを言うという共通性があると思いました。その後、では本当の思いとは何なのか、それはどうやって子どもや聴いている人に伝えているのかという共通性を基盤とした視点ができ、それがシンプルなリズムやフレーズを繰り返して没入感を生み出すというインドネシアの音楽の特徴や、踊りも含めたこの曲がもつ民族的なエネルギーの高さといった固有性の理解・体感につながりました。一方「Soleram」の場合は、インドネシアでポピュラーな子ども向けの歌であるということや、インドネシアの国民性と言われている奥ゆかしさが反映された歌詞であるという知識が先にありました。そしてその固有性から曲の背景を捉えた上で、子どもを想う親の気持ちという国を越えた共通性が、曲の世界観や歌っている時の自分の支えになっていたと感じます。私の中でも、曲によってアプローチが違いますし、同じ稽古をしている他のよびごえの方々も、人によって様々なアプローチをしていたのだと思います。どれが正しいということは無く、自分が一番腑に落ちる形で曲に対する理解を深められることが大切だったのだと思います。自分達とは異なる文化や音楽とどう接したら良いのか、その過程を実際に体験できたことはとても勉強になりました。
次に、よびごえの活動全体について書きたいと思います。
最初はよびごえの本番までの過程をできるだけ詳しく整理しておこうかとも思ったのですが、何だか違う気がしたので止めました。ここでは、よびごえの活動の自分なりの解釈について書こうと思います。
よびごえでやっていることを私なりに一言で表すと、「表現の主体者として、根拠をもって音楽をデザインすること」だと思っています。これが成り立つためには様々な要素が関係していると思いますが、団員個々の解釈や音楽表現が尊重されること、曲の世界観を理解する機会が保障されていること、この2つが特に重要な要素だと思っています。そして、この重要な要素は、解釈や音楽表現を無理に統一しないこと、曲の世界観について歌詞や背景、音楽から理解した上で、それを音楽表現に還元すること等の、よびごえで大切にしている考え方に支えられていて、そのような考え方がよびごえらしい学びを形づくっているのだと私は解釈しています。また、よびごえにおける合唱に対するアプローチが、そのまま団員同士の関係性の基盤になっていることが、よびごえという合唱集団の人間関係の特徴だと私は思っています。個人を尊重し主体的に行動するというのは集団の理念としてよくあるものだと思いますが、それが指導法と照らしても齟齬が無いというのは珍しいことなのではないかと思います。そして、このような活動をしているよびごえだからこそ、自分らしく学ぶことが誰かの学びや気付きになっているということに、卒業のタイミングで気付かされました。私にとってよびごえでの学びは、色々な要素や視点が混ざりあった多角的で開かれたものだったので、これからも自分の中で反芻しながら学びを深めていきたいと思っています。
さらに、私自身の大学4年間について書きたいと思います。
大学4年間を振り返ると、大切にしたものは大切になるということを改めて実感します。例えば、何かやってみたいことや興味があることに思い切って挑戦したことで、それが自分にとってすごく重要なものになったり、自分が変化するきっかけになったりしたことがありました。また、自分が大切にしたいと思っていたことが、色々な原因で大切にしきれなくなりそうだったとき、そのままそれを手放してしまったことも、ここだけは譲れないと大切にしきったことで、自分の揺らがない根幹になったと感じたこともありました。さらに、最初はあまり大切に思えなかったことでも取り組んでいくうちに、気付いたら実は大切なものになっていたということもありました。何かと接するときそこには必ず相手や対象が存在して、自分がした行動の影響を自分も相手も必ず受けるということを忘れないようにしたいと思いました。大学で学んだことを大切にしながら、何かを大切にできる勇気と柔軟性をもって過ごしていきたいと思います。
最後に、いつかこの日誌を読みにくるであろう自分に、せっかくのHPの位置づけを生かしてメッセージを残そうと思います。
この日誌を読みにきたということは、おおよそよびごえでの合唱体験をどうにか自分でも実践しようとして、行き詰まってしまったといったところでしょうか。もしよびごえの詳しい練習の様子が知りたいのであれば、他の日誌や当時の楽譜・録音を振り返れば良いと思いますが、そこまで不安になり過ぎる必要はないと思います。よびごえでせっかく学んだことを取りこぼしてしまったと思っているなら、たった4年で全てが理解できるほど合唱は単純ではないし、自分が本当に大切にしたいと思っている理念はちゃんと自分の中に残っていると思うので、安心してほしいです。むしろ、変わり続ける自分の教育観の中で、よびごえで学んだことを捉え直すことこそが、よびごえでの学びを生かすことにつながるのではないかと思います。教育観を確かに、柔軟にもちながら、目の前の子どもをよく見て、ともに学びを作っていってください。
本当に最後になりますが、よびごえで関わってくださった全ての皆さん、本当にありがとうございました。よびごえにいられて本当に良かったです!
堀切彩愛…
21
February
2023
2023
【2022】よびごえ日誌 メッセージ(原田)
こんにちは、3A原田です。春こん。ありがとうございました!
今年も本当にあっという間で、でも私なりにたくさん学んだ稽古期間でした。せっかくなので、去年の私と同じ3つのテーマで振り返ってみようと思います。この間書いたばかりなのに、また長くてすみません……
◎歌唱技術について
いつかの稽古の帰り、“発声はファンタジーじゃない”と小田さんに言われたのが印象に残っています。また、稽古では声量で感動させる、という話があって、アルト1全体で求められていたほど声量アップできたのかは分かりませんが、4ヶ月で少しは気持ちよくクレッシェンドできるようになった気がしています。指導者として「もっと元気に!ffで!」という指示をするのは簡単ですが、体をどう使えば大きい声が出せるのか、どんな練習や環境構成が効果的か、まで考えなければいけないな、と実感しましたし、そうして学んだ技術が増えれば増えるほど、曲での表現の幅が増えるのだと思いました。
余談ですが、私は発声中の小田さんの「筋肉と会話して」「ブレスから勝負は始まっている」といったパワーフレーズが好きで、この4ヶ月でも楽しい指導言がたくさんメモできて嬉しいです。「OK?」と優しく聞いてくださるのも好きなので、今度の実習で使ってみたいなと思います。
◎曲について
今年取り組んだ2曲は、インドネシア スマトラ島北部のパクパク族民謡と、リアウ諸島の民謡でした。稽古では、詩を一語ずつ訳して、インドネシアの文化にも触れながら、詩の解釈をしていきました。子どもは何歳でどこにいるのか、どんな抑揚をつけたら民謡らしくなるか、この部分にはどんな気持ちが隠れているのか、それはどんな技術で表現できるのか、など、没入感をもって歌うための解釈をたくさんできたように感じています。没入感といえば、先日声楽のレッスン中、突然ゾーンに入ったような、曲の世界観に閉じ込められたような気分になったことがあって、私、成長できているかもしれない……!と嬉しくなりました。表現するには、正解を察することではなくて、自分なりの解釈に入り込むことが必要なのだと最近ようやくわかってきた気がします。教育現場で扱う外国の音楽も、子どもなりの解釈ができるよう文化への理解を深めることで、よくわからないまま綺麗に演奏する、ということはなくなるのかもしれないと思いました。
また、今回は詩と音楽だけではなく、踊りの稽古もありました。視覚的な一体感は強烈でしたし、合わせて作った衣装もインパクトがあって、本番も変なことしてる感じが面白かったです。振りが付いているChikala le Pong Pongでは、詩から踊り方のイメージを膨らませたり、それぞれの動きに込められた意味を感じることで音楽の方向性が決まったりと、それぞれが影響し合ってを曲を作っていることが実感できました。
そして、この2曲は、民謡として誰かの人生の中で実際に歌われている曲という特徴もあります。合唱団ではなくても歌う人がいて、コンクールのステージでなくても歌われるタイミングと場所がある曲。それゆえの難しさがあったとは思うのですが、最後の稽古で“この曲は春こんが終わっても、明日も明後日も歌われる曲だよ”という話があったとき、なぜか少し嬉しくなりました。それは、ステージの本番のために準備する曲があるのと同じように、大切な人のために歌う曲、自分のために歌う曲があって、私の中でそれはどれも同じように大切だから、かもしれません。個人的な意見ですが、私は、“歌いたい”という衝動は本来、ステージ上よりも寧ろ日常の、どうしようもなく悲しいときや嬉しくてたまらないときの方が湧いてくるのではないか、と思っています。そうした衝動を、表現に繋げられたら、言われた通り歌うだけの合唱にはならないのかなあ、と考えたりもしました。音楽科にいるからこそ、日常の中の音楽、生活の中の歌の価値、意味にも気持ちが向けられたらいいな、と思います。
◎合唱について
大学に入ってから、たくさんの人のおかげで歌を歌うことが本当に楽しくて幸せだなあと思っています。ですが、それと同じくらい、合唱をすることにたくさん悩んできた気がします。私は歌うと元気になるはずなのに、合唱をするとなんで疲れるんだろう?とか、やっぱりコンクールは苦手だなあ……とか。「合唱が大好き!」と嬉しそうに振り返りをしているよびごえメンバーを見て羨ましく思ったり、声楽ではできることが合唱だとうまくいかなくて落ち込んだりもしました。それでも、合唱は私にとって楽しいものですし、そう思えているのはよびごえのおかげだなと思っています。素敵な環境にいられて嬉しいです。
去年の日誌で「関係性」の話をしたのですが、合唱団の中の関係性というのは、常に変化するものです。去年の私は先輩方に追いつこうと必死で歌っていましたが、今年は逆にパート練を進める立場になって、自分の歌唱技術を頼りにしなければならない場面がたくさんありました。そこには責任感のようなものが生まれていたのだと思います。このような変化が至る所で起こっているのが集団というもので、教育現場での合唱は、そういった関係性の変化が大きく演奏に影響するのではないかと思います。指導者との関係性、曲との関係性もありますね。合唱指導をするということは、広い視野とバランス感覚をもって、そういった変化にも敏感にならないといけません。声を合わせて、と簡単に言うけれど、楽器で音色を合わせるよりも声を合わせるのは感情を消費する作業だよなあと思ったり。これまで素直に歌えていたのに指導者の一言で歌いづらさを感じるということがあれば、逆に歌いやすくなることもあるなあと思ったり。賞がつくと頑張れる人がいる反面、音楽に…賞…?と心がざわつく人もいるかもしれません。歌うことを好きでいてほしい、と願うほど、合唱指導は難しいなあと感じます。
コンクールについては、夏の勉強会で“子どもの学びを支える合唱作品”の重要性を感じるとともに、歌い手が充実感をもてるコンクールへの向かい方について、春こん稽古からもヒントを得られた気がして嬉しいです。価値ある合唱指導、正解があるわけではないですが、歌い手側の思考を促す指導は大切にしたいと思います。絶対的な理想を押し付けられるのではなく、子どもたちが自由に考えてそれを主体的に歌にできる……コンクールに出たことで、その過程を経験できるような指導をしたいです。先生にお守りで貰った金のキーホルダーを見ながら、金賞じゃないとだめなのか…と不思議がっていた私のような小学生も満足する指導ができたら、当時の私も喜んでくれる気がします(笑)。
それにしても、周りのブレスを感じて、自分の声と同じパートの人の声を、自分とは違う音との重なりを感じながら、解釈の受け渡しをし、指揮者の要求にも応えつつ、最終的に伝えるものは空間全体にある音楽で……と考えると、様々な要因を含んだ、複雑で繊細なことをしているんですね。でも、いや、だからこそ、連帯感、親近感、一体感……でしょうか?一緒に歌うことでしか味わえない感動や魅力が合唱にはあって、私はそれが好きなのかな、と思います。
そして、よびごえでの時間はいつも、これまでの人生で一番真剣に、そしてマイペースに合唱と向き合える時間だと思います。こんな書き方をすると、いつものように各方面から考えすぎだの思いつめすぎだのと声をかけられそうですが、寧ろ逆で、こういう時間が欲しかったので嬉しいです。私は小学生にどんな気持ちで歌を歌ってほしいのか、合唱からどんなことを学んでほしいのか、それにはどんな手立てが必要なのか。先生になる前にもう少し深くまで考えてみたいです。
改めて、
4年生の先輩方、卒団おめでとうございます。関われた期間は1年ほどですが、先輩と一緒に歌えて嬉しかったです。ありがとうございました!
そんな偉大な4年生さんと、優しい同期、頼もしい2年生、かわいい1年生、こんな濃いメンバーで毎週一緒に歌える場所があるってすごいことですよね。いつもありがとうございます。幸せです。
小田さん、面白くて新鮮で楽しい稽古をありがとうございました。よびごえからもらったたくさんの学びを、自分なりに広げていけるように頑張ります。
春こん。本当にお疲れさまでした!
原田綾乃…
05
January
2023
2023
【2022】よびごえ日誌 vol.12
こんにちは!3A原田です。2023年もよろしくお願いします!
新年一発目の稽古は、小田さんが大学まで来てくださり、Zoom越しではなく対面で行いました。以下稽古の流れです。
発声(ハミング・a母音で声量意識!)
2曲通し
2パート練(Sop./Alt.)
全体稽古
振り返り
まず発声では、ハミングで徐々に跳躍の幅を広げて息のスピードを速くする練習、a母音でクレッシェンド、fで出す練習をしました。大きい声を出すとき、私はまだ別のところに力が入ってしまったり、息の通り道の意識が薄れてしまったりと、百発百中で気持ちよく大きい声が出せないので、春こんまでの課題だなと思っています。
その後は、一度通しをしてから2パート練。そして全体稽古をしました。
Cikala le Pong Pongでは、息のスピードを速く、というのと、とにかく輪郭をはっきりすることが個人的な課題だと感じました。全体稽古のなかでは、リズムで勢いを出したり整えたりすることがテーマだったように感じています。フレーズ間の引力への意識だったり、パートごとのリズムを立てる場面だったりという意識が、客席で聴いてくれる方の聴きやすさ、ノリやすさにつながるのだと思います。また、最後のHei!のテンション感についても、もう少し意味を持たせられるといいな、と思います。
Soleramでは、勢いを保って大きく捉えて歌うことが重要だなと思いました。そのためにもやはり声量を出せるように練習したいです。また、2パート練でアルト2の声を聴きながら、インドネシア語、マレー語をはっきり伝える意識が足りていないな、と感じました。去年も感じたことですが、外国語に対してはどうしても日本語よりも「伝える」という感覚が薄れてしまうように感じます。言語として音を理解して、それを客席に届けられるように歌いたいな、と稽古を経て感じました。私自身、一人で歌うときはどうしても内的な楽しみ方をしてしまうので、自分の外側へ、伝えるという意識をしながら歌える環境は貴重だなと思います。
本番まで日が迫ってきましたが、後悔のないように、よびごえメンバーみんなで曲と向き合えるといいな、と思います。一団員としても、執行代としても頑張ります! 原田…
15
December
2022
2022
【2022】よびごえ日誌 vol.11
こんにちは、お久しぶりです。2年A類の一柳です。今回の練習では、ソレラン(Soleram)の歌詞について深め、話し合う活動を行いました。
ソレランはインドネシア語の曲ですが、団員にはインドネシア語が分かる方がいらっしゃらないので、今シーズン全員まずは訳を書くところからのスタートとなりました。
感じたのは、言葉が分からないと、訳してみたところでそのニュアンスなどが分からなく、直接的な意味しか分からないことです。しかしさすが、そんな中でも想像力豊かな団員達からは様々な面白い歌詞解釈が出てきました。
最近は音とりとダンスに追われるに追われる日々だったので、久々の、よびごえらしさが存分に詰め込まれた活動だったような気もします。
“よびごえらしい”活動…そういえば、よびごえの理念とは、ただ合唱すること、合唱が上手くなることではなく、合唱と教育について考えることです。
ここから、非常に私的な事柄になってしまうのですが、私自身、最近合唱を教える、ということが全く分からなくなってしまって、あらためてそれについて考え直す日々でした。
合唱指導は、合唱を上手くするという明確な目的があります。しかし合唱を教えるというのは、合唱指導が全てなのか。もし合唱指導がすべてでないとしたら、合唱を教えるとはどのようなことなのか。もし合唱を通して教育に取り組むという視点で考えたら、何を目指すのか。合唱に取り組むことで、生徒達に何を得てもらいたいと考えるのか。
正解はないですが、とても大事な問だと思います。最近自分なりの答えが若干つかめたような気もしますが、それは今の自分にとってのもので、正解はないですし、今後も考え続けていきたいです。
あと春こんまで2か月、長いようであっという間なのだと思います。
このメンバーで過ごせる時間を大切にしていきたいです。
追伸:この日ではなくて次の日の稽古なのですが、三年生が披露してくださった歌があまりに素敵でした…!心温まる演奏をありがとうございました🌼 一柳…
03
November
2022
2022
【2022】よびごえ日誌 vol.10
A類4年の滝澤です。11月3日の稽古について振り返っていきます。
前回はCの音取りが中心でしたが、今回はSにも触れることができました。
Sは和声的な音楽のため、パート内でピッチを合わせるのに苦労しました。ソプラノ2は半音の動きが苦手ですね…部分練習を重ねるごとに合わせることが難しくなってしまい、最終的にはピッチが高いのか低いのか誰がどうずれているのかも分からない、という負の連鎖が起きてしまいました。ただ、ソプラノ2の楽譜だけを見ると「前の音より半音上がる」という指示のところが、半音上がった先の音がアルト1と長三度になっているので、音が半音上がるという意識よりもアルトを聴いて和音の中で調整しよう、という意見も出ました。自分のパートの音程にこだわるのも大事ですが、視野を広くもって、和音の中の自パートの立ち位置を考えながら歌うということも、今後の合わせ練習で意識していきたいと思います。
Sの動画をいくつか見てみているのですが、子どもが衣装を着て歌って踊っているものや、大人が踊っているもの(個人的には日本の民謡や音頭の踊り・またはフラダンスのように見える振り付けもありました)、合唱編曲などいろいろなパターンがありました。また、その動画たちの関係で、世界各国の子守歌にヒットして、様々な国の子守歌のフレーズを聴いてみていたら、際限がなく… どこの国にも基本的に子守歌は不可欠なんだなという浅い感想の段階ではありますが、面白かったのでぜひ皆さんも世界の子守歌を調べてみてください!
それから、子どもが歌っている動画をたくさん見ていたら、昨年度演奏した「マザー・グースの三つの歌」を思い出しました。今回のSは、直接子どもの声を意識した発声や発音はしないかもしれませんが、今年度も子どもの純粋さを思い浮かべつつ、それを何か表現できるような合唱にしていきたいです。
秋学期、皆さん忙殺されていることと思いますが、週に1度のよびごえ稽古、ぜひ楽しんでいきましょう~
次回の日誌は、4年堀切さんにお願いしています。よろしくお願いします♪ 滝澤…
20
October
2022
2022
【2022】よびごえ日誌 春こん、開始します。
みなさん、こんにちは。小田です。今日、いよいよ今年度の春こんの稽古を開始しました。
今日の稽古に向けて、会場をおさえたり、キーボードを運んだり、PCの準備をしてくださったり、本当にありがとうございます。
まずは、よびごえの稽古が感染拡大の場とならないよう、全員で注意を払いましょう。安全を確保し、安心できる場があってこそ合唱の活動を行うことができます。気になることや不安なことがあれば、誰かに相談することを忘れないでください。
ついに今日、自由曲が決まり、来週からどんどん譜読み・合わせを進めていきますが、今回の自由曲は、本当に悩みに悩みました。8月頭から悩みはじめ、ようやくこれでいこうと思えた曲に出会えたのは先週です。自由曲にするからには、その曲が本当に今のメンバーにとって良い学びに成り得るのか、その成立背景や楽譜を分析して、準備をしていました。
でも、今日、みなさんの顔を見て、良い曲を選ぶことができたと、この2か月が報われた思いです。選曲は本当に大切です。それは、これから皆さんと一緒に過ごす時間がどのようなものになるかを決めることに等しいからです。いま、よびごえメンバーと一緒に考えたい作品、そしてみなさんのもってる力が100%ではなく、120%発揮できる曲を探していました。
選曲の過程では、いろんな曲が頭をよぎりました。
せっかくなので、候補だった曲のうち、音源がオンラインにあるものについて紹介したいと思います。いろんな曲を知っておくのは悪いことではないので、もしよければみなさんも時間のある時に聴いてみてください。
“SUITE” de Lorca 全曲
作曲:E. Rautavaara
詩 :G. Lorca
以下の動画は混声版の演奏ですが、女声版も演奏される機会が多い作品です。女声版の楽譜の表紙には”児童合唱のための”と付されていますが、日本でいう、子どもたちのための作品のように希望に満ちた、明るいテーマというわけではなく、三善晃における児童合唱作品のように、この世界のリアルが真摯に描かれています。ここでは、いつでも”死”は私たちのことを見つめており、私たちの近くをうろうろしているということです。作曲者自身は「死と生の間に潜む、暗く、重苦しい内容を合唱作品として表現したかった」とのこと。言語は、スペイン語で歌唱されることが多いです。
「梟月図」より 青
作曲:鈴木輝昭
詩 :宗左近
2004年、僕が中学生のころのNコン高校の部の全国大会で安積黎明高等学校(福島)が自由曲として歌唱していた作品です。その時の衝撃がいまでも残っています。歌唱も大変に素晴らしかったのですが、「なんてすごい曲なんだ!!!」という作品に対する感動があり、鈴木輝昭を意識するようになったきっかけの曲のようにも思います。人の声が重なることで合唱になるわけですが、その重なり方によってこんなにも美しい空間ができるのかと、鈴木輝昭が楽譜の冒頭に書いてある「多層的に広がる色彩」の通り、まさに色が広がっているかのように僕には聴こえました。2群合唱による作品で、同時に女声12部で動く箇所があり、難曲と言えます。
【合唱】無伴奏同声合唱のための「梟月図」から 青
「日本の民謡 第2集」より 会津磐梯山
作曲:松下耕
詩 :伝承
8人のソリストに加えて、ソプラノ、メゾ、アルトという通常の女声合唱団が必要な作品です。よびごえのメンバーは全国各地から集まっていること、また現在、福島出身のメンバーがいることから、この曲も候補に考えていました。この曲は究極的な〈チームワーク〉が求められる作品に思います。8人のソリストは、十六分音符ずつずれながらロングトーンすることで、音による背景を空間につくっていきます。難しすぎる曲なのですが、国内でこの作品に挑戦する合唱団は少なくありません。
「風の馬」より 指の呪文
作曲:武満徹
あまりに選曲に悩み、この曲のことも真剣に考えていました。せっかく昨年度は「第1ヴォカリーズ」を取り扱ったので、「指の呪文」に挑戦できれば、なにかが解決するような気もしました。「第1ヴォカリーズ」のモティーフが「指の呪文」でも使用されていたりと、作品間の関連性はあるのですが、実態はまったく別の作品のように、個人的には捉えています。この作品を歌唱できる団体は、日本にはほとんど無いと思います(挑戦することは自由ですが・・・)。
「合唱のためのコンポジション 第7番」より マンモスの墓…
01
March
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(松本)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。25
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(一柳)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。15
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(堀切)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。15
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(原田)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(佐藤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(滝澤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(大瀧)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(小田)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(伊藤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 メッセージ(小金澤)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 春こん編 12/23の日誌と、本番前日に思うこと
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。13
February
2022
2022
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2022 金賞・1位, 東京都合唱連盟理事長賞
「ユースの部 女声」金賞・1位, 東京都合唱連盟理事長賞※感染症対策のため、マスクを着用して歌唱。
混声合唱のための『風の馬』「第1ヴォカリーズ」(武満徹作曲)
少年少女のための『マザー・グースの三つの歌』(Mother Goose詩/三善晃作曲)
「ひい ふう みい よ いつ」
「キルケニーの ねこ二ひき」
「もしうみがみんなひとつのうみだったら」
…
22
January
2022
2022
保護中: 【2021】よびごえ日誌 春こん編
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。25
November
2021
2021
【2021】よびごえ日誌 春こん編 vol.4
初めまして、こんにちは!今回の担当は、今年度から新たによびごえメンバーに加わりました、A類1年の一柳優里愛です。よろしくお願い致します…!さて、今回扱った曲は、春こん。に向けた2曲。武満徹「風の馬」より「第一ヴォカリーズ」、そしていつものマザーグースより3曲目「If all the seas were one sea,」です。ついに第一ヴォカリーズに取り組み始めました。
今日の稽古を楽しみにしつつも、少々恐れていたメンバーも多い様子。なぜか?日本一難しい合唱曲ともいわれるこの曲、なんと無調で、拍子も書いていないのです。おまけに6パートに分かれるため、1パートの人数も少なくなってしまいます。さすがのよびごえ団員でも、少し不安…。
そんな中始まった稽古。自分の歌っている音は、果たして合っているのか。調性がないことで和声が分からず、正解が見えません。…と、そこで発見が。こんなに複雑な音の重なりの中にも、実は和声がしっかり決まっている部分があったのです。不思議な音の絡まりの中に垣間見えるG-durやF-durの響き。最初は訳が分からない曲、と思ってしまいましたが、もしかしたら、ただ複雑なだけではないのかもしれない。少し、この曲を理解するための手掛かりとなるものが見えた気がしました。
マザーグースの3曲目では、楽譜にスラーが一つも書かれていないことに着目。歌の場合、楽譜に書かれているのは音符や記号だけではありません。歌詞、つまり言葉が書かれています。今回の曲の場合は言葉からフレーズを読み取ることができるため、わざわざスラーでフレーズを示す必要はなかったのです。マザーグースは、古くから口誦によって伝えられてきたイギリスの童謡で、言葉のリズムが印象的。スラーを書かなかったのは、その言葉のリズムを生かすための配慮なのでしょうか。
ずっと昔から人々に口ずさまれてきた、言葉ありきのマザーグースと、歌詞のない歌ヴォカリーズ。見方によっては対照的とも思える二つの作品を、一つのステージでどんな風に表現していくのか、今後の課題です。
ちなみに、余談ですが、ヴォカリーズが含まれる組曲の題名「風の馬」は、武満徹さんがこの曲をつくるにあたって触発された、チベットの仏教文化圏で行われる風習からきているもので、“ルンタ”と呼ばれる旗を指すそうです。ご興味あれば“ルンタ チベット”と調べてみてください。
早いもので、もう11月も終わってしまいますね。
最近は冷えますので、暖かくしてお過ごしください。
次回の日誌は同じく新メンバーの、稲村さんにお願いしました。お楽しみに! 一柳…
18
November
2021
2021
【2021】よびごえ日誌 春こん編 vol.3
はじめまして!A類音楽選修2年の原田綾乃です。夏からよびごえの活動に参加させていただいております。
初日誌、よろしくお願いします…!
まず発声練習では、ポジションが変わる音域をハミングで滑らかに歌う練習、「マリア」で母音間での響きを均す練習をしました。稽古でも小田さんから口腔内の体積、響かせる位置を意識するというお話があったので、滑らかな発音や響きを目指して練習したいと思いました。
春こん。に向けた4回目の稽古では、マザーグースの3曲目の音取りを終わらせたあと、3曲の合わせをしました。以下、稽古内容です。
○3曲目
・全員 p.14 2段目頭 F durきめる
・A1 p.16 2小節目 Eのピッチ
・A1.2 2段目最後の半音階正確に
○2曲目
・全員 p.8 thoughtの和声きめる
・全員 p.10 2小節目頭のbitの和声 S1ピッチ高め
・全員 p.12 半音階正確に
○1曲目(p.5)
・S2 Why did it〜 ピッチ安定させる
・A1.2 Because bit my finger so…
11
November
2021
2021
【2021】よびごえ日誌 春こん編 vol.2
こんにちは。2Aの大瀧夏未です。〈発声〉
前回の録音で“k”が聞こえにくかったということで、今日の発声練習には“k”の練習を取り入れてくださいました。kを発音するには意外とエネルギーがいるのだと思うと同時に、発声練習と曲の練習をつなげて考える重要性を再確認できました。
〈内容〉
マザーグース2曲目 最後まで音取り→合わせ
マザーグース3曲目 P16、3小節目まで音取り 発音練習
マザーグース1曲目 軽く通す
マザーグースの音取りがどんどん進んでいます。
○マザーグース2曲目
・全員(全体)i 母音がポイント のばすところチェック
明るく、しかし深くなく
・S2 A1,2(P11、1段目最後) Gきめる
・全員(P12、1段目最後)Instead of two cats ポイント
ねこは一ぴきになりたかったのに、二ひきともいなくなってしまう
・S2 A1,2(P12、2段目2拍目~)シ♭ドレ 聴きあって
○3曲目
・全員(P14、2段目2小節目)axes 八分音符にわける
・全員(p14、2段目~) 曲線よりもかために発音
○1曲目
・全員
rightのrの発音
私は今年の7月下旬によびごえに入りました。よびごえでの活動は、楽しく充実したものですが、なかでもいろいろな人の考え方に触れられるという点でとても貴重な時間だと感じています。実際に教員になったら音楽の先生はだいたい学校に一人だと思うので、今の活動を通していろいろな視点を吸収したいと思っています。
そして、春こん。受験を乗り越え、ゆっくりめに上京して、合唱団に入って、私にとって久しぶりの本番です!予想以上に音を取るのが難しく、自分の音の居場所を見つけるのもとても難しいです。今はまだ音程か発音のどちらかだけに集中してしまいます。しかし、小田さんがハーモニーを伝えてくださったり、同じパートの奏有美さんが母音の規則性を教えて下さったりして、少しずつ輪郭が見えてきた部分もあります。少しのことで歌いやすくなるところがたくさんあります。初めはこんな難しい曲を歌うのか!と驚きましたが、木曜日の稽古に集中して取り組めるように、よくさらっておきたいと思います。健康に気を付けながら頑張ります。
これからよろしくお願いいたします。…
04
November
2021
2021
【2021】よびごえ日誌 春こん編 vol.1
こんにちは!A類音楽選修3年の伊野綾那です。
今日は、春こん。に向けた2回目の練習を行いました。
音とりを進めつつ、英語の発音を確認し、子音を意識して練習していきました。
以下、活動・稽古内容の詳細です。
〈活動内容〉
・第一ヴォカリーズ パート決め
・マザーグース1曲目 復習
・マザーグース2曲目 9ページまで音取り
〈稽古内容〉
○1曲目
・全員 p.7 on the right の前でブレス
・全員 Es-dur の和音決める
・ソプ fffの和音ソプ2のesから5度と4度決める
○2曲目
・全員 語尾の「t」鋭く!!きびしく!!(cat,fit,fought,bit,weren’t )
・全員 ma-ny母音変わってもピッチ変えない
・全員 最初はストーリーを考えて
・全員 最初とバトルシーンとのメリハリ
・ソプ1 fought and fit and下の段、アクセントの度にクレッシェンド…
27
February
2021
2021
【2020】よびごえ日誌 本番後の振り返り編(森本)
会場での練習なしで客席から舞台に出るというのが新鮮で、客席に出た瞬間に緊張が押し寄せてきて少し大変でした。段々とこの舞台の空気感に慣れ、歌うことの楽しみを感じながら歌えました。気持ちが最初から作れなかったのが悔しいですが、このような状況下のなかでも本番を迎えられて本当に良かったです。そして卒団の時を迎えました。本番終了後のミーティングでも話しましたが、短い間の所属だったもののよびごえで本当に濃い経験ができました。私は作曲専攻ですが、よびごえで、実際に音楽を演奏する活動でなければ経験できない、音楽を形作ること、音楽を伝えること、音楽を共有することについて、よびごえならではの濃さをもって、沢山経験できました。そしてそれらは私の創作活動に良い影響をもたらしています。おそらく、それが、惜しくも演奏されることはなかった、よびごえの新歓コンサートのために作曲した女声合唱にも現れていたかと思います。よびごえの活動なしではこの曲は生まれていませんでした。
私は今後大学院で作曲を続けますが、このように、これからも、音楽に向き合ったり音楽と仲良くしようとしたり、または時には違う視点をも持ったりして様々な経験をし、そんな自分だから作れる新しい音楽を生み出していきたいと強く思います。また、教育(人に音楽を言葉などで伝えたり教えたり、その音楽の良さを発信することも含み)にも興味があるので、その点もよびごえでの経験をいかして引き続き探究していきたいと思います。
今までありがとうございました。 森本…
23
February
2021
2021
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2021 銀賞
「一般の部 クラシック・現代音楽部門 指揮あり」銀賞※感染症対策のため、マスクを着用して歌唱。
「Ave Maris Stella」(R. Dubra作曲)
「前へ」(佐藤賢太郎作詩/作曲)
~Message from R. Dubra~
[…]the performance of her(Ms. Kunimoto) choir is very good. If it’s about music, musicality, emotions and similar most important musical things – all is performed…
18
February
2021
2021
保護中: 【2020】よびごえ日誌
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。18
February
2021
2021
【2020】よびごえ日誌 番外編
みなさん、こんにちは。小田です。まもなく、初めてだらけの2020年度が終わりを迎えます。
この1年、例年とは異なる角度からも合唱について考える機会を得ることができた点では、良かったこともあったと言えるかもしれませんが、一方でみなさんにはたくさんの我慢をしていただいたこと、それでもよびごえのために様々なご協力をいただいたことに心から感謝をしています。
この1年の締めくくりとして、それぞれ目標をもって、現メンバーでの残された時間を悔いなく過ごしてほしいと思います。
遅くなりましたが、これまでお寄せいただいていた「よびごえ日誌」を一気に公開しました。
また、みなさんで一緒に決めたパスワードを付した記事もあります。
よびごえ日誌は、通常、年度ごとに通し番号を付していますが、
もしかすると、担当になったけれどもまだ提出できていない方もいるかと思いましたので、
最後の最後に通し番号を付そうと思います。
今年度は、本当に様々な負担がみなさんにあったと思いますので、
「担当だったのによびごえ日誌が書けてない!」という方も、焦らず、完成したら小田までお送りください。
お送りいただけたら、随時公開していきます。
(担当が割り当てられていない箇所は、なるべく小田が記録用に書き起こすようにします。すみません。)
それでは今年度もあと少し、とにかく悔いのないようにお過ごしください。 小田…
21
January
2021
2021
保護中: 【2020】よびごえ日誌
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。14
January
2021
2021
保護中: 【2020】よびごえ日誌
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。11
January
2021
2021
保護中: 【2020】よびごえ日誌
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。24
December
2020
2020
【2020】よびごえ日誌
こんにちは、今回の担当は3年中島菜々子です。年内最後の練習です。全体での発声練習では、特に「ポイントの当て方」を意識して練習をしました。パートを交互に配置してお互いの声を聴きながら歌ったり、高音を出す際に息を止めないようにするなどについても意識して歌いました。また、高音をppで出す、というのは、自分で発声練習する際もあまり取り入れたことがなかったので、ぜひ試してみたいと思いました。
今回の「前へ」の練習では、詩の解釈、およびその表現方法について重点的に取り組みました。
この詩の中で何度も登場している「あなた」とは一体何を指しているのかといった歌詞の解釈から、「どうしてここに空白があるのか」といったように詩の書き方に込められた意図といった部分まで、細かく検討を行いました。また、解釈をしたらそれだけで終わるのではなく、技術的として還元する、といった点についても考えましたが、意外とこの実践が難しいということに改めて気づかされました。個人的に未だ解決できていないのは、「あなたと共に歌ったことを」の「共に」の表現方法です。この「共に」は特に大事に歌いたい、というような認識は共通していますが、ではそれを具体的に、技術的にどう工夫すればよいのか、ということがまだはっきりせず、言語化もできず、という状態で終わってしましました。他パートとの兼ね合いにも目を向けながら、引き続き検討していきたいと思っています。
今回は、パートごとに話し合い、どの部分をどのように工夫するか考える時間が複数回ありました。同じパートで実際に歌っているからこそ共感できる点も多々あり、意見を出し合って自分たちで工夫することで、「自分たちでつくっていく」という意識をより強く持つことができたと感じました。この場面で、私が特に興味深いと感じたのは、パートでの打ち合わせの後、まだ「具体的な方法」を引き出せていない状態でも、何らかの変化が生まれた、ということです。これはアルトパートで起こっていたことですが、パート内で話し合って、認識を共有しあったことで、無意識的にかもしれませんが歌声に変化が現れることもあるのだ、と知りました。また、こういった状態のとき、この時に限らず再現できるよう、どうして今うまくいったのか、と分析を行うことも重要だと感じました。
今回は特に詩の解釈・表現を重視した練習になりましたが、まだまだこの詩には多くのことが隠されていると思います。何度も細かいところまでこの詩を読み返して、たくさんの「なぜ?」を自分でも見つけていきたいです。
次回は、1年生の藤原くんに担当していただきます。フレッシュな視点を楽しみにしております。 中島
…
17
December
2020
2020
【2020】よびごえ日誌
この日は、春こんの練習を始めて、3回目の稽古でした。発声練習では、息を吸うときの体の状態(①鼻をどう通るか 広い状態・狭い状態 ②その息がどこへいくか 背中側・お腹側)や、言語が求めている響きの位置があること、そのための練習の仕方を学習しました。息が鼻腔を通りながら、同時にハミングで音を出すということをしました。
Ave maris stellaでは、パート間の音程やブレスの位置、それに伴う息の使い方、ポイントが当たっている声であるかということを確認後、この曲の詩について、韻律の話がありました。12音節詩行であるというまとまりや、詩のリズム・意味から来るうねりがあること、そして私たちが分かっていることをどのようにしたら音楽で伝えることができるか、という問いが提示されました。また、そのうねりは3つのパートで時間軸が異なる部分と、tuttiで同じ波をつくる部分があること、aveという言葉から想起されるもの、韻をふんでいること等についても言及がありました。
前へでは、音程や開離に伴う歌い方等基本を確認しつつ、少しずつ曲の内面、表現に入っていきました。主旋律のエネルギーを他のパートに示し全体で共有していくこと、掛け合いや感嘆符をどう表現するか、どれくらいの決然さかなど、構成を考えた計画的かつ意志がある音の使い方を考えるためのヒントがありました。個人的に、「時間をかけてあたためるべきは、この曲のどれぐらい深いところにずっといられるか」という言葉が印象に残りました。
振り返りとしては以上です。話は変わりますが、最近、「炎」(Lisa)と「前へ」がどことなく似ているなと感じました。私は流行に乗り遅れて鬼滅の刃は見ておらず、曲の背景にあるものは分からないですが、なんとなく思いました。一人で歌う・複数人で歌う、曲が世に出た目的など違いは多くありますが、(だからこそ、)未来を考える想いや喪失の悲しみへのエネルギーを考えるヒントをもらえるような気がします。 佐藤
…
10
December
2020
2020
【2020】よびごえ日誌
皆さんこんにちは。A類音楽3年の伊藤真緒が担当します。約5か月ぶりのよびごえ日誌です!
よびごえは長らくオンラインのみで活動を行っていたのですが、遂に12月から対面での練習が再開されました。感染への不安はまだまだ続く状況ですが、各自対策に取り組みながら春こんに向けて頑張りたいと思います。
ではさっそく、2回目の稽古の内容を書き留めていきます。
◆発声練習
オープニングは、発声練習から始まります。私は、自分以外の人と歌うという機会がよびごえにしかないので、1番声だけに集中できるこの時間はとても貴重です。
最近の発声練習でよく指摘されるポイントとして、「高さが変わっても母音のポジションを変えないこと」「音が高くなるほど息のスピードは速くなる」の2つが挙がります。歌や合唱を練習するときに考えることは沢山ありますが、他のことは一旦無視して1つのことのみに意識を集中する練習も有効な方法だと思いました。ある程度の時間強く意識して行うと、その後に別のことをやっていてもさっきのことは無意識にできるようになっているらしいです。確かに!今日も発声で集中してできたことは、曲中でも自然にできていたと思います。次の練習でも同じことをできるようにしたいですね。
◆1曲目「Ave maris stella」DUBRA,Rihards作曲
春こんで歌う1曲目です。今日は通しで歌うところまでいき、曲の全体像を捉えることができました。和音が決まらないと話にならないこの曲、そこが難しくも面白いところかなと感じています。私は特に、随所で発揮される7度のエネルギーをぶつけるところが良いなぁと思いました。アルトは人数が多いのに何故かブレスの場所が被るという以心伝心っぷりで、カンニングブレスを毎回相談し直しています(小声)。
換気ついでに、小田さんがキリスト教についてお話して下さいました。というのも、よびごえで宗教曲を扱うのは初めて(?)で、基本的な知識がほとんど無い!(多分私が知らないだけかもしれない。)
Ave maris stellaで称える聖母マリアは人間のカーストでいうトップで、もうめちゃくちゃに手の届かない存在であるという話、人は死んだら天国・煉獄・地獄にいく話、地獄にも階層(第9圏が最も極悪)がある話など、本当に入り口のところを学びました。第9圏にいくような人はどんなことをしたのか気になりますね。練習が終わった後に、団員数名でダンテの『神曲』をパラパラーっと見ましたが、「積読になりそうだ」という話になりました。
キリスト教について新しいことを吸収しても、そこで終わりにせず、音楽につなげるということを忘れずにいたいです。
◆2曲目「前へ」佐藤賢太郎 作曲
春こんで歌う2曲目です。
このよびごえ日誌を書きながら録音を聴いていますが、客観的に聴くことで課題をより明確に突きつけられている気がします。今日重点的に練習した跳躍の部分もそうですが、シンプルそうで難しい。いやシンプルだから難しい(?)。
知名度も高く、コンクールでやるのはなかなか厳しいと分かっていながらも挑戦するこの曲。ありきたりな言葉だけれど、やっぱり、聴いてる人の心に響くような音楽に仕上げたいです。といってもまだまだ土台が(;_;)まずは今年中に和音やバランスを文句なしと言われるまで持っていきたいです。
練習後には、恒例になりつつある写真撮影をしました。
この日は12月10日世界人権デーだったので、「LOVE&PEACE・・・♡」ハートに見えますか??
寒い日が続きますが、皆様お体にお気をつけくださいませ。
次回の日誌は、同期の佐藤さんです。よろしくお願いします! 伊藤…
01
March
2020
2020
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2020 銀賞
「一般の部 クラシック・現代音楽部門 指揮あり」銀賞(金賞該当なし)混声合唱『風紋』より「風紋」(岩谷時子作詩/石井歓作曲)
「BIN-NAM-MA」(A. Grau作曲)
~Message from A. Grau~
I very liked the recording and am very Happy with his interpretation.
I also liked It. The color of the voices, the progressive accellerando. Good work!
…
24
February
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.036
お久しぶりです、2年アルトの中島菜々子です。今回の練習は、いつもの大学ではなく、とある公民館の一室をお借りし、あたたかなお日様の光に照らされながら、遂に一週間後に迫ったコンクールに向け最終調整を行いました。
発声練習では、「ko」で歌う練習や、ハミングを用いた練習を行いました。前回の練習でも指摘があった、速いテンポ下での母音の響かせ方を意識することができました。今回の2曲はどちらも比較的テンポが速い部分があるので、緊張などでいつも通りにいくか分からない本番でも確実にできるよう、常に意識していきたいと思います。
風紋の練習では、曲中の強弱を、より明確に聴いている人に伝わるよう工夫しました。また、曲の冒頭から、集まった声で歌いだせるように、息の吸い方、頭の空間の使い方、ポジションなどのポイントをおさえながら、練習しました。今回の曲は勿論のこと、他のあらゆる場面でも応用できるよう、もっと追究していきたいと思います。
今回は、本番と同じ衣装、靴を身に付けての練習だったため、BIN-NA-MAの練習では、足踏みの音などにも注目しました。また、部分で取り出して、より細かく曲をつくりました。また、皆からも気になる点などを出し合い、それぞれが納得して歌うことができました。
ついに、コンクールまで一週間を切りました。それぞれができることをやりつくして、いい演奏ができるよう、より集中して練習に取り組んでいきたいと思います。
次回のよびごえ日誌は、同じくアルトパートの1年生・谷 夏七星さんにお願いしたいと思います! 中島…
20
February
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.035
本日のよびごえ日誌は、A類2年アルトパートの伊藤が担当します!寒さの中にも春の足音が聞こえてくる今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。よびごえが出場する春コンもいよいよ来週と迫っており、団員一同日々の練習に励んでいます。まず初めに、発声練習です。今日は時間が無かったのですが、「腕を上下させジャンプしながら『どんぐりころころ』を歌う」というものを佐藤さんが提案してくれました。佐藤さんが小学生の時に「心拍数を一回高いところまで上げると、次にもう一度その心拍数になった時に慣れてキツくない」という話を聞いたらしく、みんなでヒーヒー言いながら「どんぐりころころ」を歌いました。私たちが春コンで歌う「風紋」も「ビンナマ」もそれぞれパワーが必要なので、体力も肺活量もすごく大事です!!
さて、本番も近づく今日の練習テーマは、暗譜☆と細かい部分の修正でした。毎回と言っていいほど“暗譜”という敵が纏わりつきます。今回特に「ビンナマ」では動きも入るため、非常に焦っていました。しかし、練習の前にアンプ会をしたり、暇な時にブツブツ唱えたりしていると、自然と覚えるようになっていました。何回も繰り返してとにかく体に染み込ませる人、規則性を見出して論理的に覚える人、楽譜自体をスクリーンショットのように記憶できる人、暗譜の仕方は人それぞれのようです。
暗譜をしながら思ったことは、未だにアクセントの位置が曖昧であるということです。Bin-nam-maではbinに>がつくところもあれば、namについたり、maについたりします。楽譜を外して歌うとあまり意識せず歌っていたなと気づきました。また、他パートが主旋律の時はそれを意識しているけれど、それ以外の時に他パートが何をやっているか気に留めていなかったなと思いました。二曲目は立ち位置がソプラノの隣なので、もし暗譜が飛んだりしても混乱しないように、普段から自分以外に耳を傾ける余裕も大切にします。
また、「風紋」でも「ビンナマ」でも子音が多いところで声が前のほうに出てきてしまうので、それを修正しました。摩擦音を出すために狭くした口を一瞬で開けるのを、無意識でやるのは難しいです。しっかり開ける、顎を下げる、と考えながら歌うことが必要です。詰めの時期になっても、発声や体の使い方は絶対に基本となるので、時々確認する機会は大事にしたいです。
写真は練習後のミーティングの様子です!
春コンまで残りわずかですが、限られた時間を有効に、よびごえらしく、楽しく、最後まで磨いていきます。
P.S.出番は3/1(日)浜離宮朝日ホール11:08頃の予定です。私たちの合唱を、ぜひ多くの人に聴いて頂けると嬉しいです(*^^*)!!!
次回のよびごえ日誌は、は私と同じ二年生でアルトパートの中島さんにお願いしたいと思います!♡ 伊藤…
13
February
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.034
こんにちは!1年ソプラノパートの伊野綾那です。今日は秋学期の授業最終日。ようやく春休み突入ということで、大学がいつもより静かな気がしました。しかし、練習室のある音楽棟4階はいつもと変わらず、活気に溢れていました!それもそのはず、試験が終われば次の曲が待っていますからね!今、私も新しい曲の譜読みに取り掛かっているところです。休みだからといって気を抜かず、こつこつ練習していきたいと思います。
さて、今回の練習はかのんさんが発声練習を担当して下さいました。最初の体ほぐしでは、前屈をした状態で脚の後ろ側全体を伸ばしたり、しばらく小刻みに揺れて脱力してから止まり、体の軸を感じたりしました。止まった時に何とも言えないふらふら感があり、体が安定する場所を自然に見つけていく感覚を味わうことができました。次に、風紋を意識したクレッシェンド、デクレッシェンドの練習をしました。強弱の幅を全体で統一するため、隣の人の声に耳を傾けながら歌ってみると、自分は思ったより声を押しすぎていて、発声が乱れていることに気づきました。今度は先程とは逆に、デクレッシェンド、クレッシェンドの順での練習です。これは思ったより難しく、多くの人が苦戦しているようでした。音が3度上がったときに弱くなっても、声に芯を残し、かつ強弱の差もしっかり出す、というのが難点でした。しかし、このような地道な練習の積み重ねが、曲の中で使える表現を増やす近道なのかもしれません。
今回の稽古は、細かい確認をしてから通しを行いました。風紋では、ソプラノとアルトの4度、5度、8度の響きを決めるということに焦点を当てていきました。冒頭の女声はユニゾンから始まり、ソプラノの音が高くなることで偶数小節が3度、4度、5度と徐々に音程が広くなっていきます。ただ音楽の流れにのって音程に関して無意識で歌っていては、4度と5度はなかなか決まりません。そこで、音が高くなるにつれて息のスピードを速くし、発した瞬間に音を当てる練習をしました。その際、「来る」「貝」のKの子音で息が遮断してしまうが流れを止めないこと、ポジションは後ろ、息の量は少なく一点に集中させることが課題となりました。テンポが速い曲の中でも音を確実に当てることができるよう、体の準備の仕方、タイミングなどを染みこませていきたいです。
BIN-NAM-MAは、表現一つ一つの違いを明確に、そしてよりシャープな音をつくる、というのが今回のテーマでした。テノールとバスがずれてクレッシェンド、デクレッシェンドする複雑性、クレッシェンドしては音量をがっと落としてまたクレッシェンドする再現性など、この曲には恐怖や不気味さを感じさせる細かい表現がぎっしりと詰まっています。お客さんに気持ち悪いと感じて(楽しんで)もらうためには、その一つ一つを極端に明確に表現しなければなりません。そして、子音の入れ方、ロングトーン、体を叩く音、地面を踏み鳴らす音すらもシャープな音を目指します。いつもはホールの響きが私たちを助けてくれますが、今回ばかりは、シャープな私たちの表現を邪魔してきそうです。柔らかい響きに飲み込まれない鋭さを、これからもっと突き詰めていきます。
お客さんの目にBIN-NAM-MAがどう映るか気になるところですが、忘れてはいけないのがインディアンとベネズエラの大洪水で犠牲になられた方々の目です。自分の肉体と痛みを捧げ、自然の平安を願ったインディアンのダンス。災害の絶望から立ち直っていく人々の姿。思いを馳せるにはあまりにも遠い存在ではありますが、この曲を通して知ることのできた人々の心情を少しでも体恤し、音楽を作り上げていきたいです。
少々重くなってしまいました。最後は井出さんを明るく送り出して締めましょう!
教育実習頑張ってください!私たちも、本番までまだまだグレードアップしていきます!
伊野…
10
February
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.033
こんにちは、3年の國元美乃里です。秋学期は今週で終了ということで、テストや試験が佳境を迎えており、学芸大学は非常に盛り上がっております。と同時に3年生の名乗ることができるのも残りわずかとなり、ついこの前大学に入ったばかりなのになあと、時の流れの速さに驚いております。練習は、ななせちゃんの発声から始まります。ハミングで8拍間、2拍ずつのクレッシェンドデクレッシェンドを繰り返します。最初はどのくらいの音量で、最高音量はどの程度で、と計画的にやらないと、2拍はあっという間に流れてしまいます。次は、『カケキコクコキケカケキコク』(あってる?)を音階で歌っていきます。カ行は意識して発音しないとうまく当たらなかったり、母音の違いで響きの違いも分かりやすいため、合わせるのがとても難しいです。今回の発声メニューは初めて取り組むものも多く、きっとななせちゃんが、どうやったら風紋やビンナマにつなげられるのかと試行錯誤を重ねて、毎週持ってきてくれているのだと思います。ありがとうございます。
頭を使って机やいすをコンパクトに並べ替え、できる限り本番のステージの広さを確保します。いつも通り、まず初めは風紋の通しから始まります。私たちの強みは何と言ってもこの人数。しかもそのほとんどが、声を出すことをお得意とする声楽専攻で、他団体に負けない音量を出すことができます。その強みを生かし、風紋ではビル風のような、強烈で圧倒的な風を吹かせ、それに匹敵する大きな愛を表現したいと思います。
この練習の前に何人かでビンナマの暗譜稽古を行ったのですが、同じような音形、同じような言葉が繰り返され、微妙に変化していくこの曲を暗譜するには、規則性を見出すことが一番の近道であると感じました。中学の頃から、テストに出る何の関連性もない用語たちを、勝手に意味づけして記憶していくことが得意だった私(テストは全部それで乗り切っていた)。とっとと暗譜するんだ!!!ということで、話がずれましたが、ビンナマではまず、Pの表現の仕方を考えます。ただ小さい音で歌えばいいという話ではありません。音色を柔らかくする、その前の音を強く固く歌い相対的にPに聞こえさせる、息を混ぜる、など音量以外のアプローチはいろいろ考えられます。次に課題にあがったのが、M⤴の歌い方です。この場面では不満を表現したいのですが、言葉ではないこの音でこの世界の異質さを表現しなければなりません。いまはまだ、個人個人のイメージや方法が統一できておらず、まとまっていない状態なので、早急な課題として取り組んでいきたいと思います。ビンナマは何となく、歌っているときの頭の中や声はそれっぽくなってきたのですが、身体が追い付いていないという感じがしています。身体は意識しないと動きません。どこかに冷静な視点はもちつつ、呪術的かつ神秘的かつ幻想的な踊りで観客の皆さんを感動させることができたらと思います。
つぎの日誌は同じソプラノパート1年生のやあなちゃんにお願いしたいと思います。とっとと暗譜します!!!
國元…
06
February
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.032
こんにちは。3年の井出です。2月前半のぽかぽか陽気から一転、急に寒くなりました。私は大学1年のときから早朝バイトを続けていますが、毎年この冬の時期の早朝は、手が凍るほど寒いです(そしてなかなか起きれない!)。
今日は、花音さんの発声練習、と思いきや、いきなり「どんぐりころころ」を歌いました。
しかも隣の人の肩をたたきながら。体だけでなく、その場の空気もほぐれました。そういえば昨日、「春こん。」の中学校・高等学校の部のお手伝いをしてきました。終演まで舞台袖にいたのですが、約8割(!)の団体が、演奏前に肩たたきをしていました。どこかの本にでも書いてあるのかしら、と思ったほどでした。また、学校・団体によって本番前の空気は様々です。生徒全員と握手をする先生、ギリギリまで生徒と演奏の確認をする先生、生徒とは話さず楽譜や指揮の確認を黙々と続ける先生など、様々でした(どれがよい、というわけではありません)。一つ言えることは、その空気は先生次第なのかな、ということです。部活動の指導方針でもあるのかもしれませんが、先生によって育つ子どもは全然違うのだなあ、と。言葉では分かっていましたが、実際に間近で見てヒシヒシと感じました。
さて、話が逸れました。今日の練習では、はじめに「風紋」を扱いました。通しの録音をし、その録音を聞き、改善点を出し合いました。課題はまだまだたくさんですが、一つひとつ解決をしていきたいですね。言われたことを何個も一度にやろうとすると、かえって上手くいきませんでした。
後半は「BIN-NAM-MA」です。本番の並びを確認し、また演奏も形になってきたと感じています。楽譜に書かれている演奏記号を中心に、細かく確認を行いました。楽譜を読み込んでいる、と思っていても、見落としている記号があるものです。形になってきたのは、そのような細かい作業を繰り返した結果なのかな、と思います。終わりのミーティングでも、「やっと曲を掴めた」との声が多数。暗譜も含め、今後も頑張りましょう!
そしてもう一つ。今日の練習から、ベースに助っ人が来てくれています。バリトンパートをお願いしましたが、彼が入ったことで一段と音の鳴りが豊かになりました。練習も違った視点で見てくれているようで、よびごえに新しい風を吹き込んでくれそうです。これからもよろしくお願いしますね。
次回は同学年の國元さんにお願いしようと思います。 井出…
03
February
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.031
こんにちは。佐藤花音です。寒いですね。中学、高校、大学受験シーズンですね。受験生が落ちついて力を出しきれることを心から祈っています。
大学内も試験、試験、試験と毎日追われています…がんばります…
今日は発声の時にテヌートとアクセントの歌い分けについて考えました。二人組で行い、片方の人が歌った後2人で振り返りをします。発声を進めてくれたななせさんの指示で、まず歌い終わった人が、違いを表現するために変えたことを言った後に、聞いていた人が感じたことを言いました。ただ聞いていた人が感じたことを言うだけよりも、まず歌った人が振り返ることから始める方が、深く考えられるなぁ、と思いました。表現について、意見を聞くというより、自分の感覚や判断基準について、意見を聞く感じになるからかなと思います。先日教育法の授業でこれに関連する内容を聞いたのを思い出しました。授業で学んだことを実践の中で捉え直すことで学びが深まるのは楽しいです。
風紋は今まで部分部分で練習していたところのつなぎを確認し、その後に通しました。その際録音をして改善点を出しました。子音のタイミングや強さ、フレーズの終わり、リズムの出し方などについて言及があり、それらについて確認した後に、もう一度通しました。
風紋は息継ぎのタイミングが難しいのもあり後半になるとだんだん疲れてきます。疲れてきたときに自分の歌い方がどう変化するか知り、計算して歌うよう、また、一度に全部はできなくていいから1つずつうまくなっていってと、お話がありました。
ビンナマはいままでよりも細かく表現の仕方について練習しました。強弱、動き、アクセント、スタッカート、テヌート、どんな声質で歌うか、などの点について、数小節ずつ丁寧につくっていきました。考えることが盛りだくさんで、練習時間があっというまに過ぎていきます。野性的・非日常的な表現をめざす部分がありますが、このような世界観の曲は今まであまり出会ったことがなくて新鮮です!最後に前半と後半に分けて、通しました。分けてであっても、通したのは今日が初めてでした。通してみて改めて感じたのは、場面の変化・音楽の変化がめまぐるしい曲だということです。気持ちと思考と感覚がきちんと伴っていけるよう、1つずつ頭と体に浸透させていきたいです。
次回は井出さんにお願いします! 佐藤…
16
January
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.030
こんにちは!今回のよびごえ日誌はA類1年アルトパートの堀切彩愛が担当します。今日の練習はまずストレッチから始まりました。1人で首回し等をした後、2人組で背中合わせになって、手首を持って前に倒れて引っ張り合うストレッチをしました。普段あまり伸ばせないところも伸ばせた感じがしてとても気持ち良よく、組体操みたいで楽しかったです!
その後に発声練習をしました。ドレミレドの音形で、ハミングやka,ア母音で最初だけkの子音を付ける等段階を追って練習しました。今回の練習では、「空間で音をまとめるとはどんなことか」をテーマに、指揮者がいるあたりに声を集めるポイントを設定したり、空間全体を意識したりしながら、息のスピードや子音にかける時間を調整しました。本番のホールでの聞こえ方を意識しながら練習することが大切だと感じました。
今日の稽古では、BIN-NAM-MAをメインに練習しました。パート内や全体で決めておくべき約束事を話し合って解決していきます。1つ目に話し合ったのは、アルトに出てくるウィスパーボイスでのテヌートの付け方です。滑らかなクレッシェンドディクレッシェンドではなく、テヌートの部分で止まった時間を作る,gの子音を長めにとる等の結論になりました。次はソプラノのウィスパーボイスの部分で、楽譜の表記が3度高くなっている箇所をどう表現するかということです。音の高さは喉を締めることで表現できるという結論になりました。次に、途中に出てくる体全体を使ったリズムパターンをどう表現するかという話し合いになり、何かしらの動作を楽譜通りすることは決まりましたが、細かいことは保留になりました。またHに出てくる矢印付きのOMは有声にすることを確認しました。さらに、バツ印の付いたmaはかわいく唇の破裂音が聞こえるような歌い方にすることも確認しました。その後、楽譜の細かい所を確認していきます。「不満げに」という指示をどう技術的に還元していくのか個人で試してみたり、テヌートや細かいクレッシェンド,ディクレッシェンドを的確に表現できるよう練習したりしました。P.9にあるクレッシェンドからのフォルテ、その後のスビトピアノの流れについては特に重要で何度も練習しました。私は今までこの曲の振りや音を一通り通り歌うことに気を取られ、細かい所にまで目を向けられていなかったことをとても反省した稽古だったのですが、細かい表現は全員で共有して的確に表現していけると良いなと思いました。
最後に小田さんからの宿題として、今は日本人っぽく歌いすぎているので、舌根を落としたようなkumの言い方と南米の人の感情表現,南米についてを各自研究しようということになりました。本番までもうあまり時間が無いので、自分でも曲の理解をどんどん深めていきたいと思います。
次回のよびごえ日誌は谷さんにお願いしたいと思います!
成人された先輩方、おめでとうございます! 堀切…
06
January
2020
2020
【2019】よびごえ日誌 vol.029
明けましておめでとうございます。今回のよびごえ日誌はアルトパート1年の今城琴美が担当致します。
今日はストレッチから練習がスタートしました。
後ろに伸びたり、上に伸びたり…思ったより肩が凝っていてびっくり!全然腕が後ろにいきませんでした笑
そのあと2人組でのストレッチ。
1人は脱力して前屈して、もう1人がその人の背中を叩きます。前屈をしている人は背骨を1つずつ積み重ねるイメージでゆっくりと起き上がります。
その後の発声練習は、ソーーーファミレドーというように5度下降する音形で行いました。
高い音からスタートする発声は、思ったより高めを狙って歌い始めないとぶら下がりがちになります。しかし、アタックが強すぎると発音がきつくなるのでそれも注意しなければなりません。下降するにつれポジションが変わらないように気をつけるというのも課題となりました。
その後、BIN-NAM-MAでも出てくる、グリッサンドの練習も行いました。
1曲目は風紋の練習から!
まずは正確な音程、リズム、発音で歌唱できるかの確認です。
少しテンポを落として、器楽的にきっちりとダイナミクスの変化を表現することに意識して歌いました。
そして、今日は細かく楽曲分析をしていきました。
まず1つ目のポイントは『リズム』です。この楽曲は全体を通して大きく2つのリズムパターンに大別できます。それに注目して、楽譜にマーキングをしながら皆で確認しました。
まず、第1主題は2小節目の頭に向かった音形、つまり、フレーズの頂点に向かう過程が表現される音形です。クレシェンド、デクレシェンドをしっかり表現することが重要となってきます。
それとは対照的に、第2主題は裏拍の動き、つまり、いきなり始まります。これが第1主題との決定的な違いです。ファンファーレ的に、発音をしっかりと入ることでリズムの違いを浮き彫りにできます。
次に、2つ目のポイントは『歌詞』です。
私たちが今回歌う「風紋」は、風紋という楽曲の第四章です。私たちが実際は取り扱わない、第一章から第三章も含め、歌詞の意味を丁寧にみていきました。
第一章「風と砂丘」は、風でもなく砂丘でもなく第三者の視点から描かれています。第二章「あなたは風」はタイトルからも読み取れるように、“私”が砂丘であり、風である“あなた”へのメッセージとなっています。
そして第三章「おやすみ砂丘」は第二章と立場が逆転し、風から砂丘へのメッセージとなっています。
それでは第四楽章「風紋」は一体どの視点から描かれているのでしょうか?
これは砂丘で風の言葉を目にして想像を膨らました人間の視点なのではないかという意見などが出ました。
また、第三章の最後には「人は呼ぶ 風紋」という歌詞があります。人間はどんな現象にも名前をつけようとします。これは私たちにとってしか意味をなしません。自然は人間が及ばない神秘の世界の中のもので、風の言葉を風紋と言う言葉では認識していないのです。
そして、3つ目のポイントは『音楽と詩の関係』です。
私たちは日常的に、バーバル言語とノンバーバル言語を使っています。
バーバル言語とは、ある程度の人が何を指しているのか特定出来るものです。たとえば、ペットボトルという言葉などが例に挙げられます。詩、つまり言葉は具体的なイメージを共有するのにとても便利なのです。
一方、ノンバーバル言語は、指すものが統一されません。音楽など、個人によって感じることが違う、抽象的なもののことです。つまり音楽では、必ずしも同じ結果を共有することが出来るとは限りません。
歌というのは、詩というバーバル言語、音楽というノンバーバル言語、この2つが組み合わされたものです。
では風紋を歌う上でその2つを上手く表現するためにはどうすれば良いのでしょうか?
詩に寄り添えばいい演奏ができる合唱曲が近年多い中、この風紋は現代曲に近い形式であり、音楽が要求する合唱曲といえます。…
16
December
2019
2019
【2019】よびごえ日誌 vol.028
Merry Christmas!!はじめまして。本⽇の⽇誌は、4年声楽専攻テノールパートの濱野瑞貴が担当します。
まず、今回の練習では、発声練習を⼆年⽣の花⾳さんが仕切ってくれました。”ieieioiou”といった⺟⾳唱を⽤いて、いくつかのアイデアを試しました。たとえば、、全員で⼀緒に歌う以外にも、2パートにわかれて輪唱のように追いかけっこをして、先に歌い出したパートの歌い⽅を後を追いかけるパートが真似をして練習しました。その後、パートを交代して歌ったり、もう⼀度全員同じタイミングで歌ったりしながら、⾳を揃えていきました。私のひとまずの感想は「カエルの歌みたいで楽しかった」です。笑もちろん楽しいだけでは、上達は無いのかもしれませんが、楽しんで練習できることはとても重要なことだと感じました。
私事ですが、来年から教員になることが決まっており、どうしたら中⾼⽣が楽しみながら、⾳楽が好き!という気持ちを持ち続けながら、合唱練習に取り組んでいけるのか?と良く考えています。曲を思ったように歌いこなすためには、発声練習も必須ですが、⽣徒に前向きに取り組んでもらうためには、様々な⼯夫が必要だと思います。各々が思いついたことを実験的に取り⼊れたりしながら、いろいろな発声の取り組みができるのもよびごえの魅⼒かな、と思いました。
⼜、”Ma”のシラブルと3度幅の⾳程を使い、crescendoして頂点を迎え、次第にdecrescendoする練習も⾏いました。ここではcrescendo(⼜はdecrescendo)の幅や⼤きく(⼩さく)なっていくタイミングを揃えることを意識しました。ここでは発声練習としての、いわば⾃由な⾳楽表現に繋げるための技術練習ですから、楽譜に書かれている強弱記号とは少し意味合いが変わってくるのかもしれませんが、楽譜を読む際には、何故ここにcrescendoがあるのか、どういった演奏効果を狙って書かれたのかを考える事はとても重要なことだと思います。今、取り組んでいる、「⾵紋」にも強弱記号が沢⼭使われています。強弱記号をただの数値的な記号(fが1だとしたらffが2といったように、、)としてしか捉えられなかったら、演奏は無味乾燥なものになるでしょう。楽譜を読むということは本当に難しいな、、と感じるばかりですが、そのf(フォルテ)は柔らかいf?硬いf?どんな⾊?どんな⾹りがして、どんな気持ちになる??想像したら果てしなくありますが、あと本番まで2ヶ⽉ほど曲と向き合って、私たちらしい演奏ができたら良いなと、思います。やや発声の話から脱線した気もしますが、、笑笑
そして、今年最後の練習ということで、前々から⽬標にしていた「BIN-NAM-MA」の通しをしました。本当に通した“だけ”です笑 今回はそれぞれのパート毎に練習する時間をとり、練習の最後には全員で合わせられるようにしました。まだまだこれからです。練習においてこの期⽇までに、これをできるようにする!という⼩さな⽬標はとても⼤事ですよね。とりあえず、年末までの⽬標は達成しました!!ただ、この曲を演奏するにあたり、ただ通せて良かった、みんなで歌えて楽しいといったことの更に先にやる事はたくさんあるのではないか?そのような次元(という⾔い⽅が正しいかは分かりませんが)よりもっと上で、どうやって曲を表現するかを考えていかなければならないのではないか?、、何故なら多くの⼈が亡くなっている背景が曲に込められているのだから。といったことが、練習後のミーティングで団員から挙がりました。この曲はベネズエラで起こった⼤洪⽔をもとにつくられましたが、私が1番に思い出したのは、今年の9⽉に、私の故郷千葉県を襲った台⾵です。幸い私の住んでいる市はあまり⼤した被害ではありませんでしたし、千葉県全体でも死者、負傷者数としてはベネズエラの洪⽔に⽐べれば、軽かった(?)のかも知れません。しかし多くの⼈の⽣活に被害をもたらしたことには変わりなく、⾃然災害の恐ろしさや⾃然を前にした時の⼈間の無⼒さを感じます。練習に疲れても帰る家があることや、スイッチを押せば電気がつくこと、蛇⼝を捻れば⽔がでることすら、当たり前に感じていますが、本当はもっと感謝すべきことなんだな、と、、
⽇誌が若⼲シリアス展開になりましたが、当たり前のことを⼤事にして感謝できる⼀年にします。(あ、新年の抱負です。気が早いですが笑)
今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回は1年⽣の今城さんにお願いします。皆さん良いお年をお迎えください!! 濱野
…
12
December
2019
2019
【2019】よびごえ日誌 vol.027
はじめまして。4年声楽専攻の鈴木慧です。もう12月中旬ですね。冬は私が好きな季節です。空気が冷たく、木々は枯れ、どこか物悲しげな雰囲気がありますが、クリスマスやお正月などの行事があり、気持ちは高揚します。また、寒ければ寒いほど、春への憧れが募る気がしています。冬は風が強くて、自転車が漕ぎづらいので、歩いて生活してみるのもおすすめです。新しい発見があるかもしれません。
進路の関係でよびごえをおやすみしていましたが、日誌は読むようにしていて、そこから学び、着想を得て、時には団員の姿を見て元気をもらっていました。いざ自分が書くとなると、とてもわくわくします。
創立当初と比べると、団員も増え、組織としても整ってきたよびごえ。これからも、団としてはもちろん、それぞれが思いを書くこの日誌も続いていくといいなぁと思っています。
さて、今回の練習はまず1年生の谷さんが発声練習を担当してくれました。今回取り組む「風紋」という曲には、5度音程で響かせる箇所が多いため、それを中心に彼女の工夫が散りばめられたものでした。低声パートが根音、高声パートが5度音を歌い、ばらばらに並び、響きが混ざるようにする、2.3人のグループをつくり5度音程でクレッシェンド、デクレッシェンドをグループ内で手の動きで示し、体現するというものでした。手の動きで示すという視覚化をすると、わかりやすいです。
グループによっては手の動きが何かの儀式のようでアイスブレイクになった、終始にこやかな発声練習でした。初めて担当してくれた谷さんに拍手です!
続いて「BIN-NAM-MA(ビンナマ)」の練習です。ダンス経験者の松本さんを中心に振り付けの確認をしました。ビンナマは注訳がスペイン語、英語で書かれていて、団員一同大苦戦しています。私も英訳をしましたが、解釈が難しい箇所がありスッキリする答えがなかなか見つかりません。
作曲者はなぜこのような振り付けを入れたのだろう、なにを表しているのだろうと考え、1人に任せるのではなく、それぞれが考え、全員の表現が集まったよびごえオリジナルのビンナマが作り出せればと思います。
また、毎回の練習でここまではやるという小さな目標を設けて、本番という大きな目標を見据えたいものです。そして本番という目標の先には、より大きなものが待ち構えているのだろうと思います。結果も大切ですが、そこに至るまでの過程は、より大切にしていきたいとしみじみと感じています。
次回の練習では音と動きを伴った練習、「風紋」にも取り組みたいです。
松本さん、先導を切ってくれてありがとう!
練習後のミーティングでは、全員が思ったことや感じたことを発言し、お互いに気遣いながらも伸び伸びとしていました。久しぶりに練習に参加した私を快く受け入れてくれた団員たちに感謝しています。
春コンまでの練習回数をざっと数えるともうあと1桁です。私がよびごえとして活動できるのもそれまでだと思うと、自然と春コンに対する思い入れが強くなります。今年は難曲ですが、これだけ人数がいれば、それぞれの得意分野を活かし、意見を出し合い、能動的に動くと、今のよびごえにとって難曲ではないかもしれません。はやく曲を楽しみ、作曲者や作詩者の意図を汲めるようにしたいです。個人的な目標は1月頭の練習までに暗譜です。がんばります!
次のよびごえ日誌は、歌もピアノも楽器をなんでもできて、笑顔が素敵でみんなのアイドル!スーパーマルチプレイヤー濱野瑞貴にお願いしたいと思います。
皆さんお体にお気をつけてお過ごしください。それでは! 鈴木…
02
December
2019
2019
【2019】よびごえ日誌 vol.026
こんにちは。本日のよびごえ日誌はテノールパート4年の笛木和人がお届けします。常連の皆様には初めまして。お邪魔します。さあ何を書こうかな。ワクワクしますね。随所に余談を散りばめておきますので、どうか最後まで読んでいってください。
まず簡単に私の自己紹介をしておきます。所属はB類音楽専攻声楽科。好きな食べ物はミラノ風ドリアです。よびごえには1年生の頃からお世話になっていますが、その頃のよびごえはまだできたてほやほやでしたから、ホームページに交代で日誌を書くという文化はおろか、団体としての役職や制度などもあやふやでした。その辺りも随分きちんと整えられたものです。小田さんには頭が上がりません。
気づけば師走に突入してしまいましたね。教師の卵たちも大忙しです。
何より厄介なのは寒さです。寒いので暖房を効かせますね。すると冷気はどんどん下に溜まるので足下は余計に寒く、暖気はその上を覆うので呼吸すれば喉はカラカラに。歌えやしない。「いい歌はいい空気から」ということで、本日のボイトレは稽古場の空気をかきまわすところからスタート。
雨乞いの如く繰り返し腕を上げ下げする団員たち。そして部屋中をうろうろと歩き回る。ついでに(?)発声もする。腕の上下に応じて声量に強弱をつけます。成程、声と身体表現を連動させ声量を可視化することでより自然に息をコントロールでき、無理なく声が流れていきますね。
いい感じに暖気と冷気が混ざってきたので、次は隣の人の声を聞く練習。隣の人の声量に合わせて自分のそれも同じくらいに調節します。これを一列に並んでやってみると、強弱の意思がまるでウェーブのように伝わって楽しいです。
今回のボイトレで感じた課題は、一人ひとりがもっと幅広い強弱を出せるといいね、ということでした。早い話が、持ち得る強弱の幅が表現力に直結するのです。無論、いくらfと指示が書いてあったとしても、パートとしてのバランスを欠いてしまってはお話になりませんけども。たとえばBIN-NAM-MAにはp,mp,mf,f,ff,fffの6段階に渡る強弱記号が存在します。正確にはpiù forteとpoco più forteを加えた8段階になりますし、さらに厳密にいえば声の強弱はデジタルではなくアナログですから、その間隙を埋める無数の強弱段階が在ることを私たちは知っています。
ふと、自分にはどれだけの引き出しがあるのか気になりました。たまには自分の限界を知っておくのもいいかもしれませんね。
さて本日の稽古はというと、機械的な音取りと演奏指示の確認という緻密な譜読みの一時間でした。
時折ものすごい不協和音が鳴り響いてびっくりしますが、楽譜をよく見るとどうやら合っているらしい。こんな感じで手探りで少しずつ進んでいきます。これがなんだか懐かしい感覚で、えも言われぬ面白さです。普段は接しないような異様な合唱曲に取り組んでいると「あ、よびごえだな」という正体不明の安心感に囚われます。もはや感動すら覚えます。
音取りが中心となるとあまり実況向きの内容ではないかと思いきや、一つ興味深い発見があったのでご紹介しましょう。
鍵盤ハーモニカ。
小学生の頃に触れた覚えがありますか?あれです。ピアノのように鍵盤楽器でありながら、息によって音色をコントロールするという特徴を持つため、歌うような旋律を奏でることができるのです。音取りの際「このように」と言って模倣させるだけなら、ピアノよりも優れていると言っても過言ではないでしょう。すごいでしょう鍵盤ハーモニカ。たまには押入れから引っ張り出してきませんか。シールとか貼ってあったら懐かしい気分に浸れると思いますよ。知りませんけど。
いかがでしたでしょうか。とりとめもないことで埋め尽くしたきらいもありますが、これで私のよびごえ日誌は終えようと思います。特に大したことは書いていませんね。それでも実に自分らしい文章が書けたと思います。私はそれだけで満足です。
次回は同期の4年生で同門の鈴木慧にお願いしようと思います。これからも朝晩はぐんと冷え込みますから、くれぐれもご自愛くださいね。それでは。 笛木…
14
November
2019
2019
【2019】よびごえ日誌 vol.025
こんにちは、B類声楽専攻一年の松本です。約一ヶ月ぶり二度目の登場です。まずは小金井祭お疲れ様でした!皆さん、よびごえ以外にもたくさん出番を抱えていながらも、良い演奏ができたのではないでしょうか。私個人は反省点が多く満足はできていないのですが…ちなみに私は「お母さん」を実の母の前で歌いました。
発声練習は、一年生が音形や母音を決めて行いました。どんなことを達成して、そのためにどんな練習をするのか考えるのは大変なことだと改めて実感しました。高校までの合唱部では発声練習がワンパターンになりがちだったのですが、よびごえの稽古では毎回違うことをしています。よびごえの発声練習は必ず今後に活きてくると思っています。
今回からはついに!春こん。の稽古がスタートしました。
今年は「自然」をテーマに、こちらの二曲を選びました。
・混声合唱「風紋」より4.風紋 詞:岩谷時子 曲:石井歓
・BIN-NAM-MA(ビンナマ)曲:A.Grau
初回稽古ということで、風紋の音取りとビンナマの大まかな説明を行いました。
風紋はテンポを落として、正確な音とリズムで歌えることを目標に音取りを進めました。人数が少なく、女声2パートしかいませんでしたが、自分の声も周りの声もよく聞こえてきました。ソプラノとアルトは一緒に動くことが多いため、テンポを上げても今回と同じようなハーモニーを作れるよう練習したいと思います。
絶え間なく「風」という言葉が繰り返されますが、それぞれどんな風なんだろうと考えながら歌っていました。楽譜を見るだけでもひとつの風を感じることができます。これから稽古を重ねて、どんな風を吹かせることができるのか、とても楽しみです。
ビンナマには踊りを伴う箇所があり、その振り写しや動きの確認を担当している関係で、説明は私がさせていただきました。注釈がすべて英語で書かれているため、説明にはかなり苦労しました。(拙い説明を温かく聞いてくださった皆さんありがとうございます!)
踊りも一通りやってみましたが、私を含め、かなり苦戦していました。これを歌いながらやるのか…という心の声が聞こえるようでした。
実は、ビンナマという曲が完璧に演奏されたことはないと言われています。Web上にある動画をいくつか確認しましたが、全く同じ動きをする合唱団は二つとないのです。注釈には書かれていないアレンジを加えている団が多いです。振り写しの準備を少しずつ進めていますが、正直なところ動画はあまり参考になりません。しばらくは注釈に書いてあることだけをしようと思っています。
言ってみれば、楽譜に忠実に演奏するだけでもよびごえオリジナルのものになってしまうんですね。そう考えると少しだけ楽しくなってくるのは私だけでしょうか?
人生でここまでの難曲に取り組むことはそうないと思います。今はただ不安でいっぱいですが、この曲を乗り越えたら何も怖くなくなるはずです。地道に頑張りましょう!よろしくお願いします。
今回は稽古時の写真がないので、関係のない写真で恐縮ですが、こちらを載せます。
一年生7人で打ち上げをしました!小金井祭ではよびごえ全体の本番とは別に音楽科一年生の演奏カフェで二曲歌いました。みんなのリクエストで焼き肉食べ放題です。ほとんどノンストップで食べて話した90分でした。話題はやはり合唱のことばかりでした。
「春こんも頑張って、また美味しいご飯を食べよう」と約束しました。一年生はまだまだ成長します!
一気に冷えこんだせいで、体調を崩す人が増えています。皆さんお気をつけて…
次の日誌は、春こんからよびごえに復帰される四年生の笛木さんにお願いします!お楽しみに! 松本…
24
February
2019
2019
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2019 金賞
「一般の部 フォルクロア部門」金賞(一位)混声合唱組曲『真南風の祈り』より「今日ぬ日」(西表島:田植え歌より/中村透作曲)
混声合唱のための『八重山・宮古の三つの島唄』より「狩俣ぬくいちゃ」(松下耕作曲)
~Message from F. Prinsloo~
What a beautiful and interesting composition. I really enjoyed listening to it! The choir has a beautiful sound and is very sensitive and the phrasing is very beautiful! Congratulations on…
11
February
2018
2018
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2018 銅賞
”8 Motets”より Benedicta es caelorum Regina(prima pars)(Jean Mouton 作曲)“Huit Chansons françaises”より Margoton va t’a l’iau Pilons l’orge(Francis Poulenc作曲)
※聴いてくださる際は音量を大きくしてください。ヘッドホンの方が良いかもしれません。…
11
February
2017
2017
春こん。 東京春のコーラスコンテスト2017
女声合唱曲集『わたしは風』より「歌」(新川和江作詩/木下牧子作曲)El Hambo DD(Jaakko Mäntyjärvi作曲)…